【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯12「行きたくなる学校」をつくるには?
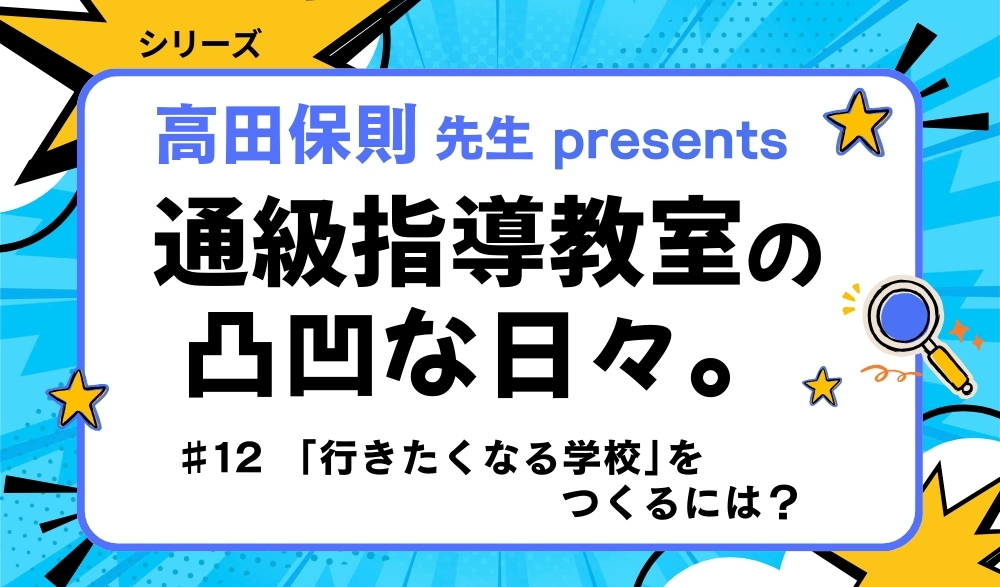
通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。
執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則
目次
はじめに
北海道オホーツク地方の小学校で、通級指導教室を担当している高田保則です。日々の指導の中で出会った子どもたちとの経験から感じたことを綴っています。ここに登場する事例は複数の子のエピソードを再構成した架空のものですが、実際の教室での空気感や子どもの姿をできる限り反映しました。
今回のテーマは「行きたくなる学校」です。学校現場で過ごしていると、子どもの登校意欲の低下を肌で感じます。「学校に行きたくない」とつぶやく子が増えた今、私たち教育関係者はどう応えればよいのでしょうか。実際の子どもの変化を描きつつ、教育政策の最新動向にも触れながら「行きたくなる学校」の条件を考えてみます。
1.学校に行きたがらない子どもたち
「学校に行きたがらない子が増えている」――これは現場の教職員の実感であり、統計にも表れています。文部科学省の調査によれば、不登校の児童生徒数はここ数年、過去最多を更新し続けています。
朝の児童玄関で、ランドセルを背負ったまま動けずにいる子がいます。「今日は体が重い」と小声でつぶやき、下を向いたまま靴を履き替えられません。別の子は布団から起き上がれず「あと5分」とつぶやき続けます。教室に来ても机に突っ伏し、「何もやりたくない」とため息を漏らす子もいます。
「朝起きたら、なんとなく学校に行きたくない」
「家でゲームをしていたい」
「動画を見るのが一番の楽しみ」
こうした言葉の裏には、生活環境の変化や、学校へ通うことの必然性を感じにくくなっている現実があります。
2.欠席が増えた背景
不登校の要因として、「コロナ禍で配付された情報端末が原因」という説明を耳にすることがあります。しかし家庭に戻った子どもたちが触れているのは、スマホやゲーム機、動画サイトです。何かと制約が多い学校の情報端末にはほとんど目もくれません。
ある子は「ゲーム機で友だちと遊ぶから、学校に行かなくてもつながれるよ」と言いました。別の子は「YouTubeには、先生の説明よりわかりやすい動画がある」と笑いました。自宅にいながら友人と交流し、知識も得られる環境が整った今、学校に行く意味を実感しにくくなっているのです。
3.公教育の転換点
公教育はいま、大きな転換点を迎えていると言えます。長年学校現場に身を置いてきた私には、そのように見えます。
学力向上の旗を振り続けても、子どもは学校を魅力的に感じません。宿題やテストを増やせば一時的に成績は上がるかもしれませんが、「またプリントばかりだ」とため息をつく子もいます。学習意欲を育むどころか削いでいる現実があります。
一方で、友だちと協力して発表を完成させた場面では「やったね!」と拍手が広がり、課題を解決できた時には「次はもっと工夫しよう」と前向きな声があがります。「協力」「達成感」「共有の喜び」こそが、学習意欲を育み、ひいては登校意欲を支えることになるのです。
4.学校でしか味わえない体験を
学校でしか味わえない心地よい体験を提供することが必要だと私は感じています。
それは決して大がかりな取組ではなく、ちょっとした工夫でも実現できることです。例えば、友だちや先生と話す楽しさ、みんなで協力して成し遂げる喜び、学び合うことでの成長、できなかったことができて褒められる経験などです。
こうした日々の体験の積み重ねが、子どもを明日の学校へと誘うのだと思います。
5.通級指導教室で実践する探究的な学び
私が通級指導教室で取り組んだ実践を紹介します。いずれも子どもの関心を出発点にしています。個別指導での探究的な学びというものになるのでしょう。
(1) 段ボール太鼓づくり
今やゲーム機は、家庭の必需品になっています。家族がそれぞれ好みのゲームを楽しんでいるという話をよく聞きます。Rさんは、学習に対する自信を持ちたくて通級指導を希望しました。工作が大好きで、おうちでは、ほどほどにゲームを楽しんでいました。
「高田先生、作ってみたいものがあるんだけど・・・」
そう言ったRさんは、動画を紹介してくれました。それは、段ボール工作の達人のYouTuberが、ゲームセンターにある『太鼓の達人』のゲーム機の太鼓を完全再現して制作している動画でした。
「完成したら、みんなに遊んでもらえるよね。」
「おもしろい♪ やろう!」
校区のお店にご協力いただき、大量の段ボールを集めました。達人の動画を見ながら、制作を進めました。作品は、休み時間に通級指導教室に遊びに来た子どもたちの注目の的になりました。Rさんは、自分が取り組んでいる学習活動をみんなに話しました。
Rさんにとって学校は「挑戦と共有の場」へと変わっていったのです。

(2) 黒板アートで自己表現
Sさんは、朝起きたら何となく学校に行きたくない日があると言います。器用でなんでもできてしまうSさんには、熱中できるものがないのかもしれないと私は見立てました。そこで、イラストを描くのが好きなSさんに、通級指導教室の使われていない黒板を指さして「ここに絵を描いてみない? 」と提案しました。Sさんの目が輝きました。
Sさんは、本格的な黒板アートの動画を検索して、描き方の研究を始めました。次第にでき上がっていく作品を他の子が興味深げに眺めていました。
Sさんにとって学校は「自分を表現し、認められる場」となったのです。

(3) 都市伝説を教材化
Tさんは、文字の読み書きが苦手で、通級指導教室で平仮名を習得する学習に取り組んでいました。
「ひらがなはむずかしい。いっぱい見ていると、わからなくなる。」
Tさんはそう言いました。平仮名を書こうとしても形が崩れたり、似た文字を混同してしまったりしました。自信をなくしたのか、国語の時間には机に顔を伏せてしまうこともありました。
そんなTさんは、「怖い話」が大好きでした。ある日、「高田先生、きさらぎ駅って知ってる?」と話しかけてきました。
ネットで見つけた動画を何度も見返し、国語ノートの片隅には、『きさらぎ』と繰り返し書き連ねていました。
私はTさんの関心を生かして、「じゃあ、きさらぎ駅の看板を作ってみない?」と提案しました。大きな段ボールを用意すると、Tさんは真剣な表情でマジックを握りしめました。ゆっくりと、でも力強く『きさらぎ』と書いていきます。書き終えたときのTさんの顔には、達成感の色が浮かんでいました。
看板を教室のドアに貼り出すと、「何これ!?」と子どもたちが集まりました。上映会のように動画を観る輪ができ、その中心でTさんは、「これはね…」と説明役を務めました。
Tさんにとって学校は、苦手な勉強をするところから、「学んだことを活かして友だちとつながる場」に変わったのでした。
6.子どもに合わせる特別支援教育
特別支援の現場では、しばしば「子どもを集団に近づける」ことが指導の目的になりがちです。「周りに合わせられるようにする」ことが優先され、「子どもの思いに合わせる」という視点は脇に追いやられがちです。
ここで紹介した実践は、子どもの関心や得意を出発点とし、それを小さな探究的な学びに育てていく学習活動です。子ども自身が友だちを巻き込み、集団との関わりを広げていくのです。
「子どもを学校に合わせる」のではなく、「子どもから学校を変えていく」実践です。
7.学校の「楽しい」を価値づけする
ここで重要なのは、「楽しい」が一時的な気晴らしに終わるのではなく、学習意欲の底上げにつながる教育的意味を持つことです。
心理学の自己決定理論では、『有能感・関係性・自律性』が満たされるとき、人は内発的に動機づけられるとされます。
・できた!=有能感
・みんなと分かち合えた!=関係性
・自分の関心から始められた!=自律性
この3つが揃ったときに生まれる感情が「楽しい」であり、それが子どもを次の挑戦へと導きます。Rさん、Sさん、Tさんの事例はいずれもそれらを具体化しています。
「楽しい」を基盤とする体験は、学習意欲を広く底上げする力を持っているのです。
8.「楽しい」は教育政策も動かす
ちょうど今、中教審の教育課程企画特別部会では、次期学習指導要領に向けた論点整理が行われています。そこで強調されたのは次の3点です。
①「主体的・対話的で深い学び」の実装(Excellence)
②多様性の包摂(Equity)
③実現可能性の確保(Feasibility)
はからずも私の実践は、これら3つを現場で具体化した試みだと感じます。
・子どもの関心を起点に自ら探究する姿=Excellence
・個々の特性や興味を尊重する姿勢=Equity
・段ボールや黒板など身近な素材で工夫できる取組=Feasibility
「子どもに合わせた探究的な学びの個別指導」は、中教審が描く教育の方向性と同じ方を向いていると考えます。
9.おわりに
学校は、子どもにとって「行きたくなる場所」でなければなりません。そのためにはまず、私たち教育関係者自身が問い直す必要があります。
「いまの学校は、自分にとって楽しいだろうか」
「どうすれば、もっと楽しくできるだろうか」
大人が楽しく働く学校の延長線上に、子どもが「行きたい」と思える学校があります。私はこれからも、子どもの思いに寄り添いながら、小さな探究的な学びの実践を積み重ね、子どもとともに「楽しい」を創り出していきたいです。その先にこそ、学習意欲の底上げと「行きたくなる学校」の実現があると信じています。
<参考資料・文献>
〇文部科学省 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
〇文部科学省 中央教育審議会教育課程企画特別部会 『論点整理(素案)』 2025年9月5日
〇『「面白い!」は最高の動機づけ ~自分の足で歩く子どもを育てるために~』 春日智稀、小学館みんなの教育技術 (2025年9月8日 閲覧)
〇特集「行きたくなる学校から考える不登校」 月刊生徒指導 2025年9月号 学事出版
〇『【ダンボール工作】ゲームセンターの太鼓の達人をつくってみた!』 DanCreator / 段クリエイター(2025年9月8日 閲覧)
〇『チョークアート キレイに仕上げる塗り方のコツ/お悩み解決』アトリエ チョークアートmili (2025年9月8日 閲覧)
〇映画『きさらぎ駅』公式サイト (2025年9月8日 閲覧)

高田保則先生プロフィール
たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。

