「マイクロアグレッション」とは?【知っておきたい教育用語】
今年7月に行われた参院選で掲げられた「日本人ファースト」という言葉。この言葉が、XをはじめとしたSNSで広がっていった背景には「マイクロアグレッション」と呼ばれる、無意識な差別的言動が深く関与しています。今回はマイクロアグレッションの概要と、学校現場におけるマイクロアグレッションについて解説していきます。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
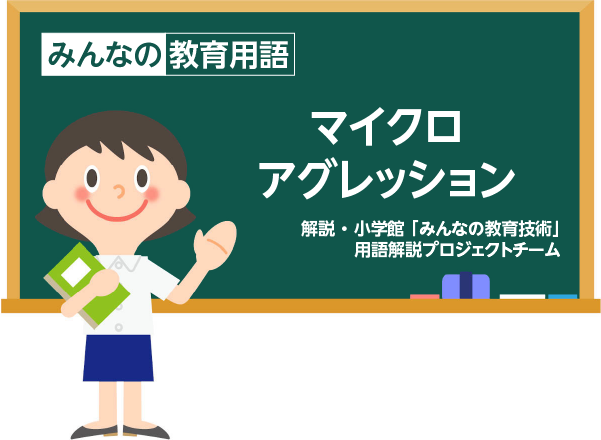
目次
マイクロアグレッションとは
【マイクロアグレッション】
無意識のうちに行われる特定の人や集団に対する差別的な言動のこと。言動を行った本人にとって悪意がない場合が多く、むしろ親しみのつもりで行われるケースなどもあるため、自身の言動が差別的な言動であると自覚しにくいという課題がある。
マイクロアグレッションの多くは、人種や国籍、文化、ジェンダー、性的指向など個人のアイデンティティーに関わるトピックに影響するため、受け手は差別や偏見を感じ取るものの、相手が無意識・無自覚であることから、あえて指摘しない、我慢してしまうことが数多くあります。しかし、マイクロアグレッションが与える攻撃は、どんなに小さいものでも、少しずつ相手の心をむしばみ、心理的なストレスや集団からの疎外感を蓄積することにつながります。
マイクロアグレッションが生じる場として、学校も例外ではありません。近年、多様性社会を構築するために、インクルーシブ教育の重要性が見直され、より積極的な指導が求められています。インクルーシブ教育の実践においては、教師自身がマイクロアグレッションを行っていないかを内省する必要があります。
学校で起こりやすいマイクロアグレッションには、次のような例があります。
●ジェンダーに関するもの
「女性で理系なんて大変だよ」 → 理系=男性という先入観に基づいた偏見
「男なのに泣くなんて、みっともない」 → 性別に基づく感情表現への否定
●人種や文化、国籍に関するもの
(日本で育った子どもに対して)「日本語上手だね」 → 「あなたは日本人ではない」と勝手に認定
●障がいに関するもの
「○○(障がい)なのに頑張っているね」 → 障がい者を弱者と見なすような発言
こうした無自覚に行われるマイクロアグレッションが、子どもたちの心を傷つけるだけでなく、子どもたちの価値観や考えを狭めてしまうことにもつながります。
マイクロアグレッションにつながるアンコンシャス・バイアス
では、なぜこうしたマイクロアグレッションが生じるのでしょうか。理由の一つに「アンコンシャス・バイアス」と呼ばれるものがあります。アンコンシャス・バイアスとは、誰にでもありうる、無自覚の偏見や固定概念のことで、その人が経験してきたことや見聞きしてきたことに基づいて形成されます。
「女の子はかわいいもの、男の子はかっこいいものが好き」といった言説は一見、問題のないように思えますが、時として誰かの心を傷つけたり、可能性を制限したりするアンコンシャス・バイアスになりかねません。
また、アンコンシャス・バイアスが行動となって表れてしまったとき、結果としてマイクロアグレッションを引き起こしてしまうこともあります。そうならないために、政府広報オンラインでは、「アンコンシャス・バイアスを減らす3つのポイント」を周知しています。(一部抜粋、編集して紹介します。)
Point1 「べき」「普通は…」に注意!
「~するべき」や「普通は~だよね」といった、押しつけた決めつけの言葉が出そうになったら、一度立ち止まって、「本当にそう言い切れるのか」「なぜ、そのように思ったのか」を考えてみましょう。
Point2 相手の「サイン」を見逃さない
他者と話しているとき、自分の言葉によって急に相手の表情が曇ったり、声のトーンが変わったりした瞬間を見逃さないようにしましょう。自分の言動に相手を傷つけるものがなかったか振り返ることが大切です。
Point3 常に自分に問いかける
アンコンシャス・バイアスは無自覚であることから完全に払拭することは難しいです。そのため、常に自分の言動を見つめ、内省することが大切です。違和感のあったことをメモするなどして、自分の考え方や物事への視点を捉え直し、傾向をつかめるように心がけましょう。
以上のポイントを日常生活から意識するだけでも、自分自身の考えや価値観をアップデートし、より円滑な対人関係を構築するほか、アンコンシャス・バイアスによるマイクロアグレッションの発生防止にもつながっていきます。

