<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #21 高知大学教育学部附属小学校2年B組④<前編>

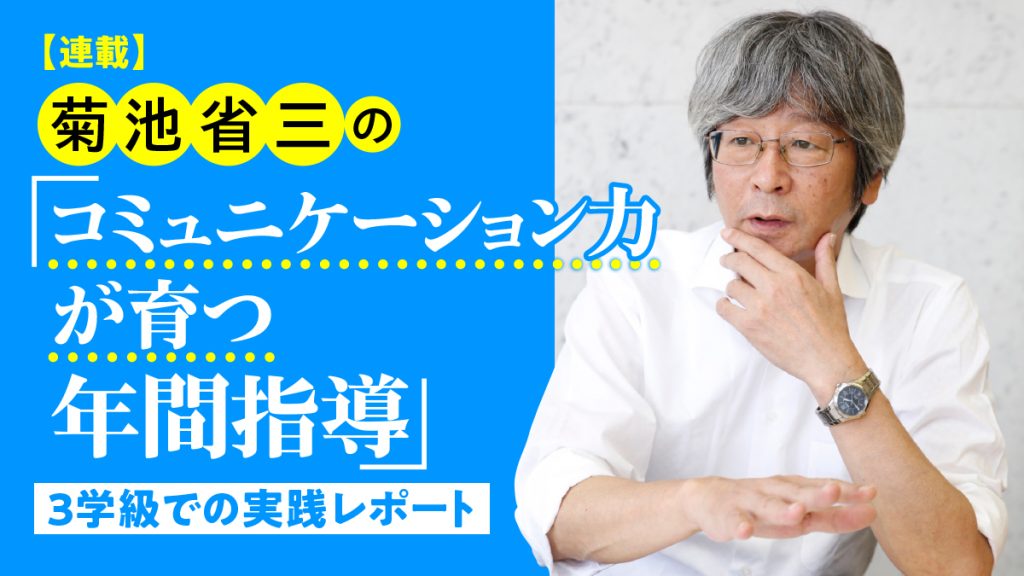
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする好評連載。今回からは高知大学附属小学校の小笠原学級(2年生)における2025年2月の授業レポートをお届けします。菊池先生と小笠原先生による、2時間続きの合同授業の記録です。

目次
担任・小笠原由衣先生より、学級の現状報告
相変わらず日々のちょっとしたトラブルはありますが、安定してきました。1年後に目指していた学級の姿に近づいてきています。きつい言葉を使って自己アピールする子はほとんどいなくなりました。
声が小さい子の発言も、周りの子たちは耳をすませて聞いています。聞こえないときには「スピーカー係」の子が補ってくれます。以前は全く声が出なかった子も、授業中に手を挙げて発言するようになりました。
時折、きつい言葉が聞こえることもありますが、基本的には「いいね」「大丈夫だよ」など、温かい言葉があふれるようになってきました。
今回の授業は、「1年間取り組んできたことを、参観の先生方に伝える発表をしよう」と、子供たちと計画しました。プレゼンテーション活動を行う授業ですので、彼らのチームワークやパフォーマンス力が発揮されることでしょう。子供たちの成長を感じる授業にしたいと思います。
菊池先生と小笠原先生の合同授業レポート
小笠原先生が、
「2年B組では1年間を通していろいろなコミュニケーションの活動をしてきました。今日はみなさんが待ちに待った『2年B組の成長を祝う会』をします」と話すと、子供たちはみんな、わくわくした表情でいっぱいになった。
<プログラム>
●菊池先生のお話
↓
●班ごとに、1年間頑張って取り組んできたことを選んで発表
↓
●班の発表ごとに他の全チーム(班)からの感想と質問
↓
●授業参観者と菊池先生からの感想と質問
↓
●8班全ての発表後、審査
<審査基準>
①教室に入るとき、出るときの態度
②他チームの発表の聞き方
③服装は正しいか
④真剣さ、チームワーク
⑤はっきりとした、ちょうどいい大きさの声か
⑥発表の内容はよいか
⑦表現力(表情、笑顔)、感動させる力があったか
「審査した後、賞を獲得したチームを発表します。賞は8つあります。みなさんにも、自分の班以外でよかった班を選んで、『子ども賞』を決めてもらいます。じゃあ、頑張るぞ。えいえいおー!!」と小笠原先生が声をかけると、子供たちも元気いっぱいに、
「えいえいおーっ!!」。
菊池先生が、
「発表の聞き方も審査の対象になるんだね。つまり、聞いていなかったら、だめなんだね。 コミュニケーションはみんなと仲良くなることだから、友達を大事にし合う勉強です。今日のみなさんの発表を楽しみにしています。じゃあ、指の骨が折れるくらい、いや、手首がちぎれるくらい拍手!」
と声をかけると、子供たちの割れんばかりの拍手が教室に響き渡った。
![]()
「成長を祝う会」には、儀式的な意味もあります。そのためには、集団としてのシステム、みんなが楽しむための “型” が必要です。
それらをきちんと確立し、守った上で楽しむことが大きなポイントです。そのため、今回はコンクール制にして、他班の発表を聞く態度も審査の対象に含めました。
早速、発表がスタート。
1班「あふれさせたい言葉」
テロップを用意して1人ずつ発表した。
●発表内容
「あふれさせたい言葉の授業をすると、『はあ?』『いや』『めんどくさい』などのカチコチ言葉が少なくなります。笑い声が増えて、みんなが仲良くなります」
●発表の方法
①まず1人で「よい言葉」を考える
②言葉が重ならないように、班で整理し、数える
③班ごとに黒板にその数を書き、発表。それを何回か繰り返してみんなに伝える
●この活動をやってよかったこと
「あふれさせたい言葉が増えて、嫌な言葉が減ってきました。『がんばれ!』『いいね』『ナイス!』という言葉かけが増えてきました」
「あふれさせたい言葉の授業を受けたら、優しい言葉や楽しい言葉が増えたので、全国でやってもらって、優しい人を増やしたいです。全国の学校でもやってください」
●他班から1班への質問・感想
質問「一番あふれさせたい言葉は何か」
1班の回答「『頑張れ』と『いいね』です」
感想「言葉をすらすら言えたのですごい」
質問「一番なくしたい言葉は何か」
1班の回答「言いたくありません」
感想「一人ひとりが長い文章を発表していたのがすごかった」
●参観者からの感想
「このクラスでよく使ったなあという言葉を知りたい」
1班の回答「『ナイス!』です」
菊池先生は、
「発表で『あふれさせたい言葉が増えると優しくなる』と言っていましたね。言葉が変われば心が変わる。だから成長したんだね」と、1班に感想を伝えた。
さらに、4月と1月のあふれさせたい言葉の表を見比べながら、
「これだけ言葉が増えていったのは、続けてきたからです。言葉のレベルはどんどん上がっていく。だから成長できるんだね」と伝えた。
![]()
各班、発表の際には声をそろえたり、一人ひとり分担したり、即興劇をしたり……。「協力」=「分担とフォロー」です。フォローし合ってこそ、お互いに責任感が生まれます。それが本当の協力なのです。
子供たちは、「あふれさせたい言葉を繰り返し続けること」の大切さについて説明していました。1年間を通して取り組んできた結果、子供たちの語彙が増えました。その背景には、「言ってもいいんだ」という教室の温かい空気ができたこともあります。
こうした活動は、ともすれば1回やっただけで終わってしまいます。それでは、「取り組んだ」という教師の自己満足に過ぎません。子供たちに言葉の力をつけることの意味と目的を、教師が常に肝に銘じておく必要があります。
1班の子供たちが、「繰り返し」という言葉を使ったところに、活動の本質が表れていると感じました。
言葉は進化していきます。例えば、価値語を示すと、子供は「言葉って、自分で作ってもいいんだ!」と衝撃を受けます。しかし教師が価値語実践を続けていくことで、やがて子供たちが自ら価値語を作るようになっていきます。
「言葉が自分たちを育てる」ことに子供たちが自ら気づく──。そこまでいかないと本当の意味で言葉の力が育ったとは言えません。言葉の力を伸ばす活動は、単にいろいろな言葉を覚えることにとどまらず、そうした高いレベルに達するまで、繰り返し行っていく必要があるのです。
2班「いろいろなゲーム」
●発表内容と発表の方法
「背中にシールを貼るゲームやフルーツバスケットなど、いろいろなコミュニケーションゲームをやってきました。特に楽しかったのがフルーツバスケットです。実際にやってみます」
椅子を円形に並べて4人が実演した。
次に、「餃子じゃんけん」ゲームについて発表。
「なぜゲームをするかというと、友達のことをもっと知ったり仲良くなったりするからです。楽しみながら仲良くなれます」
●他班から2班への質問・感想
感想「一人ひとりが前に出てしゃべっていたのがよかった」
感想「みんなが見やすい角度で発表していた」
感想「実際のゲームをやっていたので、わかりやすかった」
●参観者からの感想
「実演してくれたのでわかりやすかった。『楽しみながら仲良くなれる』という言葉がとてもいいですね」
菊池先生は、
「相当練習したことがわかりました。リアル感がよかった。4人のカラダと表情が柔らかいから、みんなからの感想もたくさん出ました。発表している人と聞いている人が一体になっている様子が見られました」と感想を伝えた。
![]()
楽しい活動型のゲームと論理的思考力を養うゲーム。2班が発表した学習ゲームは、単に楽しむためのものではありません。教師は、例えば話し合い活動の際、「あのときゲームでやったことが役立っているね」などと言葉をかけ、意識的にゲームとコミュニケーション活動とをつないでいくことが大切です。
ゲームを普段の授業から切り離してしまうと、「楽しかった」「友達と仲良くなった」という目先の効果だけで終わります。授業もセットで考えていくことが大切です。
3班「成長ノート」
●発表内容と発表の方法
「自分が成長したことを振り返り、工夫した文章を書く活動です。週に1回やっています。先生がお題を出して、それについて書きます」
成長ノートを例示:「今日の遠足」
・自分が成長したこと
・A(成長アップ)の道へ行くために頑張りたいこと
・先生のコメントは元気が出る
例として、1人の成長ノートをモニターに映し出した。
「成長ノートを書くことで、自分が成長したことをいっぱい知ることができたし、あふれさせたい言葉やなくしたい言葉も集めることができました。私たちにとって、成長ノートはとても大切なものです」
●他班から3班への質問・感想
感想「すらすら言えていた」
感想「みんなで言うときに、声がそろっていて姿勢もよかった」
感想「みんな、シャキッと発表していた」
感想「成長ノートだけでなく、先生のいいところも言っていたのがよかった」
●参観者からの感想
「『自分の成長を知ることができた』という発表がよかった。伝えようという姿勢がとても伝わってきた」
菊池先生は、
「発表する人の声がちょうどいい声でした。『私たちにとって』と効果を話していました。みんなのおかげで成長できるんだ、ということに改めて気づいて、感動しました。成長ノートは、自分自身とのコミュニケーションですね」と感想を伝えた。
4班「係活動」
●発表内容と発表方法
「笑顔いっぱいのクラスにするために、係活動を始めました」
・2Bの係活動を例示
お笑い係……みんなを笑わせる
クイズ係……みんなが答えるクイズを作る
植物係……教室で植物を育てる
くじ引き係……一日の運を決める
マジック係……マジックを学ぶ
「係活動がある日は学校が楽しみになります」
●この活動を続けてきてよかったこと
「やった後、楽しくなります。『それ、いいね』と係活動をほめ合うこともできます。そして、活動の発表のとき、どんな内容かわくわくして、発表の力がつきます」
「“バイト” もできるから、いろいろな係を体験できます」
「考える力が成長します」
「みんなが笑顔になります」
「人と話し合う力が身につきます」
「係のとき、友達のいいところを見つけることができます。みんなをわくわくさせたいので、これからもいっぱいしていきたいです」
●他班から4班への質問・感想
感想「声も大きかったし、いろんないい言葉を使っていた」
感想「男子と女子が声を合わせていた」
感想「失敗しても止まらず、すらすら読んでいた」
感想「係活動の楽しさがよくわかった」
感想「1人ずつの発表がよかった」
感想「話を聞いて、係活動をいっぱいしたくなった」
●参観者からの感想
「人に聞こえやすい間と声がよかった。みんな笑顔で、係活動の楽しさが伝わってきた」
菊池先生は、
「係活動も、コミュニケーションの勉強です。『係活動をすると考える力がつく』という発表がありました。『自分はこういう仕事をしたいと工夫した』。つまり、工夫したことで、考える力がついたんだね。
『みんなに喜んでもらおう』という気持ちも伝わってきました。みんなが喜べて仲良くなれるようにと考え、工夫をして係活動をした。だから、係活動もコミュニケーションの勉強、ということなんだね」と感想を伝えた。
![]()
係活動は、学級のために自分がやりたい仕事をする活動です。学校でも、このような「自分の好きなことができる時間」を保証することが大切なのではないでしょうか。
また、教師が普段の授業の中で、全員に目を向けなければいけない場面が多く、気になる子と個別に向き合う時間がなかなか持てないときに、係活動の時間を利用してもいいでしょう。前向きに取り組んでいる子供に対し、個別にプラスのアプローチができます。

