メダカの観察を通して生命尊重の心を養う (小五 メダカのたんじょう)【理科の壺】

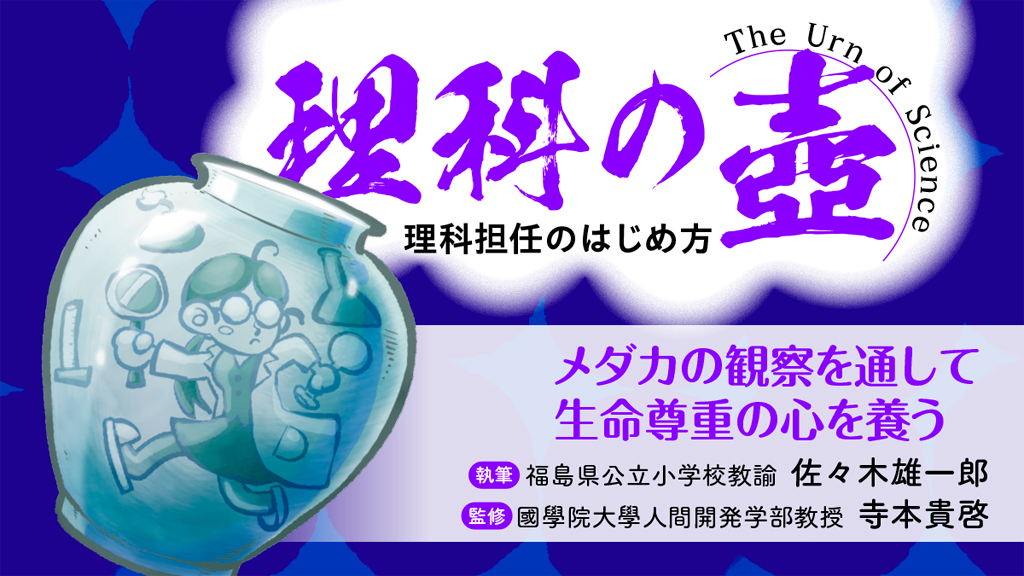
5年生では、メダカを育てることが多いです。その際、学級の水槽でみんなで育てることもあれば、個人個人で1匹ずつ育てることもあります。今回は、メダカをしっかり育てることで、生命尊重やほかの魚への適用について考えていく授業展開をご紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/福島県公立小学校教諭・佐々木雄一郎
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
5年生「メダカのたんじょう」では、メダカの卵に着目し、発生や成長について学びます。同時に、他の生命領域の単元と共に、生命を尊重する態度を養うことも目標になっています。今回は、生命を尊重する態度を養うポイントとして、対象(メダカ)と自分との距離を近づけることについて例を挙げて紹介します。
1 子どもが「メダカを育てる」ことの意味を自覚できるようにする
先生からいきなり
「今日から、メダカについて学習していきます」
と言われても、子どもにとっては寝耳に水です。
「学校ビオトープのメダカが絶滅危機だからなんとか増やしたい」
「使われていない大きな水槽でメダカを飼育して、全校生に見てもらいたい」
など、なるべく身近な目標を設定することで、子どもがメダカを育てることの意味を自覚できるようにしましょう。そうすることで、
「そのためには、何が必要か」
という視点で学習計画を立てることもできます。
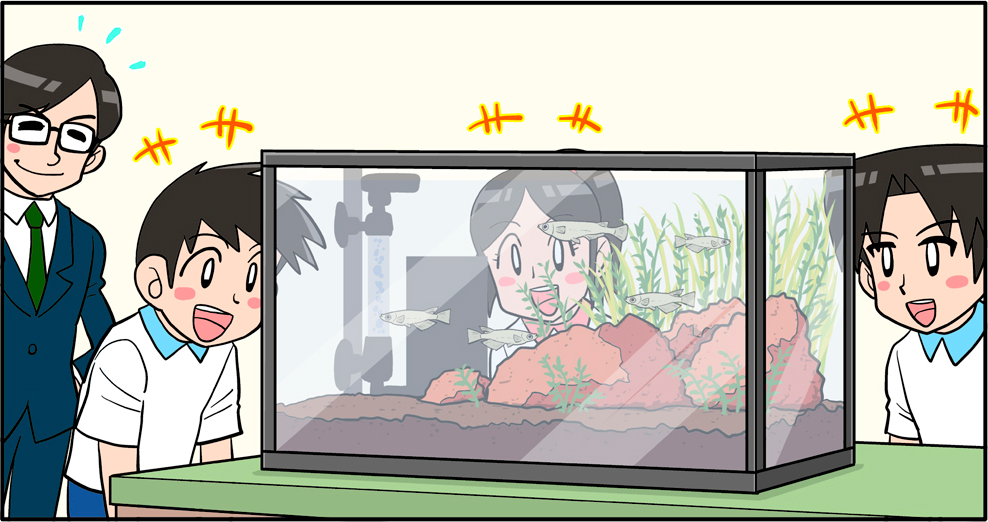
2 自分の手で卵を育てる機会をつくる
いよいよ、メダカの卵を育てていきます。できれば、1人1個の卵を準備したいところです。一人一人が育てることで、メダカとの心的距離が近づき、大切に育てようとしたり、こまめに成長を観察しようとしたりする心が育まれます。一度にたくさんの卵を準備することが難しい場合は2人組、3人組で育ててもよいでしょう。

