どう変わる?図画工作科の「新学習指導要領」改訂ポイントと授業改善アイディア
学習指導要領の改訂に当たり、図画工作科のポイントや授業改善の視点について、文部科学省の岡田京子調査官に、京都市立西京極西小学校の中下美華校長がお話をうかがいました。
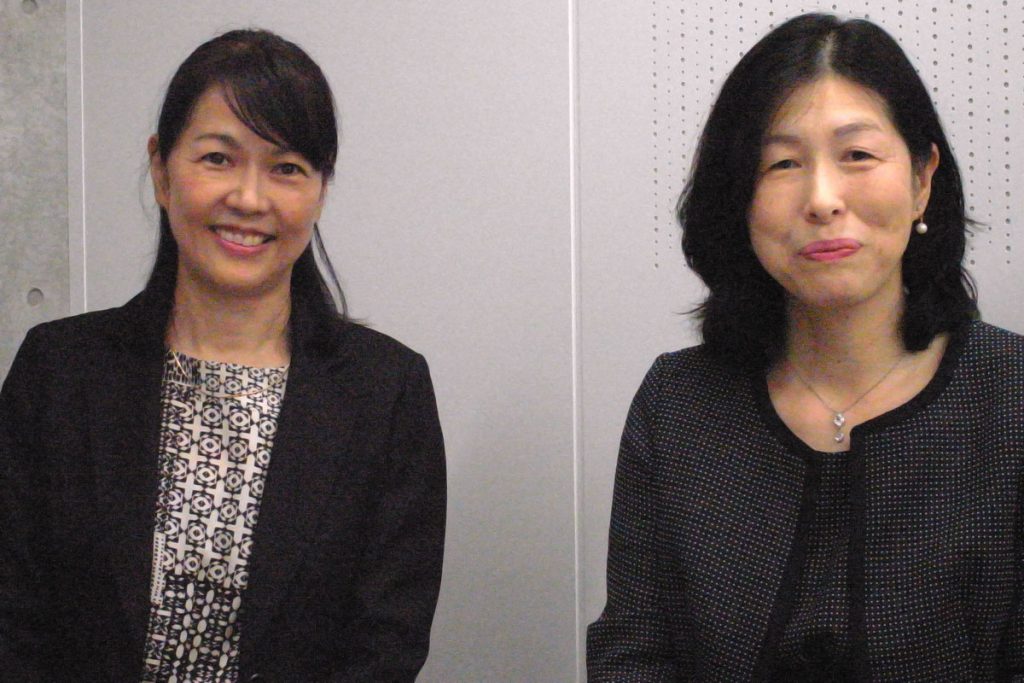
京都市立西京極西小学校校長・中下美華さん (右)
目次
今回の改訂の主要なポイント
中下 今回の改訂ポイントや現行との違いについて、教えていただけますか。
岡田 従来の図画工作科においては、例えば、発想や構想の能力、創造的な技能、鑑賞の能力など、資質や能力ですでに整理されていたところはありますが、今回の改訂では、目標を「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で整理して、育成を目指す資質・ 能力を明確に示していることが一番大きなポイントです。それに関連して、内容も整理され、例えば、A表現(1)は「思考力、判断力、表現力等」として、A表現(2)は「知識及び技能」の「技能」として整理されています。中下先生の学校は図画工作の研究指定校をされていますが、学校の先生方はどのように受け止めていますか。
中下 今までは、題材を考えるときに、造形遊びでどんな材料を使おうかとか、何を絵に表す題材にしようとか、まず内容について考えていたのですが、今回の改訂によって、資質・能力を身に付けさせるために、どんな題材にするかを考えるというように、内容からではなく、資質・能力から題材を考えるようになりました。授業をつくる際の視点が変わったと思います。
岡田 それはとても重要なことです。今回の改訂により、造形遊びをする活動と絵や立体に表す活動の両方の活動を行うことによって、資質・能力が育成されるということが、先生方により見えやすくなったという声もいただいています。
図画工作科 目標
「小学校学習指導要領 図画工作科の改訂のポイント」(文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・岡田京子)より
表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
⑴ 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解するとともに、材料や用具を使い、表し方などを工夫して、創造的につくったり表したりすることができるようにする。
⑵ 造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などについて考え、創造的に発想や構想をしたり、作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。
⑶ つくりだす喜びを味わうとともに、感性を育み、楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い、豊かな情操を培う。
造形的な見方・考え方について
中下 造形的な見方・考え方とは、どういうものでしょうか。
岡田 今回、すべての教科等で見方・考え方が示されました。図画工作科では、「造形的な見方・考え方」として、「感性や想像力を働かせ、対象や事象を、形や色などの造形的な視点で捉え、自分のイメージをもちながら意味や価値をつくりだすこと」と考えられると示しています。
ここでは特に、「自分のイメージをもちながら意味や価値をつくりだすこと」について説明しましょう。例えば、新聞紙の造形遊びを思い浮かべてください。最初、新聞紙は子供にとって「もの」でしかありませんが、触りながら破ってみたり、丸めてみたりすると、だんだんと自分の活動が生まれてきます。よく子供が、「先生、これ持って帰っていいですか」と言うことがありますね。その気持ちは、自分が手がけることによって、新聞紙が自分にとって価値のあるものになったことや、意味のある時間であったことが合わさって、そういう言葉になるのだろうと思います。図画工作科では、そのような活動にすることが重要です。
先生方には、「造形的な見方・考え方」を、子供たちにとってそのような意味や価値をつくりだす授業であったかどうかという自分の授業を改善する視点として活用していただきたいですね。
中下 子供が意味や価値をつくりだしているかどうかは、その子の作品をつくりだす活動の過程をしっかり見ておかないと見えてこないでしょうね。

