地域の河川と関連付けて河川防災教育に繋げる 〜4年「雨水の行方と地面の様子」【理科の壺】

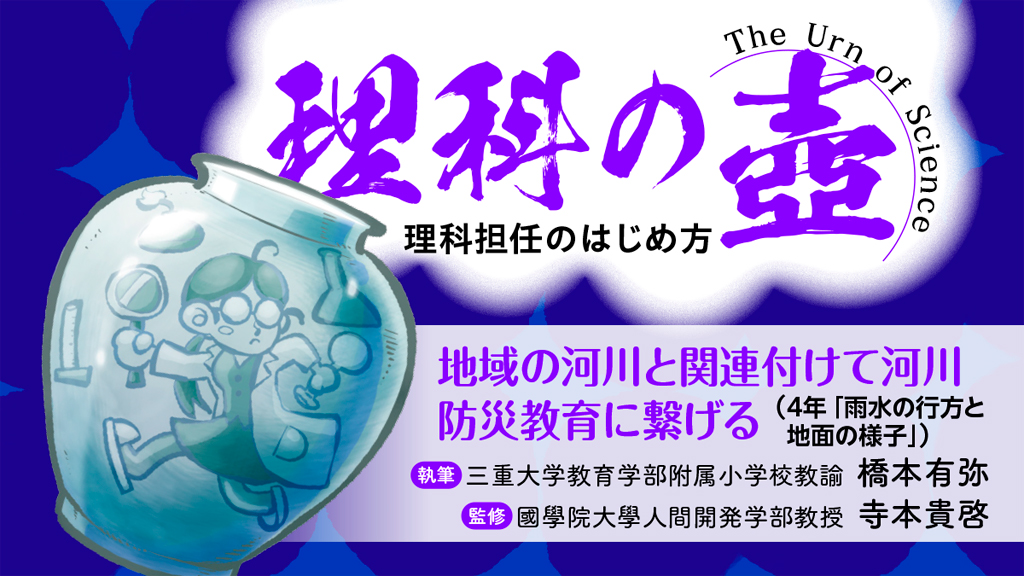
理科の授業でフィールドワークをすることはありますか? 運動場に出て確認することはあっても、学校外に出て調べに行くというのは、保護者への連絡や安全面の配慮、地域教材を使う教材の意味など、少しハードルがあります。今回は地元の河川防災教育に繋げるために、フィールドワークを取り入れる工夫についてです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/三重大学教育学部附属小学校教諭・橋本有弥
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.4年理科「雨水の行方と地面の様子」の目標
4年生の理科で学習する「雨水の行方と地面の様子」の単元では、子どもに「水は、高い場所から低い場所へと流れて集まること」「水のしみ込み方は、土の粒の大きさによって違いがあること」についての理解を図るとともに、日常生活との関連として、雨水の流れ方やしみ込み方が排水の仕組みに生かされていることや、雨水が川へと流れ込むことに触れ、自然災害との関連を通して「流域概念」を形成することが目標とされています。
近年、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化から、集水域から氾濫域にわたる流域に関わる関係者が協働して水害対策を行う考え方である流域治水が推進されている状況を考えると、本単元の学習を通して子どもが流域概念を形成することは非常に重要であると言えます。
2.流域概念形成と教科横断的な学習の必要性
流域治水を学ぶ子どもたちが、日本のどこかで毎年のように発生している水害やその対策について興味をもつのは自然なことだと言えます。また、自分たちの生活している地域の水害による被害や対策はどうなっているのかを学ぶことで、より自分事として学習に取り組むことができるようになります。そのためには、子どもの身近な地域を流れる河川を題材にし、「雨水の行方と地面の様子」の知識だけでなく、自分たちの住む地域の水害の現状や歴史、水防災対策、流域に住む人々の生活や思い、経済生活や文化などについて、社会見学やフィールドワーク、調べ学習などを通して、多面的・多角的に思考・判断する学習機会を設けることが必要です。4年生の社会科では、「自然災害を防ぐ人々の工夫」についての学習も行うため、社会科や総合的な学習の時間とも連携させた「河川防災教育」として、教科横断的な学習を展開するのが良いでしょう。
教科横断的な学習というと難しく感じるかもしれません。そこで、4 年理科「雨水の行方と地面の様子」の学習を展開する中で、子どもたちが自然と「雨水が川へと流れ込むこと」に気付き、河川防災教育へと繋がっていくような単元デザインについて紹介します。

