小2特別活動「思い出集会をしよう」指導アイデア

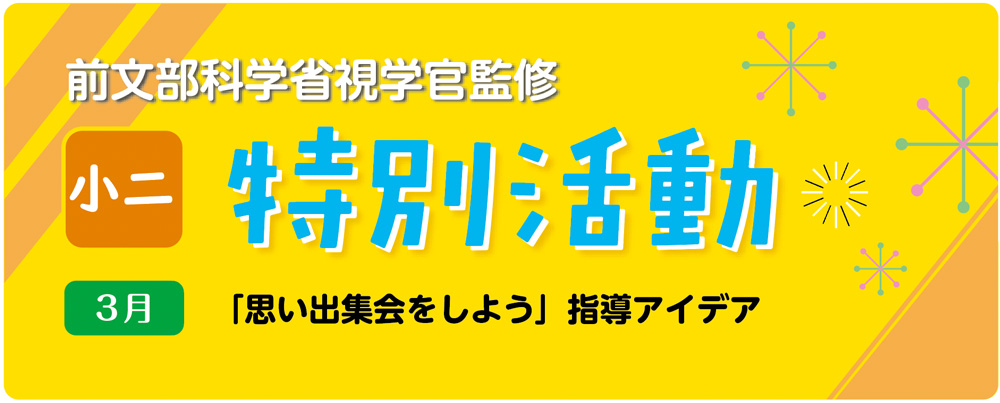
前文部科学省視学官監修による、小2特別活動の指導アイデアです。3月は、学級活動(1)「思い出集会をしよう」を紹介します。
この1年間、子供たちは様々な議題や題材で学級活動に取り組んできました。話し合って分かり合うことの難しさやすばらしさ、自分たちで決めたことを分担、協力して取り組む大切さ、活動を終えた後の満足感や自己有用感など、たくさんのことを体験を通して学ぶことができました。1年間の最後になる3月の学級会は、「思い出集会をしよう」を議題とし、2年1組の学級生活をよりよい締めくくりで終えることができるように話し合ったり実践したりしていきます。
2年1組の学級生活を振り返ったり、自他の成長や変容を振り返ったりすることができるような活動を取り入れることで、「みんなで遊んで楽しかった」にとどまらない、年度末の集会活動になるよう、子供たちと事前にイメージの共有を図っておきます。
執筆/埼玉県公立小学校校長・野村佐智夫
監修/帝京大学教育学部教授(前文部科学省視学官)・安部恭子
埼玉県公立小学校校長・野村佐智夫
目次
年間執筆計画
04月 学級活動(1) どうぞよろしくの会をしよう
05月 学級活動(2)ア 身の回りの整理整頓
06月 学級活動(1) クラスの歌をつくろう
07月 学級活動(1) 1学期がんばったね会をしよう
09月 学級活動(1) 係をきめよう
10月 学級活動(3)ウ いろいろな本を発見! 楽しい読書
11月 学級活動(1) クラスの記録大会をしよう
12月 学級活動(2)ウ 病気の予防
01月 学級活動(1) クラスのカルタを作ろう
02月 学級活動(3)ア もうすぐ3年生
03月 学級活動(1) 思い出集会をしよう
本実践までの本学級の状況
子供たちは4月から学級会の経験を積み重ねてきたので、「学級会で話し合う楽しさやよさ」「自分たちで話し合って決めたことを実践する楽しさやよさ」がよく分かるようになってきました。進行を担当する司会グループも、これまでの学級会で友達の様子を見たり、フロアからサポートする経験を生かしたりして、見通しをもって役割に臨むことができるようになってきました。そうはいっても、2年生になって初めて司会グループの役割を担当する子供たちなので、これまで同様、子供たちだけでできそうなところは見守り、心配な様子があるときは子供たち一人一人の状況に合わせた指導と支援を行う、「教師も一緒に」のスタンスで進めていきます。
また、思い出を振り返ると言っても、子供たちの中には、「どんなことがあったかな?」とすぐに思い返すことができないということも考えられます。そこで、4月からの学校行事や学級での取組について簡単に振り返ることができるように、写真などの資料を用意します。そうすることで、この議題が一人一人にとって自分事となり、話合い活動にも実践活動にも意欲とアイデアをもって臨むことができるようになります。

