<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #13 徳島県石井町立石井小学校5年3組③<前編>

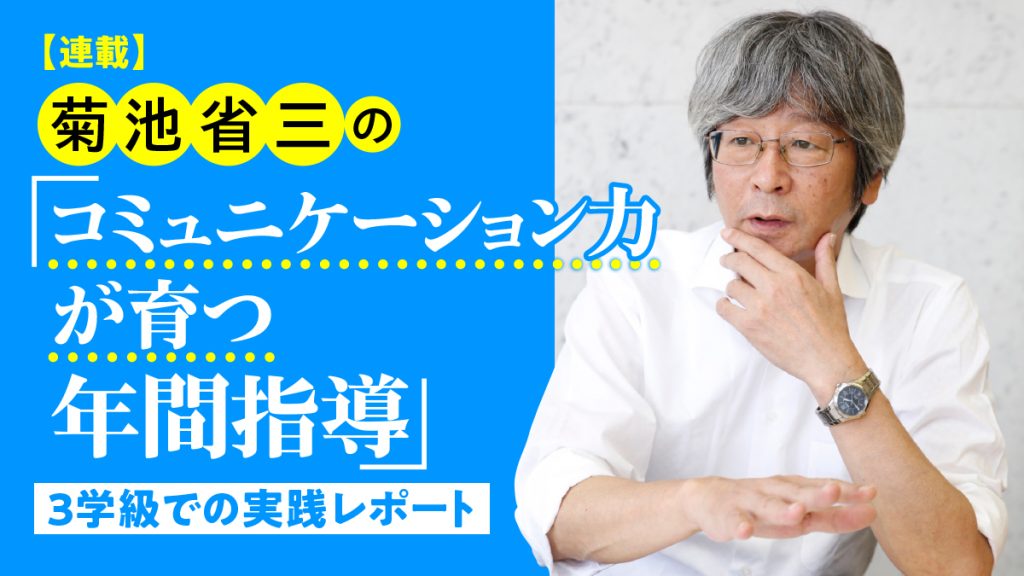
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載。今回からは、徳島の堀井学級(5年生)における、11月下旬の授業レポートです。菊池先生と堀井先生による、2時間続きの「熟議」の合同授業です。

目次
担任・堀井悠平先生より、学級の現状報告
二学期も半ばを過ぎると、子供たちはそれぞれの個性を発揮したり、学級での役割を自他ともに認め合ったりして、一人一人の居場所ができてきたように感じています。
今まで顔を覆っていたマスクを外し、学級活動にも授業にも積極的に取り組むようになった子、これまで無反応で発言しなかったけれど、最近では深い質問をし、ワードセンスを発揮しながら自分の意見を発表するようになった子、率先してクラスをリードする子――日を追うごとに、それぞれに役割が生まれ、それを学級全体で受け入れる空気ができています。
9月に初めて取り組んだ熟議では、「日本一の話し合いにするにはどうすればよいか」というテーマ設定が難しかったためか、議題設定の過程が教師主導になり、子供たちの意欲を高め切れなかったことが大きな反省点として残りました。
熟議の最中も、おとなしい子の発言を受け入れずに強引に決めようとする子供たちや、話し合いの輪の中に入れずに、外から見ているだけになっている子がいて、話し合いそのものを見直すきっかけになりました。
1回目の熟議の後は、みんなで挙げた課題の解決に向け、具体的な活動を決めて取り組んできました。その中で、「一番難しいな」と感じるものについて話し合った結果、「相手のことを考えた対話」「相互理解を深めること」という意見にまとまり、それらを2回目の熟議の議題として挙げることとしました。
菊池先生と堀井先生の合同授業レポート
5年3組は、<日本一の話し合いにするにはどうすればよいか>の議題で、9月に熟議を行った。話し合いの結果、子供たちから次の4つの解決策が出された。
●自分の意見を発表する
●白熱するための全員参加
●相互理解を深める
●相手のことを考えた対話
子供たちは、最初の熟議が終わってから2か月、上記の解決策について取り組んできた。その結果、「自分の意見を発表する」「全員参加」はできるようになってきた。しかし、「相互理解」「相手のことを考えた対話」については、「難しい」という意見が出された。
どうすればもっと相手のことを理解できるか──。そこで、今回(11月)の熟議では、<自分や相手のことをもっと理解するためにはどうすればよいか>について、解決に向けたアイデアを出し合うことにした。
熟議のグランドルールは、次の3つ。
①発言を「いいね」で受け入れよう
②発言に発言をつなごう
③みんなが参加者になろう
「みんなで解決に向けたアイデアを出していきましょう」
と係の子が説明すると、みんなが大きな拍手を送った。
![]()
熟議に取り組む教室もありますが、「1回熟議をやっておしまい」ということが多いのではないでしょうか。前の授業で行った熟議を踏まえて、解決策を実行するうちに、新たな課題が生まれてくる。それらを解決するために何をするかを新たな議題として挙げて、再び熟議を行う。これが本当の熟議です。
5年3組のように、議題について考え続け、熟議を続けていくことは、とても重要です。
堀井先生が「自分や相手の何を理解するのか、理解したいのか、近くの人と話し合いましょう」と声をかけ、話し合いの後、数人が発表した。
●感情
●長所と短所
●個性
「では、相手をお互いに知るために、日々どんな活動をしているか言える人?」
と堀井先生が尋ねると、子供たちは次々に意見を出した。
●授業中や休み時間の交流
●質問タイム
●ほめ言葉のシャワー
●係活動
子供たちの意見を黒板に書きながら、堀井先生が、
「日々やっているから、みんなは相互理解ができているのかな、と思っていました。例えば、自学ノートに、一人一人の良さを書いてくれる人がいました。学級全体のいいところを紹介してくれる人もいました。それなのに、なぜ難しいのか、相互理解が深まっていないのかを、今日の熟議では話し合っていきたいと思います」
と説明すると、子供たちは真剣な表情でうなずいた。

