今までの実験を想起し、実験器具を実際に触りながら、解決の方法を発想する力を伸ばす理科学習【理科の壺】

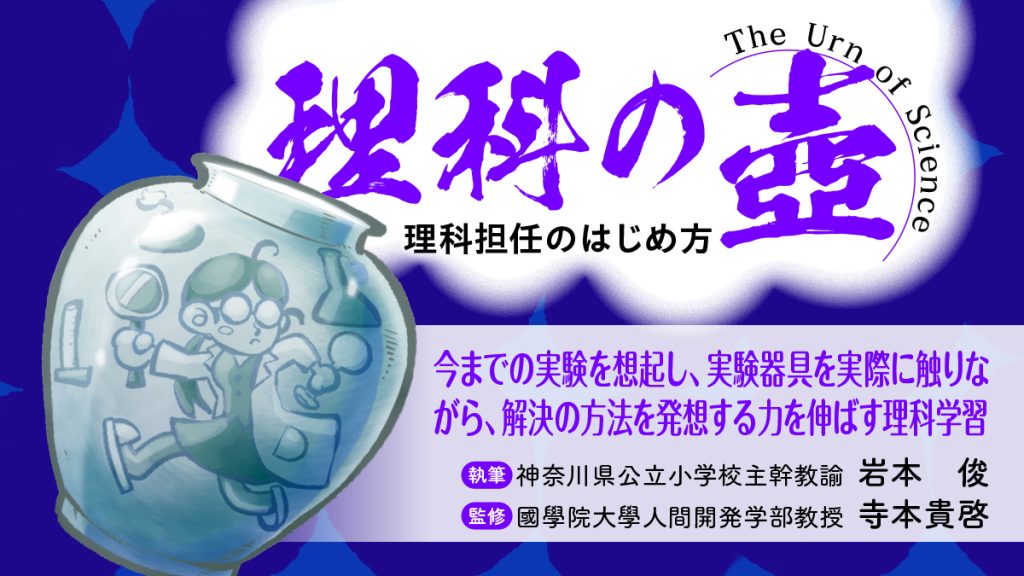
問題解決の過程の中でも、「解決の方法を発想する力の育成」は「難しい!」という声をよく耳にします。今回は、6年の「植物のからだのつくり」を例にして、子どもたちに、予想を確かめるために解決の方法を発想する力に焦点を当てて紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・岩本 俊
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.5年生までの学習で知っている植物のことと、前単元の「動物のからだとしくみ」で学んだことと比べて問題を見いだし、学習計画をたてる
まずは、子どもたちの学習してきたことを整理します。
5年生の「植物の発芽と成長」の単元で学んだことは、
植物の成長に必要(関係している):空気・水・肥料・日光・適した温度
の5つの条件があるということです。
さらに、6年生の前単元「人のからだのしくみ」で学んだことは、
人が生きていくために必要:空気・水・栄養・(日光)・適した温度
です。呼吸した空気から肺で酸素を取り入れ、血液を通して全身に行きわたることや、食べたものがどこで消化され、どのように吸収されるかといったことなど、「どうして空気・水・栄養が必要なのか」を詳しく知ることになります。主にその2つの学習経験から問題を見いだしていきます。
4年生の学習で植物は、気温が上がると成長し、下がると植物は成長しにくかったり、枯れてしまったりすることを知っています。6年生では、5年生で学んだ必要(関係している)な条件について、空気、水、肥料(栄養)、日光の4つが植物の成長に「どうして」必要なのかその理由を詳しく調べていくという学習計画を立てることが出来ます。子どもたちは、成長に必要(関係している)な条件として知っていますが、「どうして必要なのか、どうやって取り入れているのか」等詳しくはわかっていません。そこで、前単元である「動物のからだとしくみ」の学習と比べて整理していきます。
「空気がいるってことは、どこかから取り入れているよね。口や気管、肺みたいなものがあるのかな」「どこから取り入れているの?口があるのかな。根は土の中だから、葉か、茎だと思う」
「二酸化炭素を吸って、酸素を出していると聞いたことがある」
「森は空気がおいしいから、酸素が多いんじゃないかな」
など、知っていることと知らないこと(詳しく知りたいこと)を整理していきます。
子どもは、すでに、知っていることや経験から予想をしながら問題を見出しています。例えば、『水はどこから吸収しているのだろうか』については、経験から「根から吸っているだろう」という予想をもちながら、学習問題を整理していきます。

