問題解決の力を育成するための「事象提示の工夫」と「根拠のある予想の書き方」~4年「ものの温まり方」~ 【理科の壺】

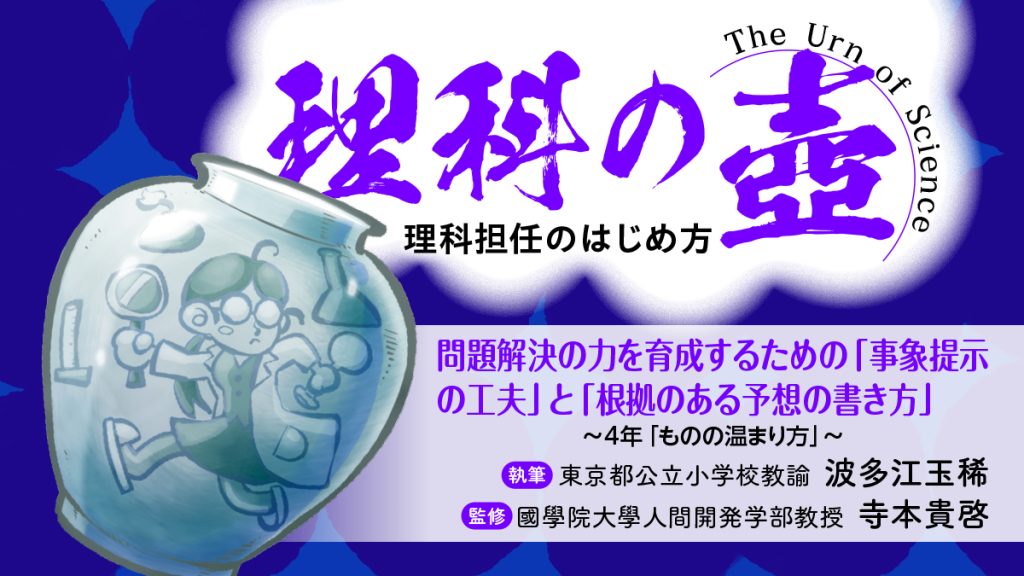
もののあたたまり方の授業では、「見えない温度をどのように見える化するか」が重要になります。子どもたちは、日常で見えないものはあまり気にしていません。この単元では、見えない「温度」、「あたたまり方」に着目していきます。導入場面では、最初から温度計を出して…というわけにはいきません。何かしら日常生活で馴染みのある物を使ったり、状況を設定したりして事象提示を行うことが多いです。今回は、「ものの温まり方」の授業導入をする際のアイデアとして、チョコレートを使った実践の紹介です。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/東京都公立小学校教諭・波多江玉稀
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.はじめに
みなさんは授業を行う際、どんなことに気をつけて教材研究をしていますか?
教材研究をするときには、
目的「何のために教えるのか?」と
内容「そのために何を教えなければならないか?」
に視点を当てて考えるとやりやすいです。
なぜなら、教師がねらいを明確にしていないと、学習のねらいが広がってしまい、子どもたちは何を学んでいるのか、分からなくなってしまうからです。
4年生では、問題解決の力を育成するために、学習の過程において、自然の事象・現象から見出した問題について、既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想することを教えることが大切です。
まずは、理科の目的と育成したい内容(思考力)を確認してみましょう。
【理科の目的と育成したい内容(思考力)】
目的
「問題解決の力を育成する」
内容
①差異点や共通点を基に、問題を見いだす力(第3学年)
②既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力(第4学年)
③予想や仮説を基に、解決する方法を発想する力(第5学年)
④より妥当な考えをつくりだす力(第6学年)
このように見てみると、①と②はつながっているものなので、4年生の「根拠のある予想や仮説を発想すること」を大切にしたくても、その前に①の「差異点や共通点を基に、問題を見いだす力」がとても大切ということがわかります。今回は、4年「ものの温まり方」の事例を元に、問題解決の力の育成するための「自然の事象・現象の提示(事象提示)の仕方」と「根拠のある予想や仮説の発想」について考えていきます。
2.どのようなものを事象提示にすればいい?
個人で予想や仮説を発想するためには、事象提示の際に働かせる見方・考え方が大切です。そのためにも、事象との出会いの場面において、児童一人一人が問題意識をもって問題を設定しているのか、どのような見方・考え方を働かせているのかを教師がしっかりと見取っていく必要があります。
事象提示の3つの工夫
問題解決の力を育成するためには、
①自然の事物・現象から問題を見出す
②既習の内容や生活経験を基に、予想や仮説を発想する
③予想や仮説を基に、観察・実験などを行い、結果を整理する
④その結果を基に、考察・結論を導き出す
という流れで行います。
事象提示の工夫は、そのうちの「①の問題を見いだす場面」がメインになります。
ここでは、身の回りで起きている自然の事物・現象の提示(事象提示)を工夫することで、意図的に自然の事物・現象に目を向けさせることができます。工夫のポイントは次の3つです。
Ⅰ:見方・考え方として「質的・実体的」にとらえられるようにすること
Ⅱ:教えたい学習問題にたどり着くまでの子どもの発言(思考)を書き出して考えること
Ⅲ:子どもたちがすでに学んでいること(既習事項)とのずれが生じる内容の教材を提示すること (単元の二次・三次など)
ここでは、金属・水・空気のそれぞれの事象提示について、ポイントをふまえて見ていきましょう。
Ⅰ:見方・考え方として「質的・実体的」にとらえられるようにすること
今回の授業の「もののあたたまり方」は、金属、水、空気と異なったものを扱います。「もののあたたまり方」で金属、水及び空気を「質的に捉える」とは、金属、水及び空気など「物ごと」、「材質によって」熱の伝わり方が違うと捉えることになります。また、ここでは「実体的」にも捉えることができるのですが、「もののあたたまり方」で金属、水、及び空気を「実体的に捉える」とは、熱は目に見えないけれど、温度が伝わったり変化したりしていると捉えることになります。
この単元では、「熱」という目には見えないエネルギーを扱います。この見えない「熱」を実体的に捉えるためには、「示温ペースト(インク)」「低温で溶けやすい物」「線香のけむり」といった、熱の様子を可視化するための教材を用いて実験を行い、金属、水及び空気の熱の伝わり方を調べます。
つまり、熱の伝わりによる温度変化を見えるようにすることが大切です。
Ⅱ:教えたい学習問題にたどり着くまでの子どもの発言(思考)を書き出して考えること
子どもの疑問から、どのような現象が起きればこの問題にたどり着くのか、という過程を、逆算して想定してみましょう。ノートなどに書き出しておくといいですね。
●金属とはちがう?
●温まり方が違うのかな。
●どんな風に伝わるんだろう。
●温度は目に見えないね。
●水は蒸発するから上にいくのかな。
●水はどうやってあたたまるんだろう。
このような言葉が児童から出ると、「水の温まり方」の学習問題を立てることができます。
Ⅲ:子どもたちがすでに学んでいること(既習事項)とこれから学ぶことで違いが生じる事象提示をすること(単元の二次・三次など)
一次:金属では「熱せられた部分から順に熱が広がって温まる」。
二次:水では「熱せられた水が水槽の中を移動して全体が温まる」を子どもたちは学びます。
つまり、教師は金属と水の結論でしっかり違いを見出だせるような事象提示を行う必要があります。
今回は、根拠のある予想を書きやすいように、子どもたちが経験上、温まると溶けることを知っている「チョコレート」を使ってやっていきます。
金属では、金属板の上側と下側にチョコを設置し、チョコに直接炎が当たらないようにしながら下側から熱して、どちらから溶けるかを子どもたちに聞きます。(30秒ほどで溶けます。)
金属は、熱したところから温まるので、下のチョコから溶けます。
次に、水についても事象提示をしていきます。
水の入ったビーカーの底の部分と上の部分にチョコを設置します。
金属と同じように、直接チョコに炎が当たらないようにしながら温め、どちらから溶けるか子どもたちに聞きます。
子どもたちから意見が出ますが、ほとんどの児童は下と回答するでしょう。
ですが、実際に温めていくと、上のチョコが溶け始めます。
子どもたちは、金属と水の温まり方に違いがあることに気付き、疑問が生まれます。そこから問題を見出すことができます。
このように、一次・二次の内容を同じ素材、同じ状況などで事象提示をすると、イメージしたり疑問が生まれたりして問題を見出しやすくなります。

