<新連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #1 徳島県石井町立石井小学校5年3組①<前編>

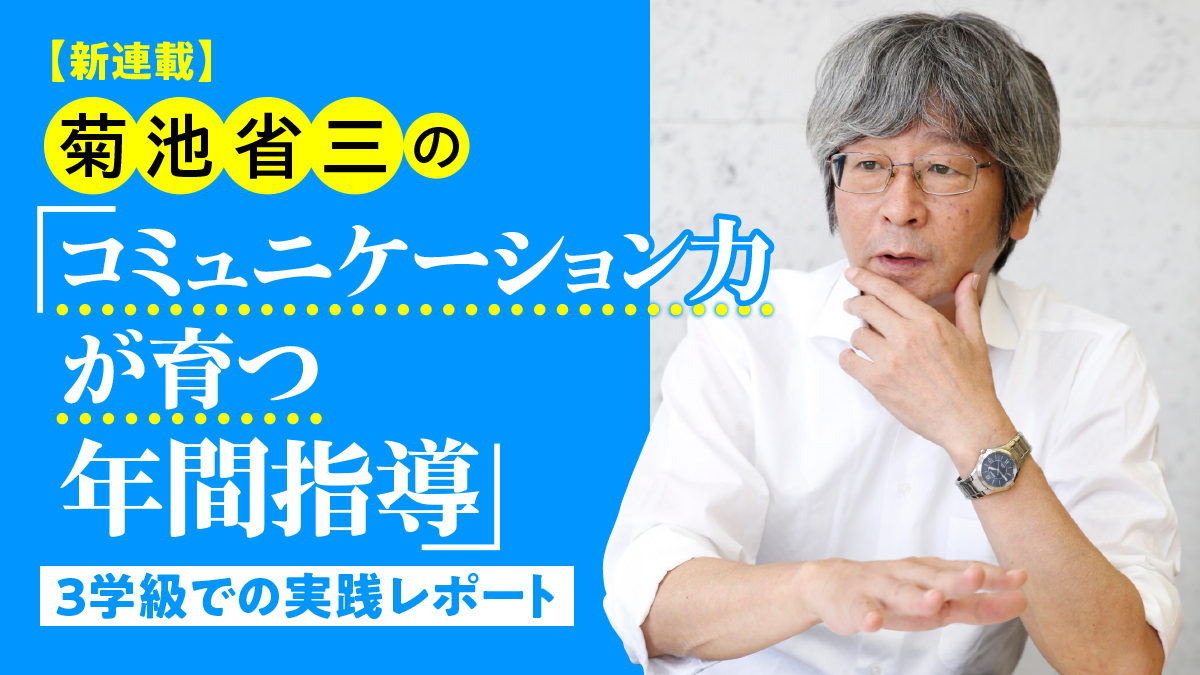
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする新連載のスタートです。3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、高知の小笠原由衣先生、千葉の植本京介先生。それぞれの学級をローテーションでレポートします。原則的に、菊池先生の授業記録+担任のコメントという構成でお届けします。第1回は堀井学級における、学級開き後わずか2週間の時点での授業レポートです。

目次
担任・堀井悠平先生より
昨年度、生徒指導主任として、何度か4年生のクラスにサポートに入ることがありました。その際、子供たちが秩序なく好き勝手に振る舞っている印象を受けました。
その後子供たちは、お互いにうまく関係性を築けないまま、5年生に進級してきました。おとなしい子が多く、また心理的な安全性がないために、簡単なことにも挑戦しようとしない、よさを共有しようとしてもなかなか広がっていかない、と感じています。どんな動きをする際にも、ワンテンポ遅れがちです。周りの動きやその空気を感じて動いているからなのでしょう。
子供たち一人ひとりには子供らしさが見られるものの、おたがいに牽制し合い、集団としてのつながりは希薄です。特に女子はSNS上でのトラブルなど、友達関係に問題を抱えており、教室がみんなの安心できる場所になっていないため、重い空気を感じました。
このような様子から、次の3つを1年後のゴールイメージとして考えました。
①他者理解と自己理解が進み、深まっている教室
②成長し合おうとする空気が漂っている教室
③聞き合い、考え合うことで新しいものを生み出そうとする教室
子供たちの実際の行為や言葉を踏まえ、ゴールイメージに向けて取り組んでいきたいと考えています。
菊池先生による飛び込み授業
「こんにちは!」
菊池先生がみんなに挨拶しながら、
「指の骨が折れるぐらい拍手をしたら、絶対に笑顔になれるんです。じゃあ、行くぞ!」
と声をかけると、子供たちが大きな拍手で菊池先生を迎えた。
「さっき3時間目の授業を見せてもらいました。話し合いのとき、みんな理由をセットにして交流していたから、どのペアも交流の時間が長い。4月でこのレベルのクラスはなかなかありません。今日は楽しくやりたいね。隣の人と『楽しもうな』と言い合いましょう」
ニコニコしながら、子供たちが「楽しもうな」と声をかけ合った。
<ワードセンス>
菊池先生が黒板に一言書くと、子供たちは「何だろう?」という表情になった。
「齋藤孝先生が考えた言葉だそうです。<ワードセンス>ってどんなことだろう? センスは、よく『センスがいいなあ』なんて言いますね。じゃあ、<ワードセンス>はどんな意味だろうか、ひらがなと漢字で表しましょう。一人ひとり違っていいんだね。先生は全部が正解だと思います」
子供たちは成長ノートを開いたものの、難しい問いに鉛筆が止まっている子も多い。
![]()
「夢」を、夢という言葉を使わずに説明しよう、「コミュニケーション」をひらがなと漢字で表そう。
私は子供たちによくこのような問いかけをします。
自分で考える問いには、正解はありません。自己開示できる安心感がある、正解がないから楽しい、難しいけれど頑張ろうと考える。これらはすべて学級づくりの下地になります。だからこそ、年度初めから1年間かけて鍛えていきたいと考えています。
「ワードセンス」の問いは、子供たちにとって難易度が高かったと思います。自分で独自に答えを考える経験がないため、余計に戸惑ったのでしょう。
それでも、こういう授業を通して、”自分で考える時間” を自覚させたいのです。わからなくてもいいし、書けなくてもいい。でも考える。今は考えるときだから、一人で考える。わからなくても、あとで友達と交流する時間はあるから大丈夫。
このような経験を積み重ねないと、深く考えようとせず、「わからん」とすぐに匙を投げたり、流されるだけの子供たちになってしまいます。
2分後、1文字でも書いた6人が発表した。
●言葉
●言葉のセンス
●言葉の選び方
●言葉のセンス
●自分が考えた言葉
●言葉のセンス
一人ひとりの答えに菊池先生がうなずいた。

