子供のやる気を引き出すには?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #13

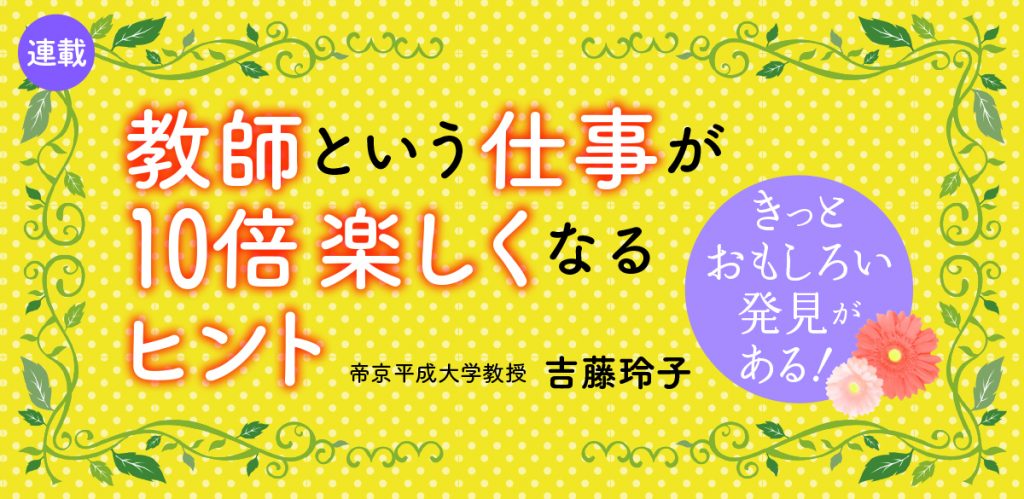
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの13回目のテーマは、「子供のやる気を引き出すには?」です。「主体的に子供が学ぶ」という授業が大切なことはよく分かります。しかし、どのようにすれば子供たちが主体的に学べるのでしょうか。子供たちが主体的に学ぶ、子供たちが意欲的になるような授業や活動の様々な方法を紹介します。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
子供たちから「もっとやりたい!」という言葉を引き出す
「主体的・対話的で深い学び」この言葉はいろいろなところで言われています。では、主体的に子供が学ぶというのはどういうことなのでしょうか。子供たちからの感想より先に教師のほうから「今日は楽しかったですね。またやりたいですね」「もっと続きがやりたいですか。来週もやりますよ」と言ってしまったことはありませんか? 大切なのは、教師より先にまず子供たちが「楽しかった!」「先生、もっと続きをやりたい!」って発言することなのです。そういう授業が組み立てられたら、子供たちが主体的に授業に取り組んだと言ってよいでしょう。そのような授業は、準備が大変かもしれませんが、子供たちからの前向きな発言によって、クラスの空気が変わってきます。子供たちが主体的に動き出すからです。
生活科の授業からのヒント
ここのところ、日本は四季が薄れてしまい、急に暑くなったり、寒くなったりという日々が繰り返されています。今年は、桜の花の開花もここ数年に比べ2週間ぐらい遅れました。やっと桜がきれいに咲いたと思ったら、強い雨や突風で散ってしまい、咲いていた時期が短く感じられました。それでも街の中が桜の花でピンク色になると「春が来たなぁ」と思います。
「ふゆをみつけよう」で子供が主体的になる授業
1月の終わりに「ふゆをみつけよう」という1年生の生活科の授業に講師で行くことがありました。思い出してください。今年の1月は暖冬でした。年末年始はとても暖かく、いつもであれば寒くて待っているのが辛い除夜の鐘も例年よりゆったりと待つことができました。元旦も暖かであった記憶があります。
そのような中、どのようにして「ふゆをみつけよう」の単元を組み立てたらよいのか、担任のY先生は悩んでいました。冬といったら皆さんは何を思い浮かべますか? 雪ですか? 氷の張った池ですか? カシャカシャと踏めば音のする霜柱ができた花壇ですか? 吐く息の白さですか? Y先生も子供たちといっしょに学校だけでなく地域を回り、いろいろと冬探しをしました。葉のついていない木々を見付けることはできましたが、観察用にバケツに水を張ってもなかなか氷ができない日々が続きました。
どうしようかと悩んだY先生は、冬の風に注目しました。冬ですから、当然、風は冷たいです。特に、強風になればヒューヒューと音が聞こえそうです。Y先生の学校は高層マンションに囲まれていたので、校庭は本当に北風が舞っているという感じでした。風を使った遊びを子供たちに考えさせ、工夫して遊ぶ授業を組み立てました。
ビニール袋の風船を飛ばす
Aグループでは、ごみ袋に使用している大きなビニール袋を活用して、大きな風船を作りました。45Lのごみ袋に空気をパンパンに入れて、しっかり口を結わいて、風船のようにして飛ばして遊びました。これが、ビュンビュン吹く北風にあおられて、すごく空高く上がるのです。やったことのない先生は、ぜひ試してみてください。もちろん、子供たちはみんな大喜びです。歌いながらポンポン、大きなビニール袋を飛ばしていました。
紙飛行機を飛ばす
Bグループは紙飛行機を作って飛ばしていました。自分たちで紙の種類を選び、折り方や大きさを工夫したり、飛行機の飛ばし方を工夫したりして試みていました。折り紙で飛行機を作った子供もいれば、厚紙で飛行機を作った子供もいました。いろいろなデザインの飛行機がありました。飛ばすときがまた楽しかったです。野球選手のようにポーズを取って紙飛行機を飛ばしている子供もいました。「エイッ!」と叫んで飛ばしている子供もいました。
凧を揚げる
Cグループは凧を作りました。凧といってもお正月に揚げるような大きな物ではなく、小さなビニールを工夫して割りばしに張った簡易なものでした。一生懸命走ってもなかなか揚がりません。その様子を見ていると、段々、「追い風に吹かれて走るとよい」「凧を揚げる高さなどを工夫していくとよい」などと話し合うようになっていく子供たちの姿を見ることができました。そして、長く凧が揚がったときは、大きな拍手をしていました。
風車を回す
Dグループは自分たちで作った風車を回して遊びました。風に当てて回してみたり、走ってみたり、振り回してみたり、いろいろしていました。そのときに1人の子供が「動いていないのに回るよ!」と叫んでいました。グループの皆が集まり、「風が動かしているんだよ!」と大喜びでした。
これだけ、たくさんの発見があった「ふゆをみつけよう」の授業。授業の最後にY先生が子供たちを校庭の真ん中に集めると、「先生、もっとやりたい!」「明日もやろうよ!」と先生が何も言わなくても子供たちから声が上がりました。このような子供たちの姿が「主体的に学ぶ」姿と言えるのではないでしょうか。冬の風は冷たいですが、このように楽しく遊ぶこともできます。冷たく、寒い冬の風から子供たちはいろいろなことを感じました。
この後、2月に東京にも雪が降りました。この授業に参加した子供たちは、Y先生が何も言わなくても長靴を履いて、雪遊びをする気満々で登校してきたそうです。そんな子供たちの姿を見たらワクワクしてきませんか?

