算数の文章題が苦手な低学年にするお話例【樋口万太郎先生の音声つき】#先生のための先生のお話

算数の計算は得意でも、文章題になると急に手を止めてしまう子どもたちには、どんな教え方が効果的でしょうか? この記事では、みんなの教育技術でもおなじみの樋口万太郎先生が、低学年を担任した時、算数の文章題を学習する際に必ずする指導法をご紹介します。ぜひここで学んで、子どもたちの苦手意識を克服できるように働きかけていきましょう!
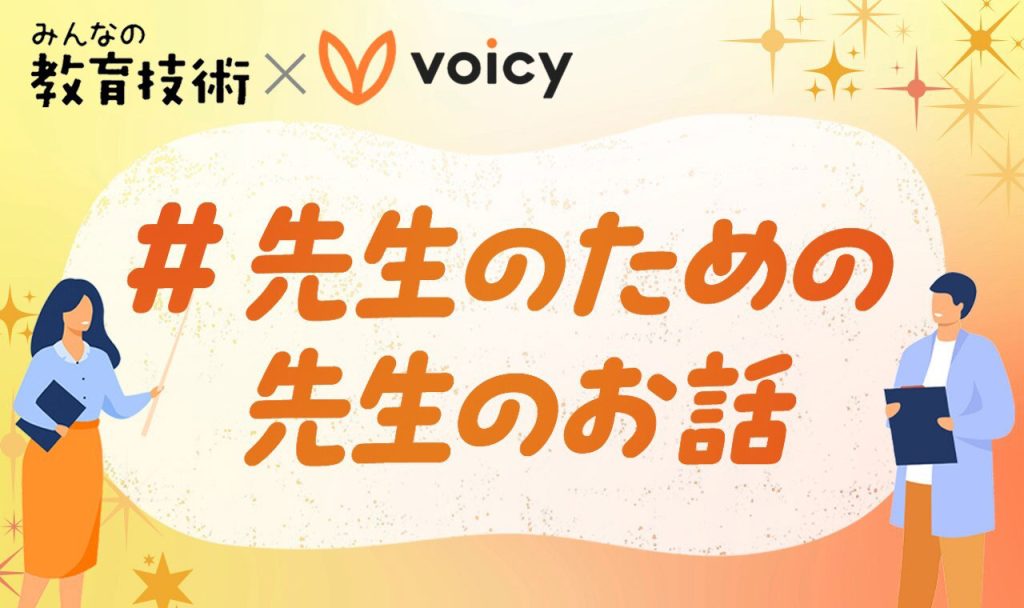
この記事は、音声プラットフォームVoicyとのコラボ企画「#先生のための先生のお話」の取組です。ここで紹介するお話は樋口万太郎先生のVoicyで聞くことができます。間の取り方や声色など、子どもたちの前で実際に話す時の様子がイメージしやすい音源になっているので、ぜひ参考にしてください。
低学年の算数文章題を指導する際の3つのSTEP
STEP1
今日、みんなと考える問題はこれです。じゃあ先生、読みますね。
マンタくんはリンゴを5個持っています。 3個リンゴをもらいました。全部で何個持っていますか。
という問題です。今すぐに「先生、式かけるよ。」って、言ってくれる子もいますね。もう答えも出せそうなの。すごいねみんな。じゃあさ、式と答えを書く前に、今日はね、この今先生が読んだ問題を絵に表してみましょう。絵ですよ。じゃあ、ノート開けてごらん。今からこのノートに問題の絵を描いていきます。では、用意スタート。
*3分から5分ぐらい時間を取ります。
はい、では皆さんこの問題の絵が描けたようですね。じゃあ前に出て黒板に書いてくれる人。はい、〇〇さん。
リンゴの絵を描いているね。みんな何個描くかわかる? そうか、みんな言ってくれるように5個描くかな。見てみよう。5個描いたね。お、またなんかリンゴ描き始めたよ。みんな、リンゴ、次何個描くと思う? そうか、3個描くかな。見てみよう。はい、描けました。皆さんこれでしっかりと絵を描けてますか?
「描けてます」ってみんな言ってくれてるね。じゃあ、この絵を見て式を書いてみましょう。どんな式になるかな。△△さん。
はい。5+3。みんなさ、この5+3の5ってどっから出てきたの?
そうだね。リンゴ5個持っていますって描いてるよね。イラストで言うとここだね。じゃあこの3は?
そうかそうか、もらったリンゴの数なんだね。絵で言うとここなんだね。じゃあ5+3、5と3を合わせると何個になりますか。はい、 そうですね。8個になります。
【POINT】問題文を絵で表す
・問題文を読んだ後、その内容を絵で描くように指導する
・絵を描くことで、問題文の内容を視覚的に理解することができる
STEP2
*STEP1を数回行った後の授業を想定しています。
では、今日の問題を今から言います。
マンタくんは オレンジを7個持っています。2個オレンジをもらいました。全部でマンタくんは何個持っていますか。
はい。それではいつものように絵を描いてください。ただし、いつもは結構長い時間絵を描いてもいいよって言ってたでしょ。今日はちょっと時間を区切ります。今日は10秒で描きます。
「えーっ」て声が聞こえますね。でも、ちょっと10秒でやってみましょう。では、いきます。よーい、スタート。1、2、3、 4、5、6、7、8、9、10。
はい、描けましたか。そうですね。皆さん描けてないよっていう子が多いと思います。じゃあ、ちょっと時間を延ばします。20秒で描いてみてください。じゃあ行くよ。続きじゃないよ。あ、また新しく描いてみてください。
じゃあ、いきます。よーい、スタート。1、2、3、 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20。
はい、どうですか。そうだよね。やっぱりこれまでね、1分以上、2分とか3分とか皆さん描いてきたけれども、急に20秒になると描けなくなるよね。
ということでですね、今日は、まず皆さんにこの問題の絵を、10秒とか20秒で必ず描けるという新しい技をみんなに教えます。それは何かと言えば、これからは絵ではなくてドット図で描いてみてください。
ドット図って何かと言えば、こういう丸です。丸。黒丸でもいいです。例えばですね、最初のリンゴ7個を白丸でこう描いたとして、次もらったリンゴを黒丸で描く。そんなふうに、今度は丸で描いてほしいんです。丸ならみんないけそうかな。
じゃあ皆さん、新しいノートのページを開けてください。今から10秒でいきましょう。皆さん、この問題をドットで表すことができるのかやってみます。ではいきます。よーい、スタート。1、2、3、 4、5、6、7、8、9、10。
さあ、どうですか。皆さん、描けましたか。お、描けてるって言ってる子いましたね。いいですね。お、早いですね。そうだよね。いつもこれまでは絵を描いてきたけれども、これからはこの問題をドット図で表してほしいなと思います。こういう丸ですね、丸とか黒丸とか、丸の中に文字を書いてもいいですね。
そうやってこの問題を図に表すっていったことをこれからしていきます。じゃあ、この問題の式はどうなるでしょうか。
【POINT】ドット図で問題を表現する
・絵を描くのが難しい場合や、時間がかかる場合は、ドット図(丸や点)で問題を表現する方法を教える
・ドット図を使うことで、素早く問題の構造を把握することができる
STEP3
*STEP2のドット図を使って問題を表すという活動を何度も行った後の授業です。先程までは1年生で取り組めることですが、今から行うテープ図は2年生で取り組むことです。
はい、では今日も問題を今から言います。いつものように問題をドット図で表してみましょう。では、今日はこんな問題です。
マンタくんは、リンゴを23個持っています。15個リンゴをもらいました。全部でマンタくんはリンゴを何個持っていますか。
じゃあ、いつものように20秒でいきます。よーい、スタート。1、2、3、 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、 16、17、18、19、20。
はい、どうですか。 描けてる子もいるね。でも、なんかしんどかったって言ってる子もたくさんいるよね。そうだよね。ちょっとこれまではドット図で頑張って描いてきたけれども、この数が大きくなると、ドットを描くのがしんどくなるよね。
頷いてる子もいるよね。ということで、新しい技を皆さんに教えます。今度はですね、ドット図ではなくて、テープ図で書いてみます。
【POINT】テープ図で問題を表現する
・数値が大きくなるとドット図では表現が難しくなるため、テープ図(長方形のブロック)を使って問題を表現する方法を教える
・テープ図を使うことで、数量の関係性をより明確に表現することができる

