インタビュー/柴田大翔さん|「教師は楽しい!」を発信し“ギガ先生”の輪を広げていきたい【注目の若手&中堅教師に聞く「わたしの教育ビジョン」Vol.03】
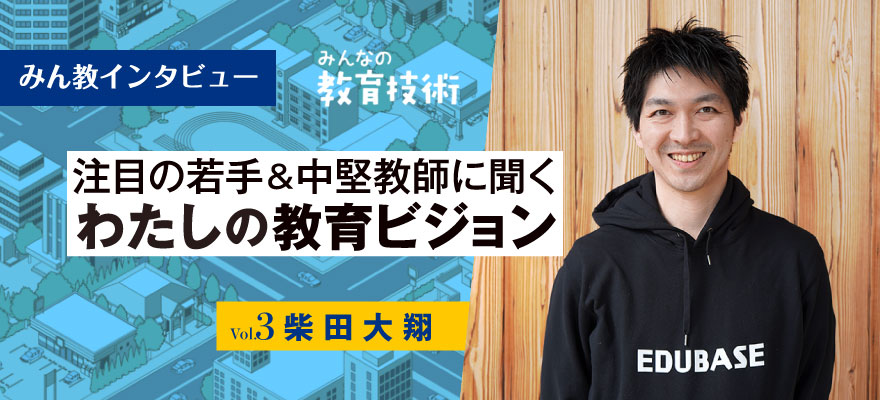
“ギガ先生”の愛称で知られ、ICTを使った授業づくりや学級経営、校務の時短術などをInstagramやVoicyといった各種SNSに発信している柴田大翔先生。日々発信することの意義や目的、これからのビジョンについて語っていただくとともに、明日からでも実践できる働き方のコツやICTを活用した教育実践についても教えていただきました。
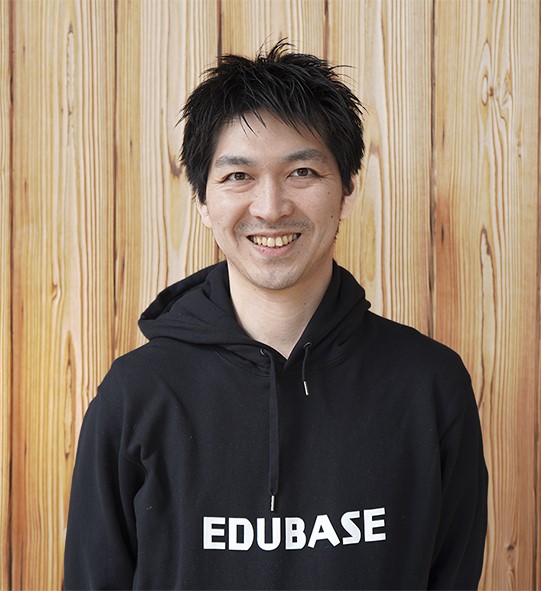
大阪府公立小学校教諭
柴田大翔(しばた・ひろと)
1990年大阪府生まれ。教師のワークライフバランスを意識した働き方やICT端末をフル活用した授業アイデア、学級づくりを研究。その内容を「ギガ先生」としてInstagramやVoicyといったSNSを中心に日々発信している。自身のSNSの総フォロワー数は2.2万人を突破(2024年4月現在)。著書に『今日から残業がなくなる!ギガ先生の定時で帰る50の方法』(学陽書房)、『小学校 新卒からの3年間を華麗に乗り切る仕事術』(明治図書)など。
目次
残業時間を90%以上も削減―自身で始めた働き方改革
「夜遅くに帰って寝るだけの生活を送っていました(笑)」――そう話すのは、大阪府の公立小学校で教鞭をとる柴田大翔先生。今でこそ、教師の働き方についての情報をSNSや著書で発信する柴田先生ですが、以前は、月の残業時間が120時間を超えるほど働き詰めの毎日で、円滑に仕事を回すことができていなかったと話します。
「早朝6時に出勤して夜中の10時ごろに帰宅なんてこともザラでした(笑)。そのころは若くて独身だったこともあり何とかなっていたんですが、そんな生活を重ねるうちにだんだんしんどくなって……。大きく変える契機になったのは、結婚して子どもが生まれたタイミングです」
自身の子育てをきっかけに、短時間で効率よく働く方法を模索するようになったという柴田先生。まず実践したことは「できることは、とにかく早く取りかかる」ということでした。
「それまでの自分自身の働き方を振り返ったとき、事務などのちょっとした仕事を後回しにしていたことに気づいたんです。例えばアンケートなどは手をつけたらすぐに終わるはずなのに、後回しにしてしまうからどんどん積もっていき、気付いたときには、自分のキャパでは処理できないほどに膨れ上がってしまう。ですので、ちょっとした事務作業などを早めに処理することから実践しました」
加えて、すべての業務を自分一人でやることを「あきらめた」ことも大きかったといいます。この「あきらめた」はポジティブな意味であり、「自分一人で抱えこむ必要はない」と吹っ切れたとのこと。そして、柴田先生はこれまで一人で行ってきた作業を一部、子どもたちに任せるようになりました。
「例えば、宿題の答え合わせなどです。子どもたちからすれば、先生がいなくても、自分たちでちゃんと行えるんですよ。それに、教師から離れたとき、子どもたちが自分自身で学び続けられる力をつけるには、子どもに委ねる場面をつくることも大切だと気づいたんです」
その結果、手が空き心に余裕ができたぶん、子どもたちのことをより見取れるようになると同時に、子どもたちが自発的に学べる環境も構築されていったといいます。さらに、そうした環境が安定的な学級経営につながり、子ども同士のトラブルによる放課後の対応なども大幅に削減されたとのこと。もちろん、子どもに任せていいこととそうでないものはあり、その切り分けも行いました。
子どもたちに任せてOKなこと/NGなこと
〇 OKなこと
宿題の答え合わせ/宿題のやり直し/配布物の返却/簡単な学級掲示物の作成/掲示物の貼り付け
教室の備品の整理整とん
× NGなこと
テストの丸付け/テストの返却/氏名印を押す書類作成/黒板の掃除
健康状態のチェック/食物アレルギーの子への配膳
(特に子どもの健康状態に関することは子どもに委ねないようにしましょう。)
ICT活用で授業アイデアを実現―Canvaを活用した教育活動の実践
なお、1年間の学級経営の明暗を左右するのは、新学期のスタートを上手くきれるかどうかだと柴田先生は語ります。
「新学期はまず、規律的な部分に重きを置きます。例えば、挨拶や返事をきちんと行うことだったり、丁寧な言葉づかいを心がけたり、靴をそろえたり……。そういった人としての基本的なことを徹底的に指導します。ここさえクリアすれば、その後、子どもたちは自分の力で進んでいけるようになります」
また、子どもたち同士の関係性や学級の雰囲気(カラー)の土台がつくられるのもこの時期とのこと。「ギガ先生」でもある柴田先生は、新学期はじめのオリエンテーションやレクリエーションにこそ、ICTの活用がもってこいだと語ります。
「おすすめは、自己紹介カードをCanvaで作ってみること。プレゼン用のテンプレートが数多くあるので、書くことや表現することが得意な子はいろんなトピックがそろっているものを使えばいいですし、苦手な子はトピックの少ないものを使えばいい。従来は教師が用意したプリントに子どもが書き込むのが主流だったと思うんですが、自由に選ばせてあげることで、一人一人の性格や個性に合った自己紹介カードをつくれますし、子どもたち同士でもお互いのことをよく知るきっかけになります」
ICT教育を実践する際は、基本的なメディアリテラシーなどを子どもたちに指導すると同時に、「まずは教師が楽しんでみることが大切」という柴田先生。例えば、Canvaを活用したクラスのロゴマークづくりは、子どもたちと一緒に作業することで、クラスの団結がより深まっただけでなく、探究学習にもつながる効果的な教育実践になったと楽しそうに話します。
「学級目標づくりはありますけど、ロゴマークづくりはあまり聞かない。「なら、つくっちゃおう!」って(笑)。しかも、クラスのロゴマークをデザインしたオリジナルトートバッグも製作して、今度の社会見学にみんなで持っていこうと話しています。Canvaを含め、ICTは使えば使うほど、今まで考えられなかったような教育活動が実現できます。まずは教師が、『ICTを使うと、こんなに楽しいことができるんだよ』と実践する姿を見せることで、子どもたちにも学習の楽しさが伝わっていくと思います」

ロゴマークをデザインしたオリジナルトートバッグ→

Canvaを活用した指導や授業に積極的に取り組んでいる柴田先生は、現在Canvaの認定教育アンバサダーである「Teacher Canvasador」への認定をめざし、日々Canvaを活用した教育技術の研究、発信に努めています。
「Canvaは、教育ツールとして無限の可能性をもっています。使い方次第で、頭の中にある様々な授業アイデアを形にすることができます。ICTを活用した授業づくりに熱心な先生はもちろん、『ICTを授業にどう活用したらいいかわからない』『あまり活用できていないな』と悩む先生にも、ぜひ一度ふれて、体験してみてほしいです」

