理科好きを育てるためのしかけの工夫 ~まずは自分からやってみよう!~ 【理科の壺】

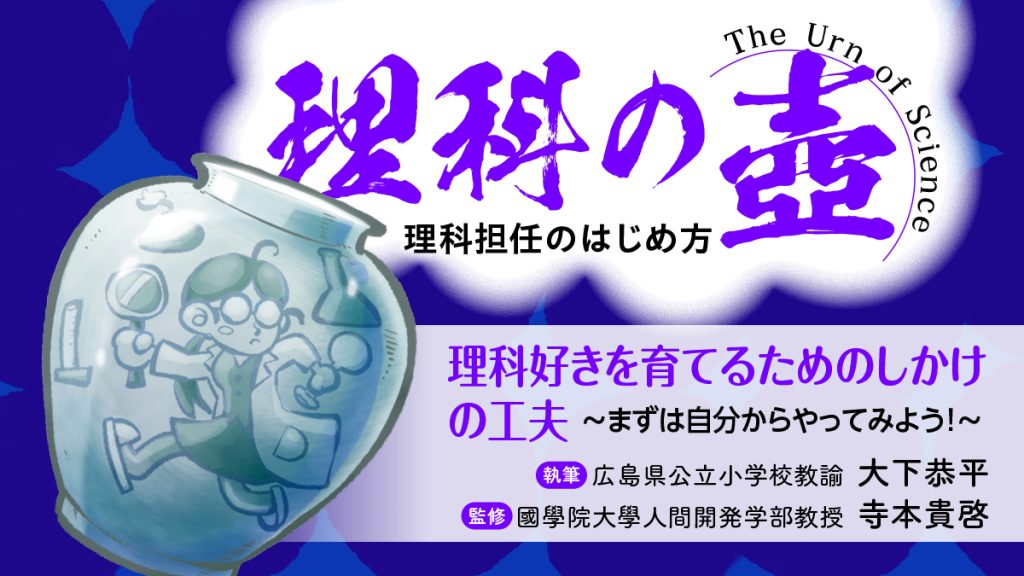
自然事象との出合わせ方は、先生によってカラーが出やすいところだと言えます。ぜひ、一歩立ち止まって考えてみてください。その導入は、子どもたちにとって「やる気」が出る方法でしょうか? 同じ問題を導くのでも、工夫次第で子どもたちの気持ちは大きく変わってきます。今回は、「理科好きを育てるためのしかけの工夫」です。特に自然事象との「出合わせ方のしかけ」についてです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/広島県公立小学校教諭・大下恭平
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
記憶に残る授業ってどんな授業??
小学生のときに、受けた理科の授業で、記憶に残っている授業ってどんなものがありますか?
ホウセンカやヒマワリの観察? メダカの飼育? 大地のつくり?
きっとここに挙げたものではなく、電気やじしゃくの実験や、空気でっぽうを使った実験、水溶液を蒸発させる実験などの「実験」ではないでしょうか。理科という教科の特徴が「理科=実験」となってしまうのは、いささか困りますが、「理科=好き」につなげるためにも、子どもたちの心に響く実験や内容を選んで一緒に考えたいものです。
出合いのしかけを!!
では、「理科=好き」にするためにどのような「しかけ」が必要なのでしょう。教科書を開いて、問題を確認し、教科書通りに実験を進める。これによって子どもたちは、必要な知識を身に付けることができるかもしれません。しかし、むしろこのことによって実験の楽しさばかりに意識が向かい「理科=実験」になっているのかもしれません。
私は常日頃から、子どもたちに「えっ!?」「なんで!?」「自分たちでもやってみたい!!」と思わせる「出合い」を経験させることが大切だと考えています。
ただ出合わせればよい、ということではありません。出合わせ方の工夫が必要になってくると思います。学習対象と出合う時に、「子どもの素朴概念とのずれ」を経験させることや、「知らなかった科学事象に目を向けさせる」という視点をもつことが大切だと思うのです。

