学びの共同体とは?21世紀型の対話的・探求的学びの実践【佐藤学先生インタビュー】
新学習指導要領が、これからの教育に求めている「主体的・対話的で深い学び」。それに先駆けこの20年来、「学びの共同体」の理論で目指すべき教育を追究し、各国の教育現場に広く指導してきた学習院大学特任教授・佐藤学先生。 新刊著書の『学びの共同体の挑戦 ─改革の現在─』(小学館) をもとに、「学びの共同体」の本質についてお話を伺いました。
佐藤学(さとう・まなぶ)さん
学習院大学 特任教授
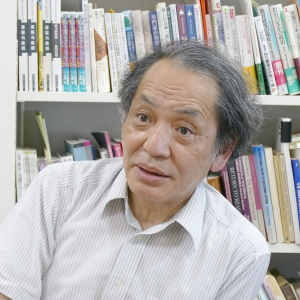
目次
特徴は、21世紀型の学びにふさわしい学校づくりにある
――佐藤先生は、学校が「学びの共同体」となるために、「聴き合う関係」「ジャンプの課題」「真正の学び」が必要と言われています。具体的にはどのような実践なのでしょうか?
佐藤 「学びの共同体」の改革は35年前に始めました。現在では全世界で17か国が挑戦しています。
学びの共同体の特徴は、21世紀型の対話的・探求的学びを初めから提示し、それにふさわしい学校づくりをしてきたことです。その中でもベースとなるのが「聴き合う関係」です。
学びは対話によって成立するもので、一人では学びは成立しません。聴き合う関係をつくり、対話的なコミュニティを大切にすることで、高いレベルの学びを実現することができます。結果として、低学力の子供がいる学校でも必ず成績が伸びるのです。
この「聴き合う関係」をつくるためには「場」と「環境」が必要です。
例えば、机の配置をみんなの顔が見えるコの字型にしたり、3、4人のグループの配置にしたりするなどして「聴き合う場」をつくります。
また、誰もが安心して聴き合う関係をつくるために最も重要な「静かな環境」をつくります。廊下まで先生の声が響いているような教室では「聴き合う関係」はつくれません。

