第59回 2023年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 内山智枝子さん(筑波大学附属駒場中・高等学校教諭)
科学的な探究活動における学習評価の検討
~「主体的に学習に取り組む態度」を育む3年間とその記録~
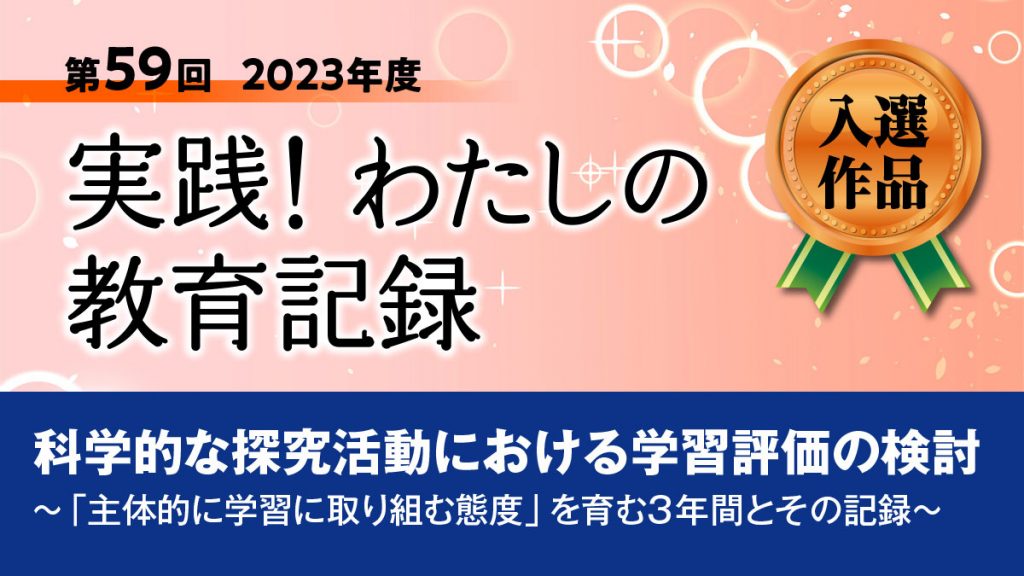
目次
はじめに
この記録は、2020年度に勤務校(筑波大学附属駒場中学校)に入学した中学生123名(3クラス)を対象に、2020年4月から2022年12月にかけて実施した理科(生物分野)の授業(1年次:週2時間、2年次:週1時間、3年次:週1時間を2学期まで)実践に基づいています。
科学的な探究活動の実践と、この活動で使用した「科学的な探究用振り返りシート」の作成および活用による影響の分析、このシートの蓄積によって得られた3年間の振り返りをまとめました。3年間の活用の結果、このツールが「主体的に学習に取り組む態度」の 側面とされる「粘り強い取組を行おうとする側面」や「自らの学習を調整しようとする側面」を表出するツールとなり得ることや、「失敗」に対する認識の変化を促すのではないかという手応えを得ることができました。
第一章 探究活動における学習評価にどう臨むか?
「生徒一人一人の学びを促し成長を見取るためにどんなアセスメントができるだろうか?」。3年前、中学1年生の理科を担当することがわかった時に、真っ先に考えたことだ。できれば、生徒自身が学びや成長を実感し共有できるものがいい。
授業そのものは、科学的な探究活動を中心に展開することを思い浮かべていたものの、今まで通りのアセスメントを含めた学習評価だけでは、不完全燃焼のまま終えて後悔するような気がする。しかも、次年度(2021年)からは、観点別学習評価の項目が変更される。
3観点のうち「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」に関しては、評価方法や実践について報告されている(1)が、「主体的に学習に取り組む態度」については、中学校理科での実践例の報告(2)は少数である上、これまでの観点「関心・意欲・態度」とは明確に区別することが求められている。もうこれは、既存のツールだけでは満足されることはないと思い、何か工夫を加えて新学期に臨むことにした。
(1) 中学校学習指導要領解説(2017)で示される「理科における資質・能力の例」や、長谷川ら(2013)が開発した「探究の技能」、中村(2020)がOECD のPISA2006 で示される「科学的能力」をベースにして設定した「科学探究能力」等を参考に基準を設定し、評価することが可能であると考える。
(2) 例えば、髙田(2021)や 山口(2022)のような報告がなされている。

