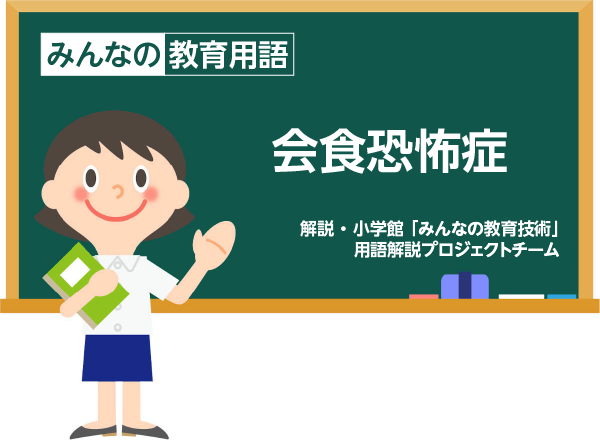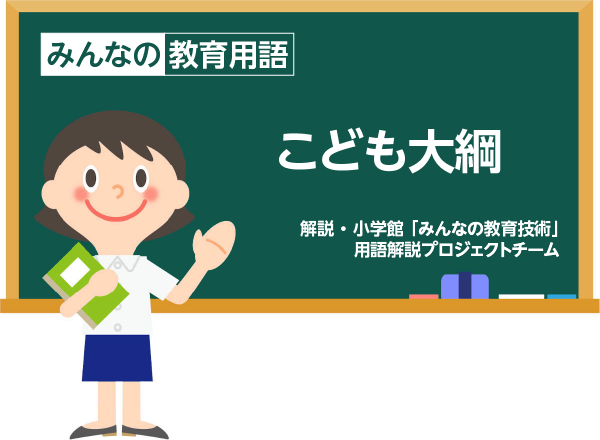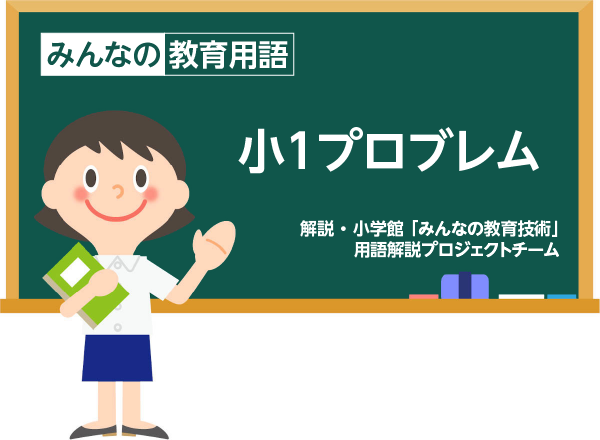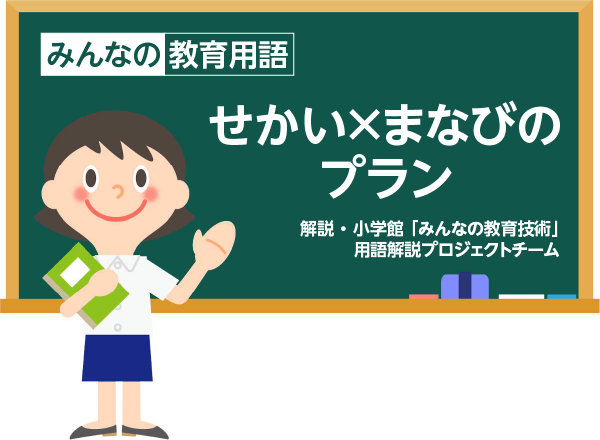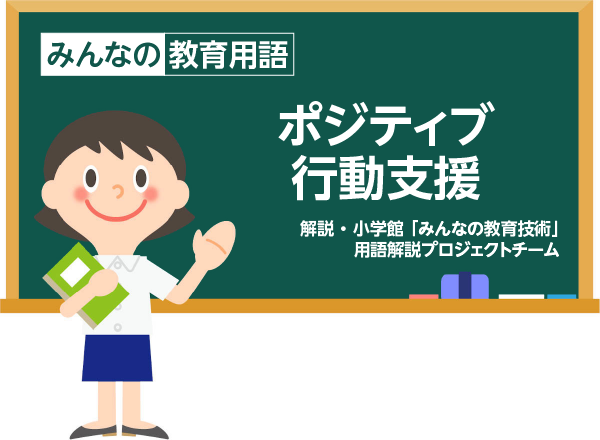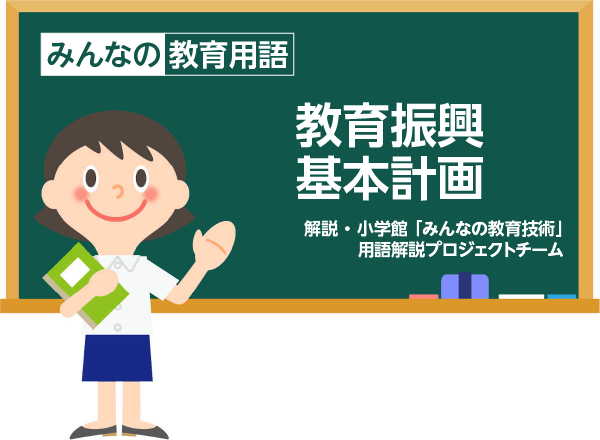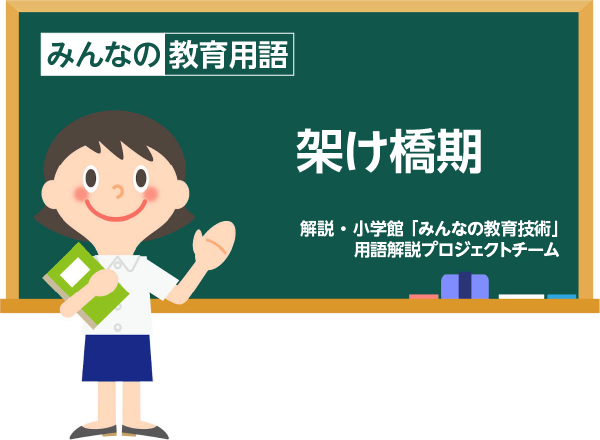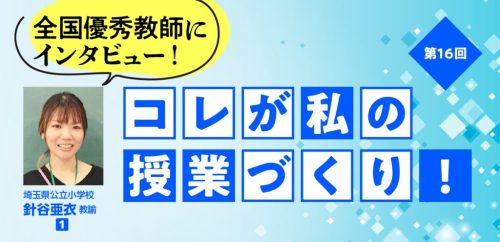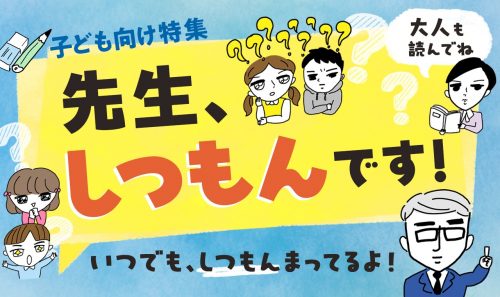「J-MIRAI」とは?【知っておきたい教育用語】
2023年、内閣官房に設置された教育政策に関する会議「教育未来創造会議」において、若者の留学や外国人留学生の受け入れを促進する提言「J-MIRAI」が取りまとめられました。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム

目次
J-MIRAIとは
2023年4月27日に開催された第6回教育未来創造会議において、「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」(第二次提言)、略称「J-MIRAI(ジェイ-ミライ)」が取りまとめられました。
このなかでは、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとする「新しい資本主義」を実現していくために、人への投資を進めることが特に重要だと指摘。これまでの国際社会や秩序を揺るがすような危機に世界が直面する中、日本が国際協調・連帯の強化を主導する役割を担い、国際社会の平和と安定の確保に貢献していく必要があるとしたうえで、このような将来の鍵を握るのは、若い人材であるとしています。
こうした考えのもと、政府として2033年までに、日本人学生の海外留学者数50万人、外国人留学生の受入数40万人の実現をめざすことなどが目標として掲げられています。2020年以降のコロナ禍により停滞していた国境を越える人の往来が回復に向かい、世界各国がグローバル人材の獲得を進めるなか、留学生の派遣や受け入れ、教育の国際化に焦点を当て、その在り方や具体的方策が示されました。
教育の国際化の現状
日本における生産年齢人口割合は、1990年代の約70%をピークに減少し、2050年代には約50%となる見込みです。また、人口も約1億人まで減少すると見られています。
経済面では、世界のGDPに占める日本の割合が1990年代の約10%から、2020年には約5%にまで縮小しています。また、一人当たりの労働生産性も先進7カ国(G7)の中で最下位となりました。こうした条件から算出される世界競争力についても、日本は1989年~1992年まで1位を維持していましたが、その後順位は年々下がり続け、2023年は35位となっています。
諸外国においては海外への留学を希望する者が5割を超えるのに対して、日本の若者は「海外留学をしたいと思わない」と答える者が5割を超えています。その理由としては経済的な問題や語学力不足などが挙げられますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、2018年度には約12万人だった留学生数が、2020年度には1,500人にまで激減しました。
また、外国人留学生の受け入れや定着の実態を見ると、在学者に占める留学生の割合は約6%にとどまっています。オーストラリアでは3割、イギリスでは2割にのぼることから、諸外国と比べても日本の留学生在籍割合はかなり低い状況にあることが分かります。日本での外国人留学生の受入数は年々増加しており、2019年には約31万人となりましたが、世界各国が留学生の獲得を競い合う中、日本においても留学生の受入数のさらなる改善が課題となっています。
今後の方向性
若者の海外留学への内向き志向が進んでいることや、経済的理由、語学力不足を理由に日本人の海外留学者数は伸び悩んでいます。このような状況を打開するために、「J-MIRAI(ジェイ-ミライ)」では、日本人学生の海外派遣について、今後の方向性を示しています。
具体的には、海外大学・大学院における日本人留学生の中長期留学者の数と割合の向上を図るとしています。この実現のために、高校から大学院までを通して短期・中期・長期留学までの学位取得につながる段階的な取組を促進。具体的な方策として、SNS等を活用した広報の強化や、協定派遣(授業料相互免除)増に向けた取組の推進、官民一体での経済的支援の充実などを掲げています。
なお、日本からの海外派遣において、育成したい人材像は以下のようにまとめられています。
【海外派遣を通じて育成したい人材の姿】
①育成したい能力・特性
●日本人としてのアイデンティティを持ちながら、異文化を理解して相手の立場を理解する共感力
●社会課題を自分事として捉える主体性・積極性
●国籍や専門性など異なる背景を持つ多様な人を巻き込む行動力
●豊かな語学力・表現力・想像力・ディベート力・コミュニケーション能力・コラボレーション力
●多様な人と協働しながら国際社会や地域社会の発展に資する新たな価値やルールを作ることのできる力
●変化を恐れず、柔軟に対応し、自ら生涯にわたって学び続けることができる力
②活躍する姿
●産業・科学・教育・スポーツ・文化芸術など様々な分野で、日本の成長をけん引し、イノベーションを創出する人材、世界に貢献する人材、地域の成長・発展を支える人材
●エネルギー・食料問題、安全保障など地球規模のものから我が国や地域が抱えるものまで様々な課題を発見し、解決する人材
●国際頭脳循環に参入し、各分野をリードする研究人材
また、外国人留学生の受入れ方策としては、日本への留学機会の創出、国内大学の教育研究環境の質及び魅力の向上などをめざしており、優秀な学生の早期からの獲得強化や、留学生の授業料設定柔軟化を図るとしています。留学生の卒業後の環境整備にも力を入れ、留学生に対する通年・秋季採用、インターンシップ等による様々な選考機会の提供を促していくとしています。
▼参考資料
文部科学省(PDF)「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」令和5年4月27 日
政府広報オンライン(ウェブサイト)「新しい資本主義の実現に向けて 」