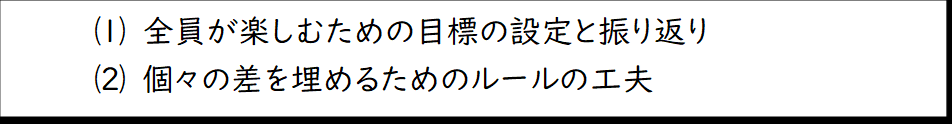第59回 2023年度 「実践! わたしの教育記録」新採・新人賞 中原修平さん(愛知県名古屋市立神の倉小学校教諭)
今日も明日も体育がいい!
~クリエイティブ型体育の授業を通して~
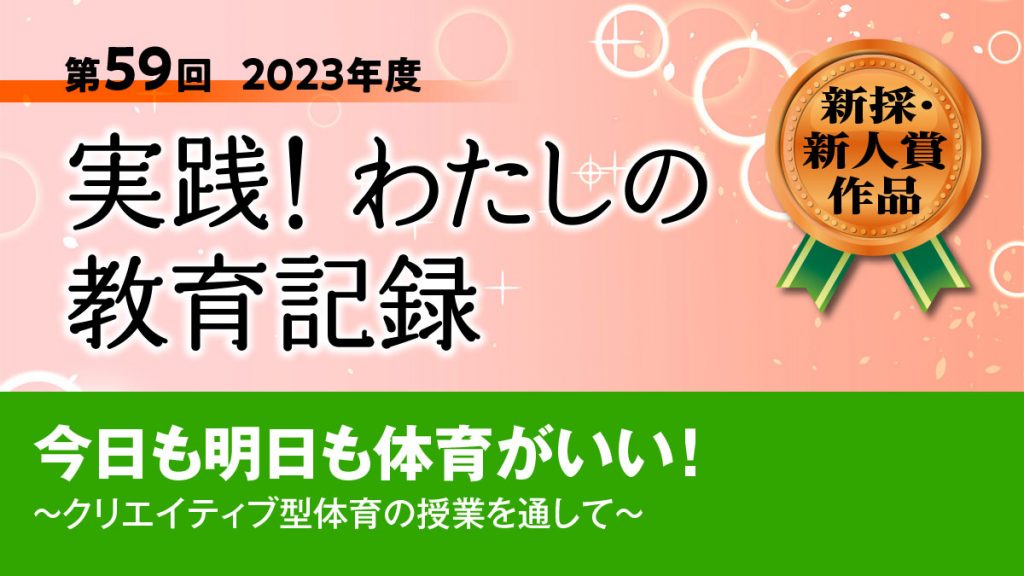
目次
Ⅰ 研究の意義
学習指導要領によると、体育科の目標は「豊かなスポーツライフの実現」である。私の考える豊かなスポーツライフとは「いつでも、どこでも、だれとでも」運動を親しむ姿だ。しかし、昨今の実態として「運動をする子供とそうでない子供の二極化傾向が見られる(*1)」とある。豊かなスポーツライフの実現を目指す上で、授業改善が求められている。
授業改善について考える中で、私がいつもたどり着く答えは、「みんなが体育授業を楽しめるようにしたい」であった。ここで言う「みんな」とは、子どもの体力や技能の程度及び、年齢や性別、障害の有無の全てを包み込んだ「みんな」である。子どもたちがこのような違いを意識しつつ、互いを認め合えるような授業ができれば、みんなが楽しめる体育に近付けるのではないだろうか、と考えるようになった。
以上のことから、私は、互いの差を認め合い、共に学ぶ授業を通して、「いつでも、どこでも、だれとでも」運動を豊かに実践する基盤を培いたいと考え、研究をスタートさせた。
Ⅱ 子どもの実態
本学級(1年2組)の子どもは、体育の時間を楽しみにしている。「ぼくはこんなこともできるよ!」と自信を見せる子どもも多い。一方で、「投げるのは苦手だからやりたくないな」「私は小さいから力がない」と、運動能力や体格に対する不安から、苦手意識をもつ子どももいる。4月に行った折り返し走やドッジボールでは、前者のような子どもが活躍し、後者のような子どもは、邪魔にならないように動いていた。このような子どもたちが、豊かなスポーツライフの実現に近付いているとは言い難い。
では、子どもたちが、運動に苦手意識をもってしまったのはなぜだろうか。私は、①「みんなで楽しもうという意識の低さ」②「必要とされる運動技能の高さによるつまずき」の二つが原因ではないかと考える。このことから、本実践では「意識」と「技能」の二つの面で指導を工夫していくとした。
豊かなスポーツライフの実現に、体格や運動の得手不得手が大きな要因となっていいはずがない。そこで、運動が得意な子も苦手な子も、大きな子も小さな子も、全てを包み込み体育を楽しめるようにするために、以下の2点に重点を置いて実践を進めていくことにした。