理科の学びを自分で評価し、自分に自信を持って「自立する学び」ができる子どもを育成しよう 【理科の壺】

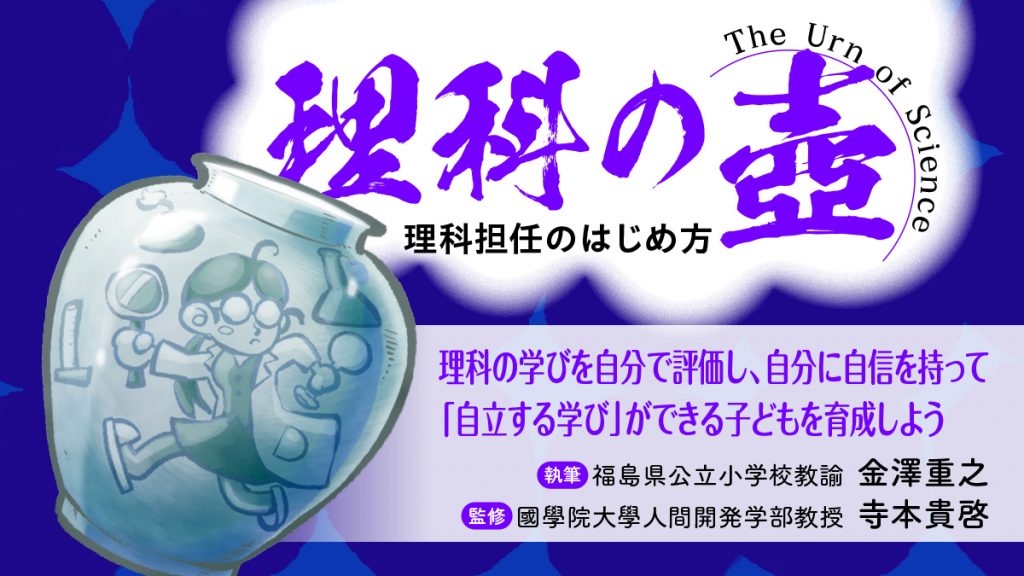
教育での究極の目的は、「自立した学習者」を育てることと言えるでしょう。しかしながら、小学生の最初から自立することはできません。なぜならば、知識や経験が不足していますし、理科で言えば科学的に問題解決をするマインドや解決方法のスキルが全く足りない点にあります。小学校時においては、問題解決の経験を重ねながら自立する学びに向けての基礎的な力をつけることになるでしょう。では、どのような指導をして自立する学びに繋げていけばよいのでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/福島県公立小学校教諭・金澤重之
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.「子どもの自立する」理科の授業とは
子どもと一緒に授業を創っていくことができたら素晴らしいですよね。私は、理科の授業において子どもたちが学ぶ目的をもち、互いに関わり合いながら、協働して学び続けていくことができるように教師が支えていくことがより一層求められていると考えています。私の考える「自立する学び」とは、教師が子どもの興味・関心などを大切にし、子ども一人一人に応じた学習の活動や課題に取り組む機会を多く設定することで、子ども自身が学習を進めていくことだと考えます。
そのためには、授業で解決すべき問題を見いだしたり、実験方法を「こうすると分かるかも」と自分たちで考えたり、自分自身の学びを客観的に見つめたり、友達と話し合い評価したりする機会を多く設けることが大切だと思います。私自身、試行錯誤しながら日々の授業に取り組んでいますが、今回は「子どもの自立する学び」を支えるために、「自分の学びに自信をつけること」について紹介します。

