探求心・課題解決能力が育つ!新学習指導要領時代の「海洋教育」とは
「海洋教育」という名称を聞いたことはありますか? 言葉の意味はわかっても、具体的にどんな実践、どんな学習を行うものなのか、しっかりと理解できている方は多くないかもしれません。実は海洋教育は、新学習指導要領の解説でも取りあげられていて、学校教育として積極的に取り組むことが求められているのです。また、教科横断的な学習により、アクティブ・ラーニングやカリキュラム・マネジメントの実践の場としても注目されています。ここでは、海洋教育の日本初の指導書『新学習指導要領時代の海洋教育スタイルブック-地域と学校をつなぐ実践-』の編著者の一人、東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター特任講師の田口康大さんのお話をお届けします。

海洋教育センター特任講師
田口 康大 さん
目次
海に近い地域だけが取り組めばよい課題ではない
海洋教育とは、「海と人との共生」という大きな課題に向かい、考え行動できる人材の育成を目指すものです。2007年に制定された海洋基本法では、学校や社会において海洋教育を推進していくよう定められています。
実は、戦前から1950年代中頃までの理科では、海に関することだけで一冊の教科書があるくらい、海に関連した学びは重要視されていました。やがて高度経済成長化とともに、第二次産業を中心とする産業立国のための学校教育振興が課題となり、結果的に海洋は第一次産業に近いものと捉えられ、海に関する学びは行われなくなっていきます。しかし、近年の異常気象、水産資源の問題、そして震災での津波被害などへの問題意識が高まっている今また、海に関する学びの注目度は高まってきています。
今年3月に出版した「新学習指導要領時代の海洋教育スタイルブック」では、小中学校における教育活動の実践例を取り上げていますが、海洋教育は海に近い地域で暮らす児童生徒だけが対象ということではありません。海に囲まれた日本では、内陸部に住む人も沿岸部に住む人も海から恵みをもらい、深く関わって生きていることに変わりないのですから。
たとえば、海洋ゴミの多くは、内陸部から排出されているという事実があります。内陸部の人々の生活と大きく関わりがある問題です。他にも、近年の豪雨や猛暑、台風などの気象災害に、日本全体が直面しています。これらは、地球温暖化に起因していますが、それら現象と海とのつながりを正しく知っている人が少ないのが現実。その他にも、普段の生活の中で、海が関連していることはたくさんあります。視野を広くもち、視点を変えれば、学校で取り扱う教材の中にも、海に関連したものがたくさん隠れています。
海洋教育は、新学習指導要領が掲げるカリキュラム・マネジメントやアクティブ・ラーニングの実践に適していると言えます。社会、理科、総合的な学習の時間、家庭科を自由な発想でカリキュラム構成した好事例を、この本の中では多数紹介しています。バリエーション豊かな授業実践例をぜひご確認いただければと思います。
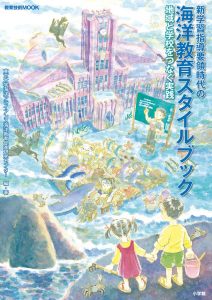
教育技術MOOK『新学習指導要領時代の海洋教育スタイルブック-地域と学校をつなぐ実践-』
東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター/編・著(小学館)
定価:本体1300円+税
試し読みはこちら
「海とともに生きる」ことに明確な答えはあるのだろうか?

ところで、「海と人との共生」のため、「海を大事にしましょう」と言われれば、皆「そうしよう」と思うけれど、具体的にどうすればいいのかはよくわからないと思います。子供だけでなく大人もわからないでしょう。
「海とともに生きる」ためにはどうしたらいいか? という問いには、決まった答えがあるわけではありません。地域によって暫定的な解はあっても、時が経てばまた変わるでしょうし、環境が変われば海も変わっていく。地域によってはもちろん、世代によっても考え方が違うでしょう。
そうであるからこそ、どこかに落ちている答えを探すのではなく、よりよい未来をつくるために試行錯誤しながら、考え続けることが大事なのだと思います。その時、先生と子供たちは縦の関係ではなく、並列です。子供たちも先生もいっしょになって探求していく。海洋教育は、情報を提示し取得させるというモデルの教育ではなく、子供たちの問いと思考に先生が伴走しながら、ともに「海とともに生きる」あり方を創造していくようなモデルの教育であると考えています。

