『総合教育技術』紙版終号に思うこと ー諸行無常の世、変化の生む光と影ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第57回】

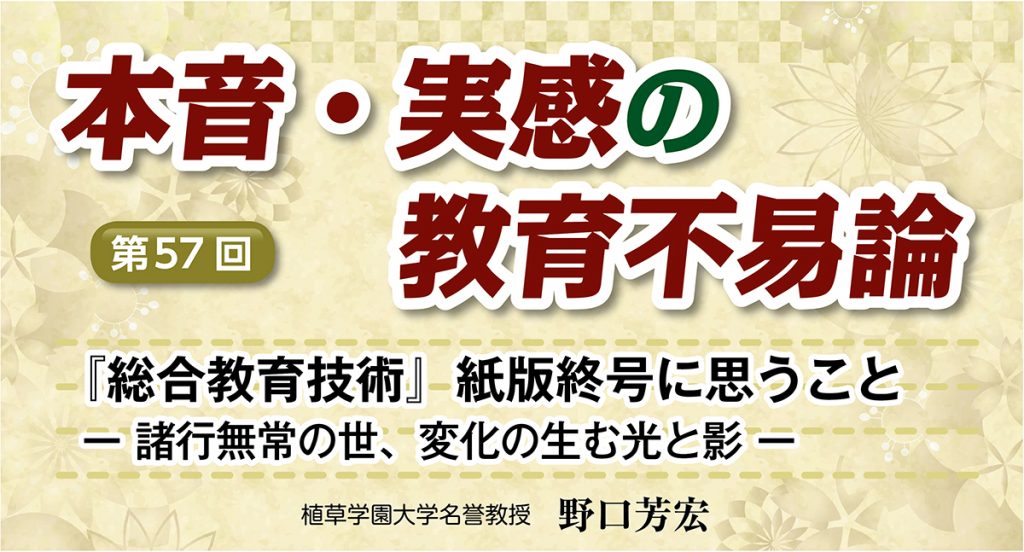
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第57回は、【『総合教育技術』紙版終号に思うこと ー諸行無常の世、変化の生む光と影ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 本誌のデジタル化、前向きに
私は電子辞書の愛用者である。平成の初め頃には電子辞書はかなり普及していたが、国語教師には一般に馴染みが薄く、紙の辞書派が大多数だった。だが私は逸早く電子辞書派を任じ、行く先々で電子辞書を推奨した。カシオの電子辞書の推薦文を書いたこともある。今でも電子辞書は常携、常用、愛用、手離したことがない。但し、いずれも「調べる」場合が専らである。
現在の電子辞書の収録情報は夥(おびただ)しく、文学作品や古典も収録されているがそちらは今以てついぞ開かず終いである。「楽しむ」「味わう」「浸る」「傍線を引く」「書きこむ」にはやはり紙情報、つまり本の体裁でないと読む気になれない。
小学館のPR誌『本の窓』は愛読誌の一つだったが、本の形からデジタル版になったのをきっかけにその後は全く読まなくなってしまった。読書イコール書籍、書物、本というのが私の習い性となった姿である。紙をめくるのとスクロールではやはり私にとっては大違いなのである。
愛読誌であり、また長年に亘って書かせて戴いてきた『総合教育技術』が、この「冬号」を以て紙の本からデジタル版に変わることになったと知らされた。金子書房の看板教育雑誌として親しまれて長い歴史を持つ『児童心理』が廃刊になった時には、「遂にそこまで来たか」という無念の思いに駆られたのだが、紙媒体としての本誌の終刊はそれ以上にショックが大きい。
ちょっとしたことを調べるには電子情報でも十分に事足りるが、少し込み入ったことや、じっくりと取り組んで考えなければならないような場合にはやはり紙媒体でないとそぐわない。パソコンで検索をしてもやはり紙に打ち出し、改めて紙に収めて読みこむことが多い。
本誌が装いを一新してデジタル版になるのを機会に、事態を前向きに捉えて、デジタル読書にも挑んでみようか、とも考えている。果たして紙情報と同等の成果、楽しみ、充足感が得られるかどうか、老後の新しい楽しみな課題でもある。
キャッシュレス、ペーパーレス、ボーダーレス、エンドレス、コードレス、シームレスなどなど、レス化によって簡便、スピーディーにはなっていくのだろうが、それによって世の中が静かでゆったりとした動きになればいいのだが、むしろせかせか、こせこせと今以上に慌ただしく、殺伐な世相になっていくのではないかとも気になることだ。そうならないこと祈るや切である。
デジタル化になっても、拙稿の掲載は継続をと有難い話を戴いている。「頼まれたら断らない」モットーを守ってもう少し「教育の不易」について考えたい。読者諸賢の率直な叱正をお願いしたい。

2 無常、変転の世、その光と影
昭和33年4月、それは私にとって忘れることのできない小学校教員としてのスタートの春である。当時の小学校の職員室では、どの先生の机の上にも小学館発行の『小○教育技術』という学年別月刊雑誌が載っていた。これは恐らく全国の職員室のごく普通の光景であったと思われる。みんなが読んでいた。定期購読の月刊雑誌だったから、近くの本屋の主人や店員が、直接職員室のそれぞれの先生の机の上に、無雑作に置いていくのが普通になっていた。その頃は、顔見知りの業者が気軽に顔パスで自由に学校や教室に出入りをしていた。
どこの学校の門も、朝から晩まで、所によっては夜でさえ開かれたままだった。また、私の出た小学校には大きな御影石の正門があり、西門もあったがどこにも門扉はなく、学校の校地には誰でも、いつでも入ることができた。田舎の学校は公園の役目も持っていたかのように、老若男女、大人も子供も、時には犬や猫の姿も見られ、誰からも親しまれていた。昔々の情景だ。
私は5年生の担任を命じられた。当時はガリ版印刷だったから、鉄筆と鑢板(やすりばん)と蠟原紙と修正液の使い方の練習をして学級通信を発行した。印刷が終わると謄写版インクで汚れた手を洗うのに苦労した。
間もなく、ボールペン原紙が生まれ、輪転印刷機ができ、印刷は随分楽になった。
就職した翌年、白黒のテレビが学校に寄付された。子供と一緒に日本史の番組を視聴した時には吃驚した。平安時代の貴族に扮した役者が十二単を着て寝殿造りの廊下を歩く姿である。貴族の日常が一目瞭然、よく分かる。もはや教師の出番ではないと悟り、毎週子供と視聴に励んだ。
だが、テストをしてみて驚いた。殆どの学習内容が習得されていなかったのだ。テレビ学習への不信感から私は再び教科書と黒板による拙い授業に戻った。
私はこの一件から「新しい文化」が必ずしも教育的には良いとは限らず、光と影の両面を持っているという事実を実感した。
子供は新しい文化に敏感で跳びつくように親しんでいく。その現象が教育問題になり、マスコミの大きな話題となって喧伝される。
テレビ問題、漫画問題、有害図書問題、テレビゲーム問題、携帯電話問題等々、大きな話題にはなるが、やがてそれが日常化すると共にいつの間にか人々の関心から忘れられていく。その繰り返しが続いている。
教員向けの学年別『教育技術』の雑誌群読者が徐々に減ってゆき、隔月刊や学年の統合誌やといろいろ試みたのだが残念な結果になった。
そもそも、「小学館」の社名が示すように、この大出版社は「国の将来を担う子供の健全育成」を期して設立されたのであった。スタートは『小学六年生』という子供向けの雑誌だったと聞いている。
「本」という文化の母体とも言うべき知の源泉が、今、急速に枯渇の危機に瀕している。とりわけ、教育という営みの主体となる教育者の読書離れは深刻な問題である。大学生の読書離れも問題視されていてそれも大きな問題だ。また、新聞を読む人口が大きく減っているのも重大な問題だろう。
パーソナル・コンピュータという新たな情報媒体の出現は、世の中の様相を一変するほどの威力を発揮しつつ広まっている。
大学生が有利な就職の為に、大学に通いながらデジタル系の専門学校にも通う例があると聞く。「デジタル技術に通じた人材なら、初任給が1千万円に届く可能性もー」と某紙にあった。企業界の「デジタル人材」の市場は引く手数多だとも言われ、現社員への「学び直し」(リスキリング)も盛んだそうだ。──急激な社会的変貌である。この巨大なうねりの中で、活字離れ、読書離れもさらに急速に進んでいくのだろうか。

