新型コロナウイルス禍への対処 ー「君子固より窮す。小人窮すれば斯に濫す。」ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第39回】

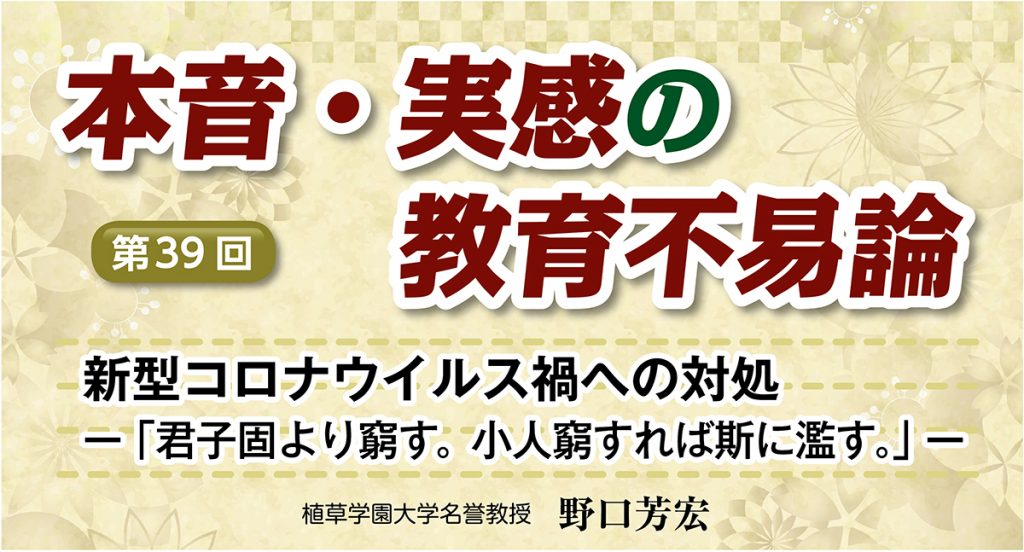
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第39回は、【新型コロナウイルス禍への対処 ー「君子固より窮す。小人窮すれば斯に濫す。」ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 コロナ禍、ハイペース
「国内感染1万人超す──9日間で倍増、東京181人」、令和2年4月19日(日)、産経新聞第1面のトップ記事の見出しである。リード文の結びは「3月末以降、1日の新たな感染者確認が数百人というハイペースとなり、市中での感染拡大の勢いは衰えを見せていない。」となっている。コロナの惨禍は、いよいよ勢いを増しているようである。
加えて、感染経路不明者数は増す一方である。どのように予防すればよいのか確たる方策も不明のまま、「密閉、密集、密接」の「三密」自粛が当面の努力事項となっている。「緊急事態宣言」は全国に及んだ。このことによって、同紙3面のトップは「耐える列島 週末閑散──観光地『売り上げ皆無』」という切実な見出しを掲げている。
大きくはオリンピック開催の中止、延期を始めとして、小さく身近な所では公民館や公共集会施設の閉鎖、学校の休校措置、様々な店舗の休業などなどがなされ、そのことによる解雇、内定取り消し、就業制限等が生活不安を生み出している。
これらは、多くの人々にとって未曾有の事態との遭遇であり、不安は増す一方である。かと言って、妙案がある訳ではない。成り行きを見る。様子を見るしかないのが実状である。では、どのように身を処したらよいのだろうか。

2 万物流転、諸行無常
改めてこの二つの言葉の本義を確かめておきたい。
万物流転 「万物は流動変化してきわまりないということ。パンタ−レイ 万物は流転するの意で、ヘラクレイトスの言葉」(『広辞苑』)
諸行無常 「仏教の根本思想で、三法印の一つ。万物は常に変化して少しの間もとどまらないということ」(『広辞苑』)
ほぼ同じような内容のことを述べた二つだが、前者は主としては物質的なことについて述べ、後者は人間の心について述べているニュアンスがある、という解説がある。
私は、この二つの言葉が好きで、北京に観光に行った折に篆刻(てんこく)の店でこの言葉を彫って貰い、短冊や色紙の関防印としてよく使っている。「万物流転」は古代ギリシアの哲人ヘラクレイトスの言葉であり、「諸行無常」は、釈迦の説いた仏教の言葉とされるが、いずれも真理を言い得て見事である。新型ウイルスのコロナ禍が大問題となっているが、問題が大きくなればなるほどこの言葉の重みを実感している昨今である。
思えば戦後70余年、天変地異の災害には何度か見舞われてきたが、それらはいずれも「ある地域」「ある範囲」での出来事であり、時間の長短はあるにしても、いずれは復興の予想が可能であり、それを目指した努力がなされてきたのだった。東日本大震災の放射能拡散も大事件だったが、それすらもせいぜい日本国内での問題であったと言える。
だが、今回のコロナ禍の規模は、今までのそれらとは比較にならない全世界的な、正に時空を超えた大事件である。人類史上初めてのオリンピック中止、延期決定の事実がそれを物語っている。
思えば、敗戦後この方の国民の生活は、戦禍に見舞われることがなかった「平和」のお蔭で、まずまずの「平穏無事」が続いてきたと言えるだろう。だが、その「平穏無事」が、この先もずっと永久に続くなどということは、本来あり得ない筈である。「万物流転」「諸行無常」の二つが、はっきりとそれを示している。不易の真理だ。
万物流転、諸行無常が説いていることがこの世の真理、本質、哲理であるとするならば、これを避けて生きることはできない。「受けて立つ」ほかはない。

