『和俗童子訓』(貝原益軒 著)に学ぶ(上)【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第35回】

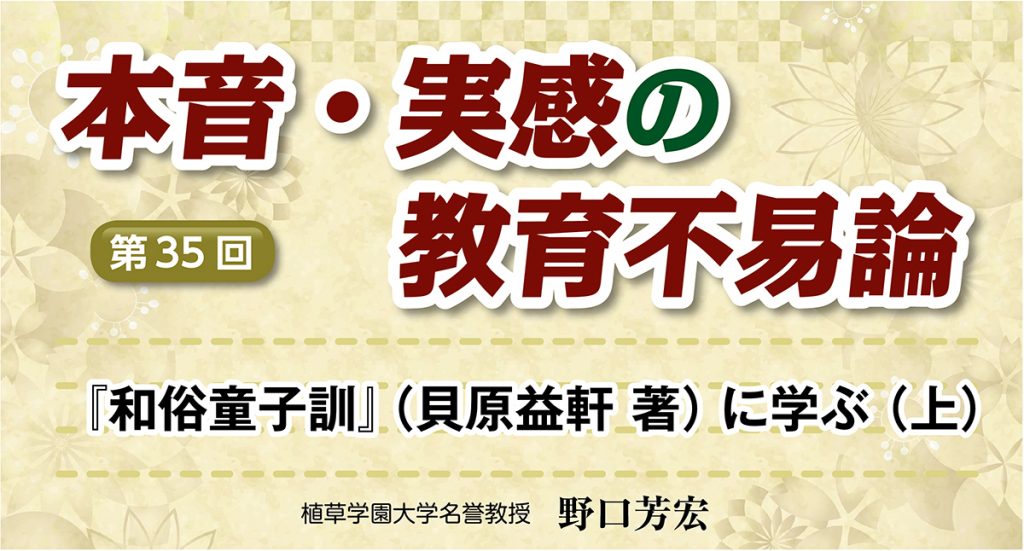
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第35回は、【『和俗童子訓』(貝原益軒 著)に学ぶ(上)】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 『和俗童子訓』推輓(ばん)の弁
『和俗童子訓』(貝原益軒 著)は、今からざっと300年前、江戸時代の1710年に著述されている。著者81歳の体験的実感論だ。現在は岩波文庫で読むことができる。その「解説」によれば、
「かれ(益軒)の教育思想が体系的にくみたてられている書物であるというばかりでなく、わが国における最初のまとまった教育論書である、といってさしつかえない。」
とある。私の大好きな一書である。
「人生50年」とも言われた短命の時代に、81歳にしてなお壮健、しかもその豊富な人生の実体験に基づく教育論であるところに本書の真価がある、というのが私の感懐である。
貝原益軒は『養生訓』の著者として著名、有名、高名を馳せているが、それに勝るとも劣らず『和俗童子訓』の価値は高い、というのが私の考えである。にもかかわらずこの著書についての現代語訳は未刊である。私は機会を得てそれに挑みたいと切望しているのだが、徒らに時を費やしている体たらくで残念かつそれを恥じている。
一言で言えば、現代の高度な文明による理屈、理論過剰な児童教育論よりも、本人の実体験に基づく簡潔、端的な直言の方がはるかに妥当、的確、的を射た警告になっている、というのが私の実感である。私の思いの一端を2回に分けて記したい。抄出は順不同である。了承を乞う。

2 教育は早期から始めよ
(原文)
──およそ人は、よき事もあしき事も、いざしらざるいとけ〈幼〉なき時より、ならひ〈習〉なれ〈馴〉ぬれば、まづ入(いり)し事、内にあるじ〈主〉として、すでに其性(せい)となりては、後に又、よき事、あしき事を見ききしても、うつり〈移〉かたければ、いとけなき時より、早くよき人にちかづけ、よき道を、をしゆべき事にこそあれ。(巻之一「総論」上)
──口語私訳──
およそ人間というものは、良いことも悪いことも、何も分からない幼い時から覚えて身につけてしまうものだ。だから、まず覚えたことがいつの間にか身についてしまい、その子の性分のようになってしまったならば、後になってからその善悪の本来について見たり聞いたりしても、もはや修正や訂正は中々できにくいものだ。
従って、物事の善悪もよく分からない幼い時から、良い人、立派な人に近づけて、物事の善悪をきちんと身につけるようにすることが肝要なのだ。(原文p.206)
──管見、私論──
幼児教育、保育についての考え方の一つに「自由保育」という立場がある。「子供の自主性と自発的な行動の育ちを目的とした保育理念」と説明され、「放任とは違う」と付け加えるのが一般である。対概念としては「設定保育」「一斉保育」などがある。後者は「保育者が主体となって、指導目的に沿って遊びを展開し、クラス全員で行うこと」であり、「日本の基本的なスタイルとしてよく見かける」形だとも言われる。
ここ数年、私は幼児教育の現場をよく訪問する機会に恵まれ、あちこち出かけているのだが、その全てが「設定保育」「一斉保育」の現場である。そこでは、子供の机は小学校と同じに、教室の前にある黒板に向かって整然と並び、一人の先生(保育士)が全員の子供に向けて一斉に同一の「授業」を展開している。「自由保育」を採用している園から私に対する訪問や指導を要請されることは皆無である。
さて、益軒の「いとけなき時より、早くよき人にちかづけ、よき道を、をしゆべき事にこそあれ。」という考え方をどう解するか。益軒は明確に「設定保育」の立場にある。この考え方は、古くて、時代遅れなのだろうか。私はそうは思わない。「古くて、新しい。そして正しい」──つまりこれこそが「本音・実感の教育不易論」と見たい。
ある解説によると、「設定保育」が「日本の基本的スタイル」ということだが、むしろ反対ではないか。現在の幼児教育界はその大方が「自由保育」の実践園である。
机は子供相互が輪になって座る「車座」スタイルで、黒板はほとんど黒板としては使われず、展示板つまり壁同然となっている。子供はそれぞれ何かをしているが、「活動あって指導なし」の状態である。絵本も紙芝居も遊具も沢山あるが、それらが一斉に活用されていることはほとんどない。そういう園が私を招く筈がない。「自由に伸び伸びと遊ばせておけば、自主性、主体性が育つ」と信じているらしいのだが、どうか。

