「否定」の教育的生産性への覚醒を【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第25回】

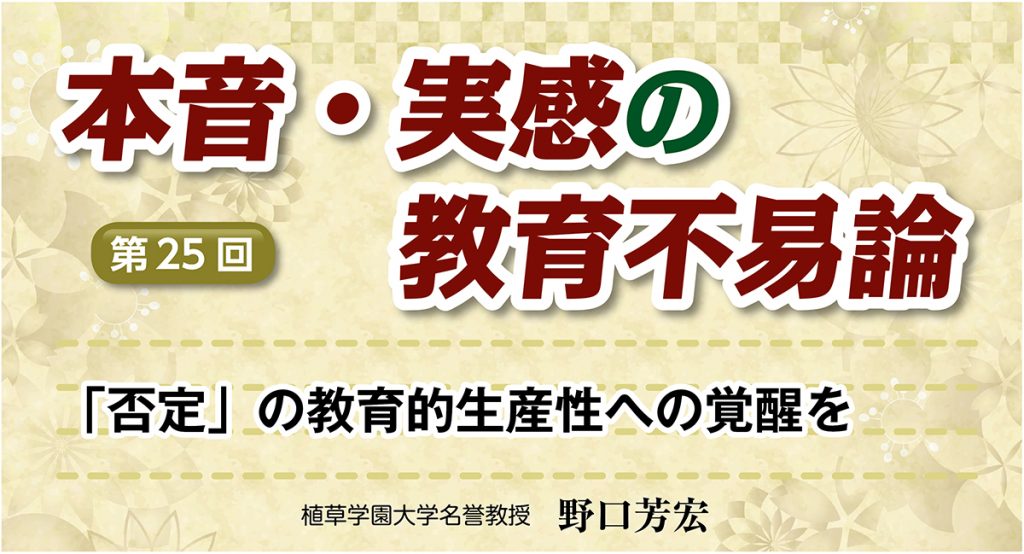
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第25回目は、【「否定」の教育的生産性への覚醒を】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 「否定」をしない風潮の考察
人それぞれに考え方や感じ方に違いがあるのだから、努めて「否定」を避け、肯定し、受容をしていくことが、一人一人の子供を尊重することになるのだ、という考え方がある。個性尊重、個性重視という考え方も軌を一にするものであろう。
その子なりに折角真剣に考えたのだから、その考えをなるべく尊重することが望ましいのだ。そういうことを忖度することなく、間違っているからと言ってばっさり否定するというのでは子供が可哀そうだ。子供は大いに心を傷つけられて失望することだろう。心を傷つけられることによって失望し、自信をなくし、勉強や学校が嫌いになる恐れもある。だから肯定的に受容し、温かく励ます方向で指導や教育を進めていくべきである。
かかる考え方は、「人権教育」の立場から考えても望ましい。「否定」は、そのまま「人権」の軽視、無視にも繫がりかねないので、十分な配慮が必要なのだ。
このような考え方が、現在の学校や教育現場で広く行き渡り、大方に肯定されているものである。私は、このような考え方を「否定の否定論」と呼んでいる。
それは、一見いかにもそれぞれの人格や人権を大切にしているように見受けられるのだが、果たしてそういうことになるのだろうか。改めて考えてみたいことである。まず、「否定」は子供の心を傷つけることになるのだろうか。
「子供の心が傷つく」という言い方、考え方を吟味してみたい。これは、子供の考えは正しく、妥当であり、本来「肯定」されるべきだということを前提として成り立っているものだろう。そうでなければ「傷つく」ことはない筈だ。
子供とは、そもそも不完全、未熟な発達途上の存在である。知識にも、経験にも乏しく、その考え方や、知識や、技術には多くの「不備、不足、不十分」な点が存在する。大人や指導者から見れば、子供にはそういう点が多々あるから、それらに気づかせ、正させ、改めさせ続けてこそ望ましい人間性を養うことが求められるのだ。だから、「教育」が必要になるのだ。
子供は、自分では気づきにくい不備、不足、不十分を指摘されることによって、新たな視点を与えられ、それを改めようと努めて成長していくのである。
このように考えると、「心が傷つく」という言い方は、決して望ましいことではなく、それは、不遜な思い違いであり、自己中心的な我がままな考え方だとも言えるのではないか。
さらに、それを「否定しない」でおくというのであれば、自己中心的な我がままをむしろ助長することにもなるのではないか。
そうであるとすれば、それは「教育の放棄」ということにもなりかねない。このような「教育の放棄」が、気づかれないまま学校現場に行き渡り、結局は子供の社会的成長を阻んでいるとは言えないか。

2 「否定」の歓迎、「否定」への感謝をこそ
大人であり、社会人であり、教育者でもある教師でさえ、人格的に完成してはいない。「人格の完成」は、成人してから死ぬまで「目指し」続けるべき課題である。いわんや子供においてはなおさらのことであろう。
未熟の自覚に立ち、少しでも成熟、成長を求めて努めることが、望ましい人としての在り方である。その思いが「謙虚」さというものなのだ。謙虚な人は伸び続ける。謙虚な人は、他からの「否定」についてひとまず「受け容れ」る。受容する。これが非常に大切な学びのポイントである。
時には、他からの「否定」そのものが間違っているという場合があるかもしれない。仮にそのような場合にも、「ひとまず」「受容」することが「謙虚」な態度である。少なくとも、自分では気づかなかったことがらを他から指摘され、自分が気づかされる、というのは、成長を求める者にとっては歓迎すべきことである。それのみならず、自分の反省によってその短所や欠点が正されるとすれば、その後の人生を幸せで豊かなものに変えていけるのだ。
それは「感謝」すべきことであるに違いない。「否定するな」という教育の在り方はこの根本的な子供としての在り方を忘れている。目の先の、当面の不快を避ける、その場しのぎのごまかし教育だとも言えよう。
子供の主体性、子供の自主性、子供の個性などという耳当たりのよい言葉によって、本物の教育がなされず終いになるのは何とも残念である。
「否定」を歓迎し、自分の今後の向上を希求し、「否定」に「感謝」するような教育をこそなすべきなのである。これを、私は「教育における否定の生産性」、または「否定の教育的生産性」と呼んでいる。

