「呪いの言葉」と「魔法の言葉」 ー正統・不易の教育像ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第23回】

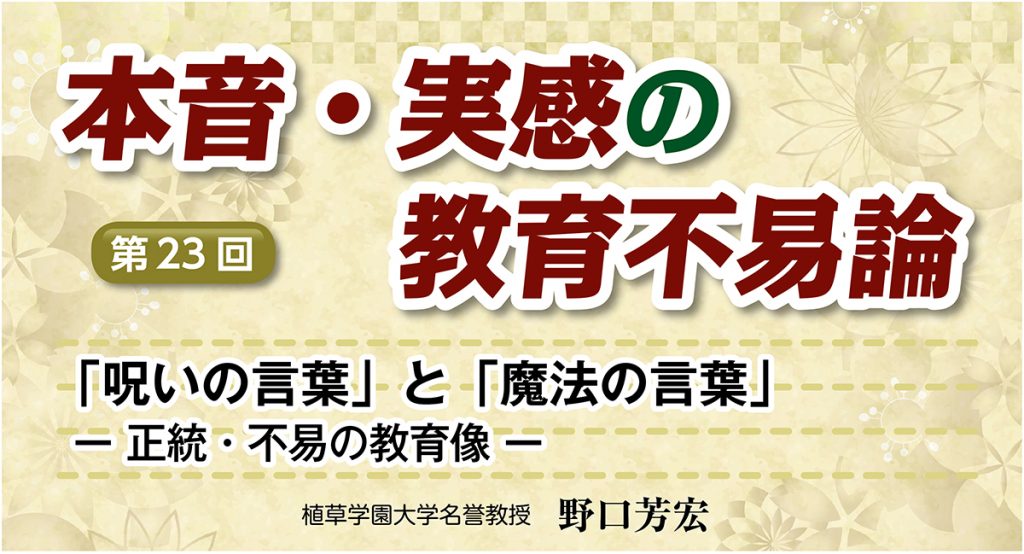
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第23回目は、【「呪いの言葉」と「魔法の言葉」 ー正統・不易の教育像ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 3つの「呪いの言葉」
ある本に「自己肯定感」について次のようなことが書いてあった。
次の3つの言葉は、いちばん使ってはいけない「呪いの言葉」だということである。
ア、早くしなさい。
イ、ちゃんとしなさい。
ウ、勉強しなさい。
この言葉に出合うと、「言われないとできないだめな子供だ」というメッセージを受けとり、「自己肯定感」をつぶしていく。自分に自信が持てず、失敗を恐れ、何に対しても前向きに取り組めなくなる。学力は、自発的、前向きにするから上がるのであって、親から強制されると前向きな気持ちが削がれ、勉強に対して心がマイナス状態になる。だから、この「呪いの言葉」はやめるべきだ。やめるだけで子供は変わる。
反対に、「ほめる」「認める」「信頼する」のプラスの言葉が子供をやる気にさせる。
例えば「いいね」という言葉がある。これは、「ほめる」というよりは「認める」という意味合いが強い。「前よりいい点が取れたの?」「おお、いいね」と言えば、子供は自分の存在を肯定され、尊重されていることを実感できる。これが「魔法の言葉」である。これによって子供の自己肯定感が生まれ、育ち、高まる──という訳である。
以上が、大まかな内容である。現在の社会、あるいは現代社会と言ってもよいだろうが、このような子供への対し方がよいのだとされ、広まっている。
だが、私はなるほどと頷きながらも、どうも釈然としない気分も残る。
「早くしなさい」「ちゃんとしなさい」「勉強しなさい」という親の言葉は、本当に「呪いの言葉」なのだろうか。我が子を愛する親なら、誰でもこの3つは言いたくなるのが普通なのではないか。
ぐずぐず、だらだらとしている子供に、「おお、いいね」とは言えまい。「早くしなさい」と、指示したり、注意したりするのは当然なのではないか。
また、親にそのように言われた時に、自分のあり方を反省し、親に言われたように従う子供であることが肝要ではないのだろうか。「強制されると前向きな気持ちが削がれ」ると言うのだが、子供のそういう親への対し方をそのままにしておいてよいのだろうか。
私が子供の頃というのは、戦時中、または敗戦の前後であり、途方もなく遠い昔になるが、子供は親の言いつけを守るべきだと教えられた。先生の言うことにも従うべきだと教えられた。親や教師の教えに従い、それを守り、親や教師の期待に応えるのが、よい子とされた。そういう子が、「まじめ」であり、「素直な」子供として称賛された。
その時代には、不登校の子供などはいなかったし、そういう言葉もなかった。教育は大人中心に進められ、子供は従うべき存在という考えが共有されていた。
「いじめ」も全くない訳ではなかったが、今のように子供を自殺に追いこむようないじめは存在しなかったし、その頃は子供の自殺などは聞いたこともない。
「呪いの言葉」論は、子供中心主義を基礎にしていると私は考える。子供はそれなりに主体性を持ち、一つの人格を持っているのだから、それらを十分に尊重しなければならない、という考え方である。

2 「呪いの言葉」なのだろうか
櫻井よしこ氏に『大人たちの失敗』というPHP研究所から出版されている文庫本がある。教育に関わる者にはぜひ一読してもらいたい本である。その中に次のような話がある。
日本の小さい子供に「先生の言うことを聞いた方がいいのか、聞かなくてもいいのか」と問うと、8割の子供がどっちでもいい、自分の自由だと答える。
アメリカでは8割以上の子供が「先生の言うことは聞かなければならない」「それは子供の義務であり、責任である」と答えている。このことからも分かるように、アメリカの学校では、一に規律、二に規律、三も規律という厳しい教育が行われている。学校のルールはみんなで守ってこそルールなのだ。我が儘や勝手は許されない。こうした非寛容の教育はゼロトレランスと呼ばれ、これが教育の基調となっている。(前掲書『大人たちの失敗』p.67)
私は、大きく頷きながら、傍線を引き、書きこみをしながら読んでいるが、謙虚に、そして静かに、日本の流行的な教育の風潮を見直してみる必要があるのではないか。
日本の最初の本格的教育論と言われる『和俗童子訓』(貝原益軒著 岩波文庫)という貴重な本がある。私の愛読書の一冊だ。その「巻之二」に「父兄の咎めに遇った時、子供のとるべき態度」という項があり、その冒頭に次のように書かれている。
「子孫、年わかき者、父祖兄長のとがめをうけ、いかりにあはば、父祖の言の是非をゑらばず、おそれつつしみてきくべし。」
今風の言い方に直せば、「子供や若者は、親や長上の者から注意されたり叱られたりした時には、その言葉や内容の良い悪いは別にして、まずはその教えを素直に聞かなければならない」ということである。
さらに続けて次のように言う。
「いかに、はげしき悪言をきくとも、ちりばかりも、いかりうらみたる心なく、顔色にもあらはすべからず。」
つまり「どんなに激しい言葉で責められ、叱られても、いささかも憤慨したり、反抗的で不快な表情などを見せてはいけない」というのである。
これは、櫻井よしこ氏の「アメリカの子供の8割以上が先生の言うことを聞くのは子供の義務であり、責任である」と考えていることと相通ずるものと言えよう。私も全くその通りだと考える。それが、権威ある人の教えは守り従う、ということであり、世の中や社会、国家の秩序、規範は守るべきだということである。
「早くしなさい」「ちゃんとしなさい」「勉強しなさい」という3つの言葉は、親が子供を愛するが故に、親から発する「とがめ」の言葉である。それに対して子供や若者は「おそれつつしみて聞くべし」と貝原益軒は言うのだ。
ところが、現代はそれを「呪いの言葉」だと言うのである。これは正しい考え方か。

