教員の資質向上実践論(上)【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第19回】

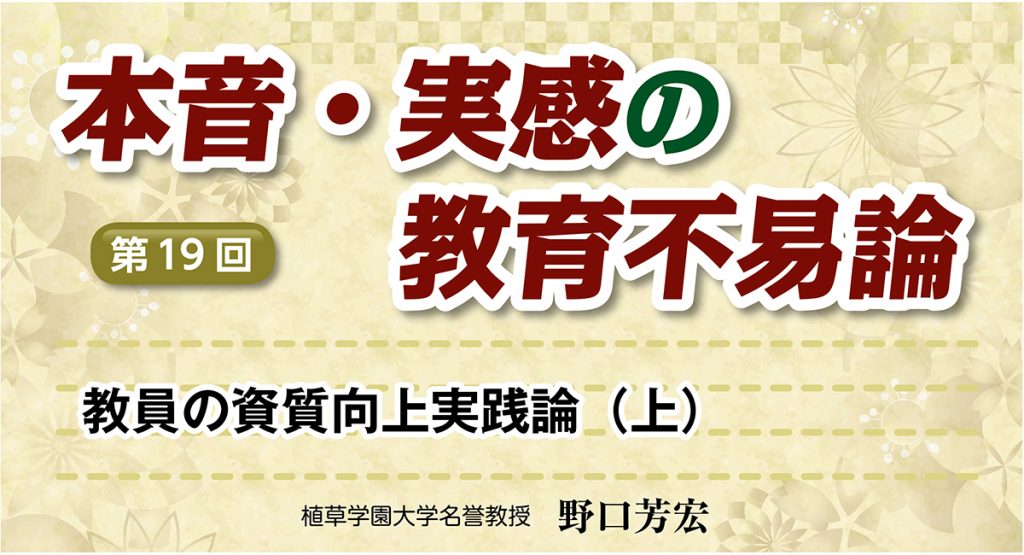
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第19回目は、【教員の資質向上実践論(上)】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 教育制度の限界
23歳で教員としてスタートをし、60歳の定年で退職するまでの38年間を、小学校という現場でだけ通した。その間に「学習指導要領」の4回の改訂を経験した。昭和33年に就職した私は、戦後教育史上最大の教育制度改革の真っ只中に遭遇した経験を持つ。
筆頭は「道徳」の特設である。「戦前への逆戻り」「軍国主義への道」「思想統制の危機」と、日教組は大反対をした。また、教頭の職位が「管理職」と位置づけられ、組合への加入が禁じられた。加えて、勤務評定制度が導入され、教員の勤務の状況が校長によって評定されることになった。
「全ては組合の弱体化策」として、日教組は空前の反対運動を展開したが、全ての制度は法制化され、具現した。
このような大変革の年に教員をスタートし、その後も全国一斉学力調査の実施と中止、道徳教育の手引きの全教員配布、教科書無償配布、国旗・国歌の法制、同和教育、人権教育、臨教審の設置などなど、いろいろの主張や反対や消長があった。これらを身を以て体験した私は現在82歳、歴とした後期高齢者となった。公立学校を退職してから22年を経た。その後は専門学校、短大、大学に勤め、ざっと60年の教職を経験した。現在も、あちこちで授業をし、若い先生方との学習会を楽しんでいる。66歳からスタートした「授業道場 野口塾」は、195回に達した。元気なら200回に届くだろう。
さて、そんな経歴を経て今の私は、つくづく思うことがある。それは、
教育の内実は制度によっては変わらない。教育の制度改正や改訂では学校の実態はほとんど変わらない。
ということである。
数えきれないほど、思い出しきれないほどの教育制度の改変がなされたが、肝心の子供への教育成果は決して上がってはいない。いじめ一つ、不登校一つ、解決には到っていないのが何よりの証拠である。
一体、何が問題なのか。何をどうすればよいのだろうか。
学校教育の内実を変えていくのは、日々子供と直々にかかわり、親とかかわっている「現場の教員」の「資質向上」「意欲向上」こそが、時代を超えて変わることのない、唯一の解決策である。私はそう確信している。
誤解のないように断っておくが、「現場の教員の努力不足」を指摘しているのではない。現場の教師の「努力」は、もはや限界である。これ以上の努力を強いれば、「体をこわすか」「頭をこわすか」「家庭をこわすか」しかあるまい。日本の教師は世界一勤勉で、世界一過労気味なのだ。


