意外と忘れられがちな「学習の目的」を把握することの重要性 【理科の壺】

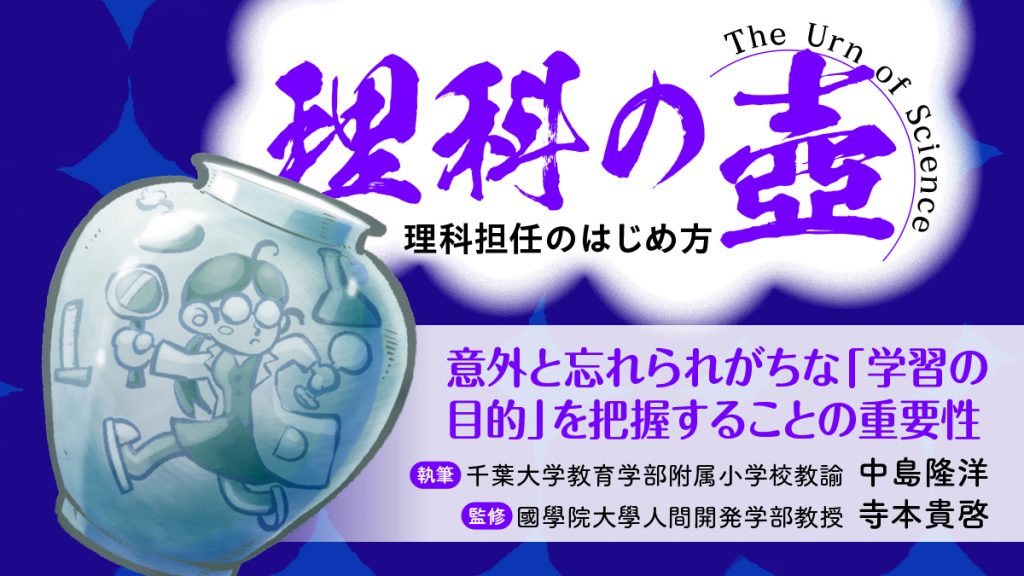
先生方が授業をする前に、授業の目標を立てられると思います。この目標は「資質・能力の三つの柱」【知識・技能】【思考・判断・表現】【主体的に学習に取り組む態度】で書かれると思います。ここで、単元で扱う教材から何を学ばせたいのか? という、<理科としての・教材としての>目的まで意識されていますか? 教科書で扱っている教材と、それらが提示される順番には必ず意味があります。
今回は、そもそもの「学習の目的」についてです。例として一部だけのご紹介になりますが、他の単元、教材についても調べてみると、より指導が深いものになると思います。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/千葉大学教育学部附属小学校教諭・中島隆洋
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
答えられそうで、意外と答えられない学習の目的を教師が把握していると、児童の学びが豊かに変容していきます。4年生の学習の中から3つの例を挙げて、先生方と一緒に考えてみたいと思います。
1.4年生「空気でっぽう」の学習
 なぜ児童に「空気でっぽう」を渡すのでしょうか?
なぜ児童に「空気でっぽう」を渡すのでしょうか?
この問いに、みなさんはどのように答えますか?
●遊ばせる中で、空気の性質に目を向けさせるため?
●教材として注文したものが手元にあるため?
●「空気でっぽうに空気や水を入れて玉をとばしてみよう」と教科書に書いてあるから?
様々な答えが返ってきそうですが、私なりの「目的」を1つ紹介します。
私の場合、以下のように答えます。
授業の最初は、見えない空気の存在に気づけるように、空気を袋に集めて触ったり、袋の上に軽く乗ったりします。
閉じ込めた空気に力を加えたとき、空気自体の体積が変化したのかどうかを考える場面がありますが、袋のように形が変わる入れ物では、空気自体の体積が変化したのか、それとも変化しないのかがはっきりしません。話合いの場面で、「空気がバネみたいに縮んだ」と考える子もいれば、「空気が袋の中を移動しただけで、空気自体はバネみたいに縮んだりはしない」と考える子も出てきます。

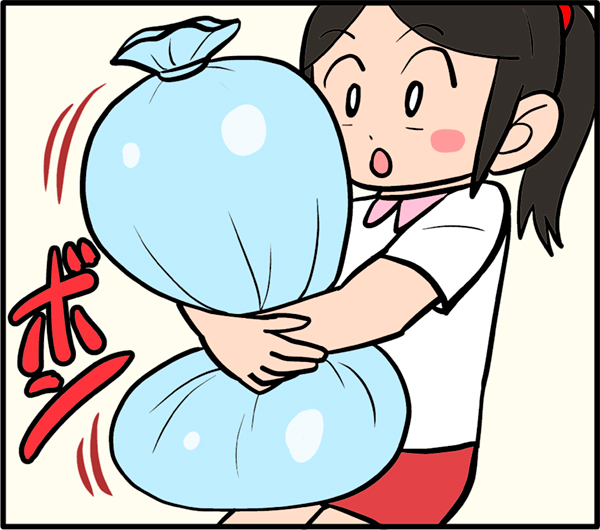
閉じ込めた空気の性質を調べる場合、入れ物の形が変化する袋では空気自体の体積が変化したのかどうかはっきりしないため、どうすればよいのか? と児童に問う瞬間を、授業の中で“空気でっぽう”に位置づけてみてください。すると、児童からは
「硬く、形が変わらない注射器の様な筒に空気を閉じ込めて押せばはっきりする」
といった言葉が引き出されることでしょう。これが、「空気でっぽうを児童に渡す目的」になるのです。


「空気って本当にバネみたいに縮むのかな」と意識して、ドキドキしながら棒を一押しする姿は、「今日はこれで遊ぼう」といきなり空気でっぽうを渡しただけでは見ることができない姿です。
また、空気の性質(縮んだり戻ったりする性質)を獲得した後に空気でっぽうで遊ぶ方が、空気の性質と遊びの中で発見した事実とを常に“関係づけ”ながら思考する事ができるようになるはずです。
さらに、空気の学習を終えた後に、「加えた力と水の体積変化」の学習に移行する際にも、この学びが生きてきます。
例えば、水を袋に入れて外から手で押すと、水が縮んでいるような感覚に陥ります。しかし、筒の様な変形しない容器に空気を入れる必要性を理解している児童は、「水も筒に入れて調べなくてはダメだ」と先行経験を基に考えることができます。
このように、空気でっぽうひとつを取り上げても、教材化されたものには必ず目的があります。その「目的を教師が理解しているだけで、児童の学びは豊かに変わっていく」とは、こういうことです。
2.4年生「ヘチマ」の学習
 なぜ庭で「ヘチマ」を育てるのでしょうか?
なぜ庭で「ヘチマ」を育てるのでしょうか?
年度当初、学年教材として庭にヘチマ(またはゴーヤなど)を植えてきたことだと思います。
さて、どうしてヘチマを植えなければいけないのでしょう?
●理科主任の先生に、「植えておくべきものだ」と年度当初に言われたから?
●理科の教科書に載っていて、観察する学習が設定されているから?
●グリーンカーテンとして植えておいて、総合の環境学習と横断させるため?
私の場合、以下のように答えます。
4年生では、「生き物の様子と気温を関係づけて考える」という学習が年間を通して位置付けられています。春の学習の最後に、春から夏にかけて、生き物の様子がどのように変化していくのか予想を立てると、児童からは「気温が高くなるにつれ、成長の様子も活発になると思う」といった考えが出されることがあります。その予想を確かめるために、「ヘチマを植えて調べよう」といった流れに移行していくことが大切になります。
児童はその時、「気温と植物の成長の様子を“関係づける”実験教材として、ヘチマを育てる」という目的をしっかりと理解することでしょう。
このような目的をしっかりと児童が把握している場合、観察対象も「気温と成長との関係性」といった点に、自ずと焦点化されていきます。もちろん、それ以外の情報を観察してはダメということはありません。しかし、メインの観察対象や目的を児童がはっきりと把握しているかどうかはとても重要となってくるわけです。


 なぜ児童に「空気でっぽう」を渡すのでしょうか?
なぜ児童に「空気でっぽう」を渡すのでしょうか?