理科授業での “対話のススメ” ~子どもたちの問題解決の質を高めるために~【理科の壺】

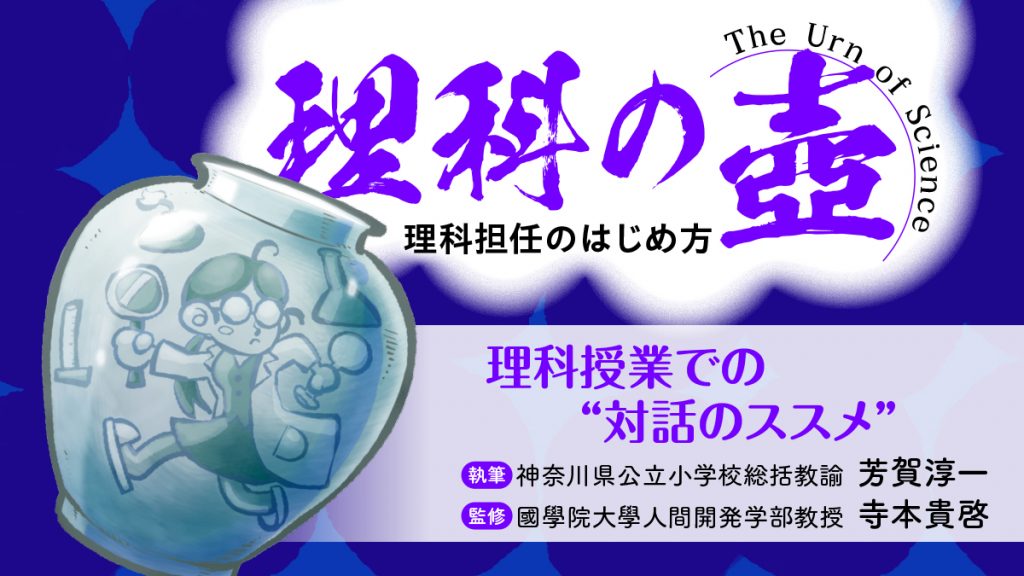
2022年4月に行われた全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙での「理科の勉強は好きですか。」という質問に対して、肯定的な回答をしている児童の割合は、79.7%との結果が出ています。理科離れが言われるようになって久しくありませんが、依然として、理科は子どもに好かれている、もしくはあまり嫌われていないと言えるでしょう。 そして、子どもに「理科のどこが好きか」をたずねると、おおよそ「実験や観察が楽しい!」という答えが返ってきます。確かに理科では、校庭に出かけて虫取りや散策ができたり、普段は自由に使うことが許されていないもの(例えば火や薬品など)を使うことができたりと、「わくわく」「面白い」といったイメージがあるのだと思います。自然や科学の不思議さや面白さからくる「楽しい」「好き」も大歓迎ではありますが、やはり授業の中で友達と一緒に考えを交流したり話し合ったりしながら解決していくこと自体の面白さや楽しさも大いに感じてもらえたらうれしいですね。そこで、理科授業での対話についてまとめてみました。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校総括教諭・芳賀淳一
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.そもそも、なぜ“対話”が大切なの?
主体的・対話的で深い学びを視点とした授業改善の必要性がうたわれていますが、理科授業での対話は、「問題解決の質を高めるため」にあると考えます。対話を通して、自分の考えを独りよがりの考えではなく、より科学的な考えに、より妥当な考えに更新していくことができるのです。
対話によって
●自分の考えに自信がもてるようになる
●視点が広がったり増えたりする
●間違いに気付き、修正の必要を感じる
●新たな見通しや方法が見つかる
●考えの客観性や妥当性が高まる
●求めていた納得解が見つかる etc.
「方法の質」や「結果の質」、「自分自身の質」を高められる!

