「教育環境日本一」を目指す京都市 2つの子ども支援事業とは
子どもや若者たちを心豊かに育むまちづくりを、市民ぐるみ、地域ぐるみで実践し、「子育て・教育環境日本一」を目指している京都市。2017年には、子どもや若者に関する施策を総合的に推進する「子ども若者はぐくみ局」を創設するなど、子ども・子育て支援のより一層の充実に努めています。今回は、そんな京都市が取り組む2つの子ども支援事業、「放課後まなび教室」と「子どもの居場所づくり支援事業」を取り上げ、その概要やこれまでの成果について、それぞれの担当者に話を聞きました。
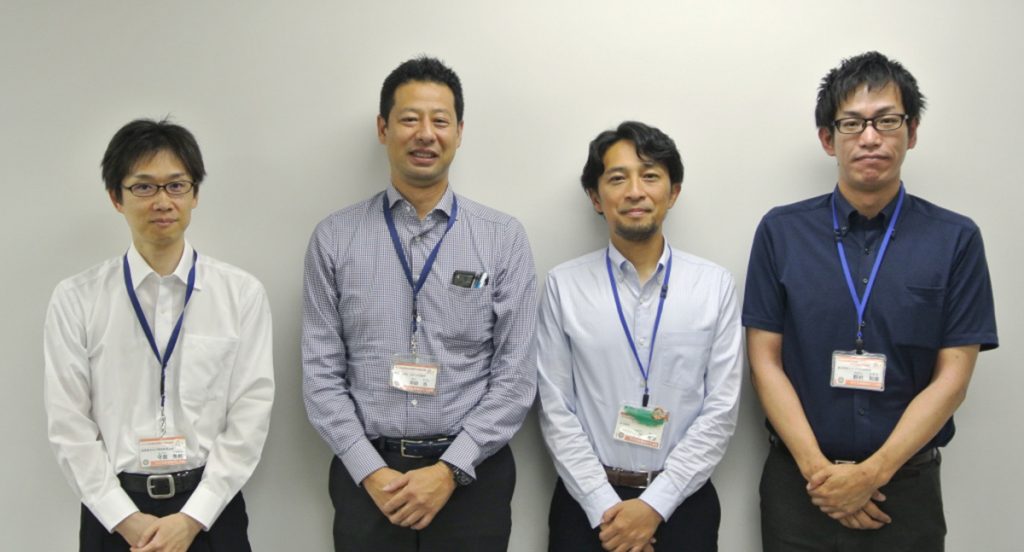
目次
自学自習の習慣化を目指して「放課後まなび教室」をスタート
「放課後まなび教室」は2007年から京都市がスタートさせた取り組みで、学校施設を活用し、地域の人たちや、学校運営協議会、学生等の協力のもと、放課後の子どもたちに「自主的な学びの場」と「安心安全な居場所」を提供するというものです。
「これは、子どもに関わる重大事件の続発、家庭教育力の低下などを背景に、国が創設した『放課後子ども教室推進事業』の京都市版です。教室の運営には地域の方たちに参加していただき、学校や家庭とは異なる、地域ならではの居場所をつくっているのが特徴です。また、京都市ではすべての子どもたちが対象というところにもこだわっていて、2009年以降は、京都市内のすべての小学校区(現在は163校)で展開しています」と青少年・若者・まなび担当課長の羽田浩さんは説明します。
費用は保険料が年間800円。授業終了後から最長午後6時まで利用することができ、学校区によって異なりますが、学校の専用教室、図書館などを利用して週に3〜5日実施されているということです。
遊びと生活の場を提供する学童クラブに対して、放課後まなび教室の目的は、子どもが自分のペースで学習する場を提供すること。それによって子どもたちに自学自習の習慣化を促すのが主なねらいです。運営は、学校単位で実行委員会を組織しているので決まりがあるわけではありませんが、基本的には子どもが宿題や計算ドリルを持参して勉強し、その様子を地域のボランティアスタッフが見守るという形がとられています。
「まずは、共働きなどの事情により家に保護者が不在で、一人ではなかなか宿題ができないという子どもや、さまざまな家庭事情により落ち着いて宿題をできる場所がない子どものための居場所づくりを目指しています。その上で、子どもたちが、学校や家庭ではなかなかできない体験活動、例えば、手芸や工作といったものづくり体験や、伝統芸能、伝統工芸、茶道などといった伝統文化にふれる体験などもできる場にしていきたいと考えています」と羽田さん。
大事なのは「自ら学ぶ意欲を育む」こと
京都市では、年に数回、実行委員会のメンバーらを対象にした研修会も実施しています。「子どもたちが喜ぶ手作り体験」というテーマで行われた研修会では、「ビー玉を使った、かんたん万華鏡(九条弘道小学校)」、「牛乳パックでつくるキュービックパズル(安井小学校)」などの具体的な実践例が紹介され、参加した実行委員たちも実際にものづくりを体験。研修会終了後には、「さっそく、自校の教室で実践しました」という報告が次々と寄せられました。また、研修会の場は各実行委員会同士の情報共有の場にもなっていて、毎回、熱心な情報交換が行われているそうです。
では、実際に放課後まなび教室に参加している子どもたちはどんな感想を持っているのでしょうか。羽田さんによると、「勉強の仕方がわかった」「みんなと一緒に学ぶとやる気が出てくる」「地域の人と話をしたり、活動したりできるのが楽しい」といった声を聞くことが多いそうです。こうした感想からも、「自学自習の習慣化」や「地域の人との交流活動」など、京都市が当初、設定した目標が、子どもたちにまでしっかり浸透していることがわかります。
また、この取り組みの成果としては、地域のスタッフと学校の教職員との連携が進んでいることも挙げられる、と羽田さんは続けます。学校の先生たちからも、「子どもに自ら学ぶ姿勢が見られるようになった」という声が多く寄せられているそうです。
「先生たちが、実行委員会のスタッフ会議に出席したり、子どもの様子を見に放課後まなび教室を訪問したりすることも徐々に増えてきました。また、地域のスタッフが学校の授業を見学し、放課後まなび教室の運営に生かすという例もあります。学校教育だけでなく、こうして子どもを地域ぐるみで育む『はぐくみ文化』が息づいているのが、京都らしさであり、強みだと私たちは考えています。市としては、こんなふうに両者が目標や課題を共有することで、どんどん相乗効果が生まれることを期待しています」
ただ一方で、取り組みが定着してきた今、放課後まなび教室の登録児童数も年々増加傾向にあり、スタッフの確保や教室の確保が困難になるという新たな課題も生まれています。これは期待が膨らんでいることの表れとも言えますが、京都市としては今後、各学校区の実行委員会、そして学校とも連携を図りながら、それぞれの状況に応じた支援を進めていく予定だということです。
「放課後まなび教室は、いわゆる貧困家庭の子どもを対象にした学習支援とは異なりますが、対象者の中には貧困家庭の子どももいますし、他にもさまざまな困りごとを抱えた子どもがいます。放課後まなび教室による自学自習の習慣化、地域の方や異学年児童との交流による豊かな体験等が、そのような子どもたちを支援することにもつながればと思っています」と、放課後まなび教室推進係長の守瀬秀則さんは言います。


