子供が主体的に取り組む宿題の出し方~多様性を受け入れるクラスづくり(第6回)~加藤典子先生×高山恵子先生対談

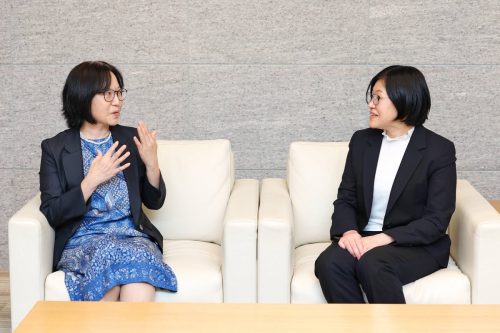
「多様性を受け入れるクラスづくり」をテーマにした、文部科学省特別支援教育調査官を務める加藤典子先生と、NPO法人えじそんくらぶ代表・高山恵子先生による対談の最終回。
前回は、習熟や学習の定着について学校の学習時間に行うことと、家庭の学習習慣の中で行うものとを区別するタイミングにきているかもしれないということが加藤先生から提言されました。今回は宿題の多様性について考えていきます。
加藤典子(かとう・のりこ)文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官。鳥取県出身。鳥取県の公立小学校で教員を14年間務めた後、鳥取県教育委員会特別支援教育課指導主事(LD等専門員)や鳥取市教育委員会学校教育課主査などを経て、令和2年度より現職。
高山恵子(たかやま・けいこ) NPO法人えじそんくらぶ代表。臨床心理士。薬剤師。昭和大学薬学部卒業後、約10年間学習塾を経営。1997年アメリカトリニティー大学大学院教育学修士課程修了(幼児・児童教育、特殊教育専攻)。’98年同大学院ガイダンスカウンセリング修士課程修了。木村泰子先生との共著『「みんなの学校」から社会を変える』(小学館新書)など、著書多数 。
目次
高学年では、子供が主体的に宿題を考えることも可能
加藤先生 学習の定着を家で図らせるのはなかなか難しいのですが、宿題という形でそこも使いたいという思いは、教員としてあります。
高山先生 「定着は繰り返しから」という概念が入っていますが、繰り返さなくてもわかる子もいるので、その宿題はいらないだろうという子もいます。逆に、繰り返しても定着しない子もいます。この2つの課題をどうするかですね。
加藤先生 そうなんです。
高山先生 漢字を10個ずつ書くというのが、本当に平等かということを先生方に真剣に考えていただかないと、「全員違う学び方をしていい」というところにつながっていかないと思うんです。
夏休みの宿題に出される読書感想文の「課題図書」を例にとると、読み書きのレベルがいろいろなのに、同じ本で感想文を書きなさいだと、難しい子もいますよね。自分にあったレベルの本でいいと思います。絵本でもいい本はありますし、このあたりから「多様な選択肢をつくる」という発想を入れていただきたいのですが、難しいでしょうか?
加藤先生 夏休みの宿題は、生活リズムや生活習慣づくりのためという理由もあると思います。
高山先生 確かに、宿題を出してくれないとゲームばっかりやるので、宿題出してくださいという保護者もいますね。保護者にも多様性があって、宿題に対する考え方が全く違います。
加藤先生 大切なのは目的なんですよね。

編集 保護者も含めた、目的の共通理解が必要ですよね。3者面談をやって、宿題を3人で決めると子供も納得すると思います。ただ、そういうことをやっているところはほとんどないようです。
加藤先生 発達段階を踏まえることも大切で、高学年になると、本人との対話はますます重要になってきますね。
高山先生 そして、そういう話合いの内容を、次の学年や中学校につなげることもすごく重要です。宿題ができなくて不登校になったり、自殺する子だっているわけなので、真剣に考えなくてはいけないと思います。 親が宿題を少なくしてくださいと言ったとき、それだと受験どうするんですかという先生がいらっしゃいます。でも、その前に体調不良、メンタルヘルスの不調、そして不登校になったらどうするのか、というところに焦点を当てることも大切だと思います。ただ、先生の立場としても難しいとは思います。
加藤先生 葛藤するところですよね。でも高学年だと、自分で決めるということがすごく大事ではありますね。
高山先生 宿題に主体性を発揮するということですね。
加藤先生 本人と話をして、「こういうことを目標にしたいんだけど、あなたはどうする?」とたずねて決めてもらえれば、自分で言ったことは自分で責任持たなきゃいけないよっていう話にもできます。

