子どもの自立を促す生徒指導とは
一学期も終盤を迎え、学級のルールも浸透してきたころでしょうか。中には、うまくいっているところと、そうでないところもあるでしょう。そこで、子どもたちと一緒に、学級生活の振り返りをする際のポイントについて、考えましょう。
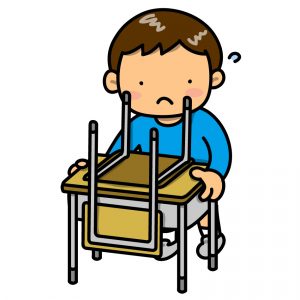
目次
解決策につながる指導の仕方
振り返りをしていく中で、クラスの問題点を探そうとするだけでは、状況はよくなりません。
「なぜ、こんなことしたの?」
「なぜ、だまっているの? 何とか言いなさい」
こんな指導をしてしまう場面はないでしょうか。
「なぜ?」という問いは、相手を責めるニュアンスがあり、言われた子どもは、言い訳をしそうになりがちです。問題点が出てきたときには、ぜひ「どうしたらいいかな?」と問いかけてください。解決策を導くことができるはずです。
×「なぜ、○○したの?」→責めていると感じとられる
○「どうしたらいいかな?」→解決策を導くことができる

子どもがめあてを設定することで自立を促す
担任が活動のめあてを決めてしまうと、「やらされている感」をもってしまう子どもが出てきます。それを解消し、よりよい姿にするために、子どもにめあてを設定させるのです。めあてを考えるということは、今できていないことに目を向けることです。これは、クラスや自分の現状を振り返るよい機会になります。そこから、課題を見つけて取り組むようにするとよいでしょう。

また、先に述べたように解決策を話し合うことも大切です。例えば、朝の会で、子どもたちが「今日のめあて」を決める時間を設けてみましょう。この話合いでは、理由を明確にして発表するように指導します。決まった内容は小黒板などに書いて確認しやすくします。そして、帰りの会では、「今日のめあて」について振り返りを行い、達成できたことを認め合いましょう。
このように、毎日の生活の中で子どもたちが話し合って決めた、めあてが達成できるように支援してあげましょう。そのことが「自分たちでできる」という自信につながり、自立につながります。また規律を意識するようになっていくのです。
めあてを達成している自分たちを具体的に想像させてみることも大切です。それが、普段の何気ない行動につながります。これがクラスのムードづくりにつながれば、学級の人間関係をもよりよくするチャンスです。

