自己有用感を育む!下級生との異年齢交流活動の具体例
自己有用感が育まれる、下級生との交流活動のポイントを紹介します。
執筆/福岡県公立小学校教諭・甲のぞみ

目次
自己有用感とは
高学年の子供たちにとって、学校の中でのリーダーとして活躍することが、自己有用感を高めることにつながります。
自己有用感とは、「人の役に立った」「友達に喜んでもらえた」など、他者との関係があってこそ生まれるものです。教師は、子供たちが、「自分は誰かの役に立っている」と感じられるような場を、意図的につくり出していくことが大切です。
そのために、下級生との交流活動は、担任だけでなく、学年全体、学校全体で協力しながら進めていきたいものです。

交流活動のポイント
活動内容
次の3点を中心に子供たちと一緒につくっていきましょう。
- 子供たちが楽しいと感じられるもの。
- 子供たちの能力に応じたもの。
- 子供たちが主体的に取り組めるもの。
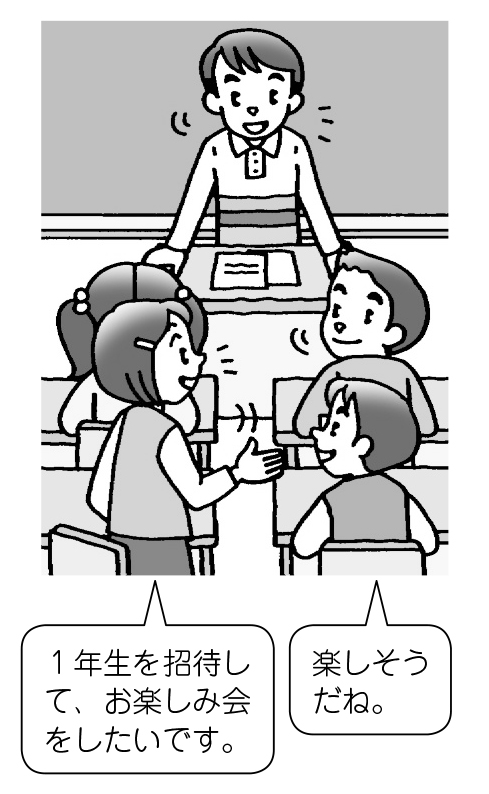
時間の確保
活動に応じて、事前学習(計画や準備)と事後学習(振り返り)の時間を確保しましょう。子供たちが自主的に休み時間を使う分にはよいですが、教師の指示で休み時間を使わせると、楽しさや主体性が失われる子供もいます。
教師の役割
教師の役割は、高学年の子供たちが下級生に好ましい影響を与える場や機会を準備し、そうした機会が好ましい影響力で満ちる仕組みをつくることです。
①事前の活動
- 計画や準備に必要な内容を明確にする。
- 子供たちに目標を持たせる。
②活動中
- 全体の流れを見ながらアドバイスをする。
- 児童の様子を観察し、よかった点を伝えられるようにしておく。
③事後の活動
- 振り返りの視点を明確にして、次回の交流に生かせるようにしておく。
- よかった点を具体的に伝える。
また、下級生の担任と連携して、活動が終わった後には、下級生から高学年の子供たちへ、お礼の手紙が届くようにすると、子供たちの達成感や、「喜んでもらえた」という喜びが大きくなります。

