【木村泰子の「学びは楽しい」#38】「無理しないで行くのが学校」です!

子どもたちが自分らしく生き生きと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載の38回目。今回は、新しい年度を迎えた今、教員の仕事の最上位の目的とは何かを改めて考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次
主語を子どもに、スイッチを切り替えよう!
2025年度がスタートしました。毎年この時期は新たな「ヒト モノ コト」などの出合いに期待と不安が入り混じった何とも言えない時期ですよね。私自身、学校現場を離れた今も、なぜかこの時期は、うきうき、そわそわ、ざわざわといった気持ちになってしまいます。
さて、今月のテーマ「無理しないで行くのが学校」をみなさんはどんなふうに受け止められますか。
学校に無理して行かなくてもいい、フリースクールや自宅でのオンライン授業でも出席にしてあげるなど、「無理してまで学校に行かなくていい」との言葉は、今や社会的に当たり前のように広められています。学校に行くことができなくて苦しんでいる子どもやおうちの人たち、フリースクールなどの関係の方がこのように言われるのは十分理解できます。しかし、公教育に携わる学校の教員や関係者が間違っても言ってはいけない言葉ではありませんか。
1年間で「不登校」の子どもの数が5万人も増加している現状です。このままパブリックのそれぞれの地域にある学校が変わらなければ、学校に通っている子どもの数のほうが少なくなるのではないかとの危機感さえ持つくらいの緊急事態です。みなさんはどう思われますか。
教員の仕事は子どもを教えること
教員の仕事は子どもを育てること
教員の仕事は子どもを失敗させないこと
教員の仕事は子どもに正解を教えること
教員の仕事は保護者に信頼されること
そのためには、完璧に教材研究をして、正しく間違えないで正解を教える授業を準備しなければならない。自分が受け持つ子どもには、決められたことができるように指導しなければならない。特に新年度の初めは、周りの教員たちの行動が気になり、遅れないように無理をしてまでもがんばらなくてはならないと焦ってしまうなんてことはないでしょうか。
もし、そうであるなら、今すぐスイッチを切り替えましょう。何度も書いてきましたが、学びの主語は子どもです。教員ではありません。
従前の学校は教員が主語でしたから、新年度のこの時期はこれでもかと準備をして、学級のルールをつくって子どもをひとまとめにして、「学級経営」という列車に乗せるのが4月のめあてでもあったように思います。こんなスペシャルティーチャーになることが教員の目標だったかもしれません。
しかし、今はどうでしょうか。社会のニーズは大きく変わっています。上記に書いたことと真逆の力が求められているのが教員の仕事なのです。教員の仕事の評価は、子どもの事実です。
子どもの事実に始まり子どもの事実に返す
1年間で529人の子どもが自死し(※1)、35万人もの子どもが地域のパブリックの学校に行っていない(※2)という子どもの事実を、私たちは突きつけられています。
これまでのように、学校のルールを守れない子どもを叱る。叱られた子どもは、学校が楽しいところではなくなり、行けなくなる。周りと違うことをすれば、「勝手なことをするな」「みんなと一緒のことができるようになりなさい」「みんなに迷惑がかかる」「『ふつう』のことくらいできないのか」と、毎日指導される。子どもが学校を楽しいと感じるはずがありません。
「不登校」のレッテルを貼られた子どものメッセージを共有します。
「ふつう」という呪いが全員を狂わせる
人は自分を知ることがなくなる
自分に何ができるのか
生きる価値が本当にあるのか
みんなにはできることが自分にはできない
できることはあたりまえ できて当然
できない自分はどうしたって劣っている
自分は仲間になれないと思う
誰も「ふつう」を知らないのに
「ふつう」に縛られている
この子どもの声にみなさんはどんな言葉を返しますか。
「先生たち 熱心な無理解者にならないでください!」
この言葉は、大空小が開校した1年目の秋に、一人の母親が私たち教職員に語った言葉です。この時までは、椅子に座れない子をいかに座らせるか、教室から飛び出す子をいかに教室に入れるかといったように、前段で書いたような仕事が教員の仕事だと思い込んで、誰もが必死で「この子のために」と指導していたのです。
一人の子どもとその母親が、学校という組織にどれだけ困らされ、苦しみ、母子で命を絶ってしまおうとまでした事実を知ったときの衝撃は今も忘れることはありません。
大空小はこの時からです。子どものことを分かったつもりになるな、子どものことは子どもに教えてもらわない限り、教員の仕事はできないと誰もが自分事に捉えたのです。ここから教員である自分を変え、「一人では無理! 大人のチーム力ですべての子どもの学習権を保障する」という「みんなの学校」づくりがスタートしたのです。
学校は無理しないで行くところです。
学校は誰にとっても楽しいところです。
あれもこれもやることが多すぎて……の声が聞こえてきそうですが、教員の仕事の最上位の目的は「その子がその子らしく育ち合う」環境をつくることです。
今の時期に、職員室のみんなで最上位の目的を果たすためには、まず「何をするか」「何を捨てるか」について、「無理なく」「楽しく」対話を重ねてくださいね。
※1 厚生労働省「小中高生の自殺者数の推移(2024年)」
※2 文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」(令和6年10月31日)
〇子どもの自死や不登校が増加の一途をたどる事実を前に、学校は「無理して行かなくてもいいところ」ではなく、「無理しないで行くところ」「誰にとっても楽しいところ」であることを確認しよう。
〇教員の仕事の最上位の目的は、その子がその子らしく育ち合う環境づくり。その目的を果たすために、「何をするか」「何を捨てるか」を職員室のみんなで対話を重ねよう。
【関連記事はコチラ】
【木村泰子の「学びは楽しい」#37】「未来の学校」をつくるために
【木村泰子の「学びは楽しい」#36】子どものことは子どもに教えてもらわないと分からない!
【木村泰子の「学びは楽しい」#35】「主体性」と「当事者性」を大切にした学びの場に!
※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。
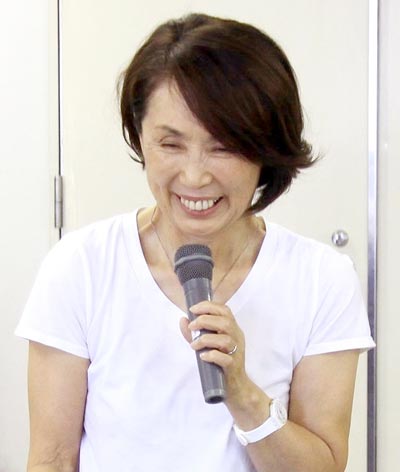
きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、全ての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。
【オンライン講座】子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり《全3回講座》(木村泰子先生✕堀智晴先生)参加申し込み受付中! 大空小学校時代の「同志」お二人によるスペシャルな対談企画です。詳しくは下記バナーをクリックしてご覧ください。

