小4算数「わり算」指導アイデア《2桁÷1桁の計算方法を考えよう》
執筆/福岡教育大学附属福岡小学校教諭・石橋大輔
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらいと評価規準
(本時1/11時)
本時のねらい
数量の関係に着目し、除数が1位数で被除数が2位数の場合の除法の計算のしかたを図などを基に筋道立てて考えることができる。
評価規準
10のまとまりに着目して、被除数の十の位の数を除数で割るなどの計算のしかたを考えることができる。(思考・判断・表現)
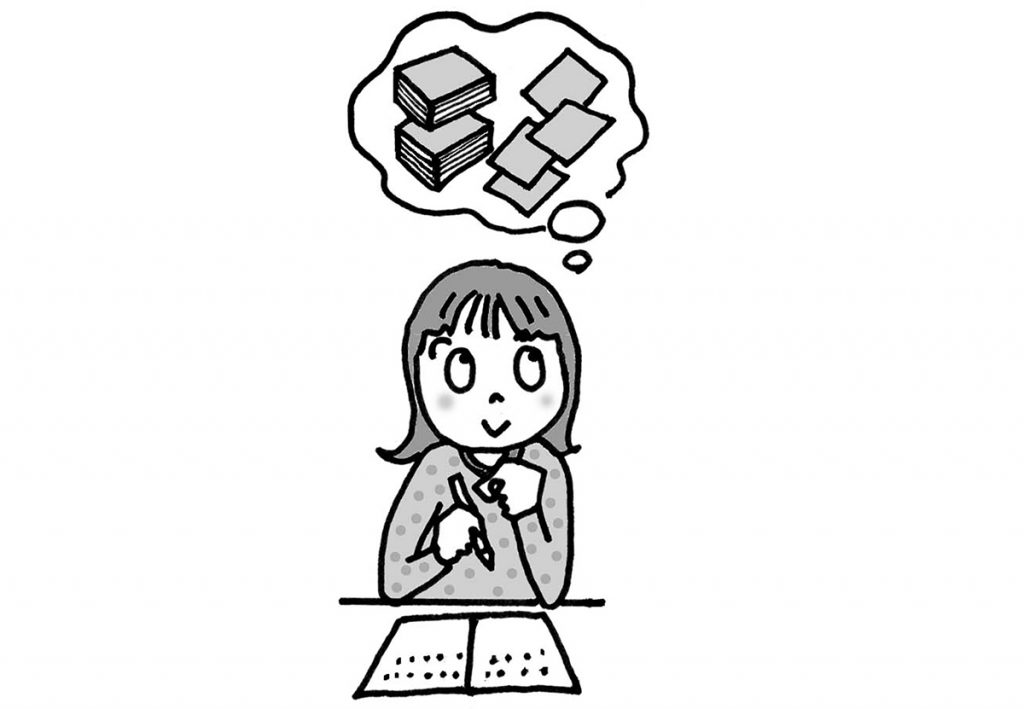
問題
72まいの色紙を、3人で同じ数ずつ分けます。1人分はなんまいになりますか。
式はどうなりそうですか。
72 ÷ 3 になると思います。
なぜ、わり算になるのですか。
3人で同じ数ずつ分けていくからです。
立式の根拠を説明できることはとても大切です。その際、文章の言葉だけを根拠にするのではなく、「同じ数ずつ分ける」というイメージを学級で共有しましょう。
学習のねらい
2けた÷1けたのわり算のしかたについて考えよう。
見通し
【答えの見通し】
20枚くらい
【方法の見通し】
・60 ÷3はできる。
・割られる数を分解する。
これまでの2けた÷1けたの計算と、どこが違いますか。
これまでは十の位と一の位に分けると、それぞれ割り切れて答えが見付かったけれど、今回は十の位が割り切れません。
十の位が割り切れないなら答えは見付からないのですか。
十の位が割り切れないときにどうするかを、この時間に考えてみればよいと思います。
見通しの段階では、答えを見積もったり、既習を基にして方法を見通したりします。教師が「今まで習った計算とどこが違うかな」と発問し、これまでとの違いを明確にするとともに、今まで習ったことに直す(帰着する)という思考へと方向付けていきます。
自力解決の様子
A つまずいている子
被除数をどのように分けて計算すればよいか分からずに、答えを見付けることができない。
B 素朴に解いている子
1人に10枚ずつ配るイメージ図などを基に、72を60と12に分け、24枚という答えを見付けている。
C ねらい通り解いている子
10のまとまりに着目し、7÷3を計算し、あまった1である10と2を合わせて12とするなどして、24枚という答えを見付けている。
学び合いの計画
イラスト/小沢ヨマ、横井智美
『教育技術 小三小四』2021年4/5月号より

