小6算数「資料の調べ方」指導アイデア《長縄跳びの並び方をデータ分析で最適化する》
執筆/神奈川県公立小学校教諭・八田安史
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥
目次
本時のねらいと評価規準
本時の位置 8/10 データの取り出し方に着目する
ねらい
データを基に合理的に判断して出した一応の結論に対して、批判的に捉えてデータの取り出し方を変えて考える。

評価規準
データの取り出し方に着目し、自分たちの目的に応じて合理的に判断し説明している。(数学的な考え方)
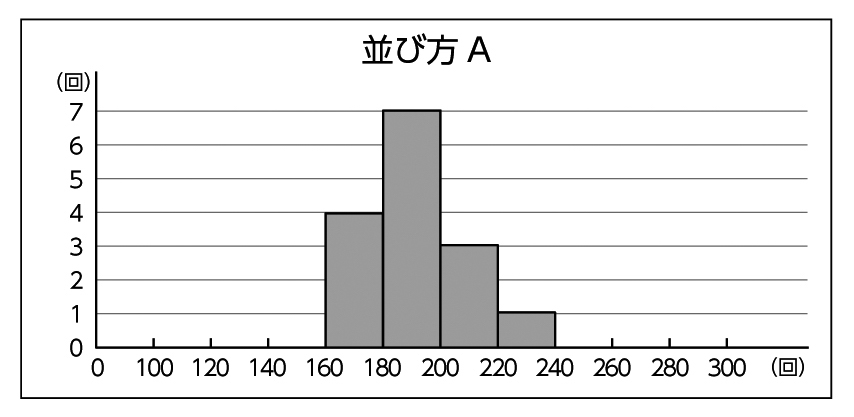
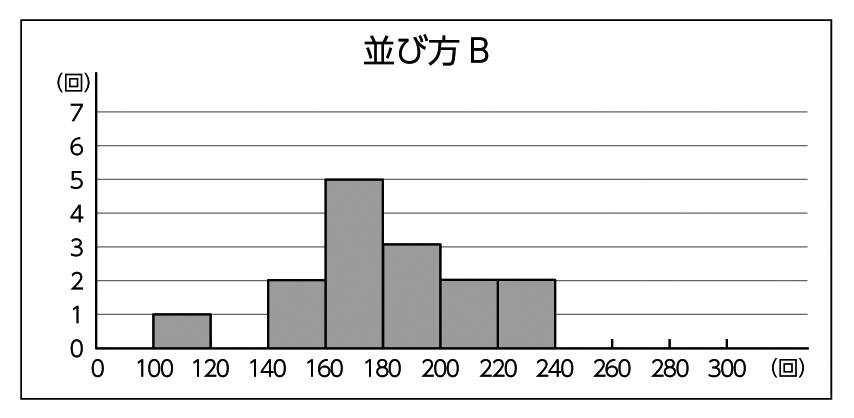
長縄跳びでより多くの回数を跳ぶために、跳ぶのが上手な人と苦手な人の並び方を3つ考えました。並び方の違いによる並び方A、B、Cでは、どれがより多く跳べるかを、データを基に判断しようと進めてきました。平均値が大きく差があるCを除き、AかBのどちらがよいか前回、収集したデータを基に分析し出した結論「Aの方がよい」に対して、「本当にこれでよいのか」という意見がありました。
確かにすべてのデータを取り上げたらAの方がよいけれど、はじめの方のデータは、今の自分たちには古いデータだからいらないと思います。
では、どのようにデータを取り出せばよいのでしょう。
問題場面
どのようにデータを取り出して分析すれば、より納得のいく結論を出せるかな。
本時の学習のねらい
より納得のいくデータの取り出し方を考えよう。
見通し
全部で15回のデータ。最近のデータをどのように見ればいいかな。
自力解決
A つまずいている子
「最後の1回だけ取り出せば、どちらがよいかわかるのではないかな?」
B 素朴に解いている子
「前半と後半に分けて考えたらどうかな?」
C ねらい通りに解いている子
「5回ずつに分けて、成長の具合を見てみたいな」
学び合いの計画
イラスト/横井智美
『教育技術 小五小六』 2020年1月号より

