小3算数「時こくと時間」指導アイデア《何時ころにお店に着きますか》
執筆/新潟県公立小学校教諭・樋浦教之
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、新潟県公立小学校校長・遠藤昇
目次
本時のねらいと評価規準
〔本時1/5時〕
ねらい
8時40分から30分後の時刻について、時間の量を数直線で可視化することを通して、加法や減法を用いて表すことができる。
評価規準
数直線を用いて、8時40分から30分後、9時50分から40分後の時刻を正しく求めることができる。
問題
明日の校外学習で行くパン屋さんとケーキ屋さんから、「何時ころにお店に着きますか」というしつ問がありました。2つのお店に着く時こくを調べて、教えましょう。
明日の校外学習で行くパン屋さんとケーキ屋さんから、何時ごろに着くか教えてほしいという連絡がありました。学校は8時40分に出発し、Aチームは最初にパン屋さん、Bチームはケーキ屋さんに行きます。
学校から最初に行く店まで『歩いてどれくらいの時間がかかるか』が分かれば、その時間を8時40分に足せばいいです。
パン屋さんまでは10分かかります。Aチームは何時に着くでしょうか。
8時40分に10分足すから8時50分です。
ケーキ屋さんまでは 30分かかります。Bチームは何時に着きますか。
40分に30分足すから70分。8時70分かな。
8時70分なんておかしいよ。『算数ボックスの時計』を使うと、 9時10分になったよ。
時計の模型を使って、9時10分になることを確かめましょう。
Bチームがケーキ屋さんに着く時刻は9時10分ですね。8時40分から30分後の時刻は、『算数ボックスの時計』を使わなければ求めることはできないのでしょうか。
Aチームみたいに、時計を使わずに時刻が求められるといいな。でも、どうやって求めるのかな。
学習のねらい
『算数ボックスの時計』を使わずに、Bチームがお店に着く時刻はどうすれば分かるかな。
見通し
『算数ボックスの時計』があれば、できそうですか。
できそうです。長い針を40分だけ動かせば、その時刻が分かるからです。でも、時計がないと40分動かしたとき、何時何分になるかがよく分かりません。
時計を自分で書けばいいと思うけど、書くのは大変そうだよ。
時計を書かなくても、40分増えたときの時刻が分かればいいんですね。どうすればいいですか。
時計を全部書くことは大変だけど、8時40分の周りだけ書けばいいんじゃないかな。
どうやって書きますか。
時計の形には書けないけど、横に目盛りを書けばいいと思います。
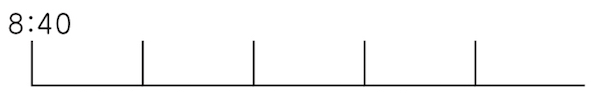
この数直線が出なかったときは、教師の側から提示してもかまいません。
これを使えば簡単にできそうだ。やってみよう!
自己解決
A つまずいている子
1目盛りが10分だということに気付いていない。答えの部分が8時44分になると思っている。
B 素朴に解いている子
1目盛りが10分を表していることに気付き、10分ずつ足している。9時10分だということが分かっている。
C ねらい通り解いている子
1目盛りが10分を表していることに気付いている。また、あと20分で9時になり、そこに10分足して時刻を求めている。
学び合い
イラスト/横井智美
『教育技術 小三小四』2019年5月号より

