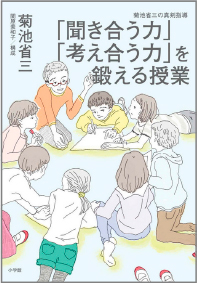<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」第2部・学校づくり編 #1 山形県小国町立小国小学校6年1組①

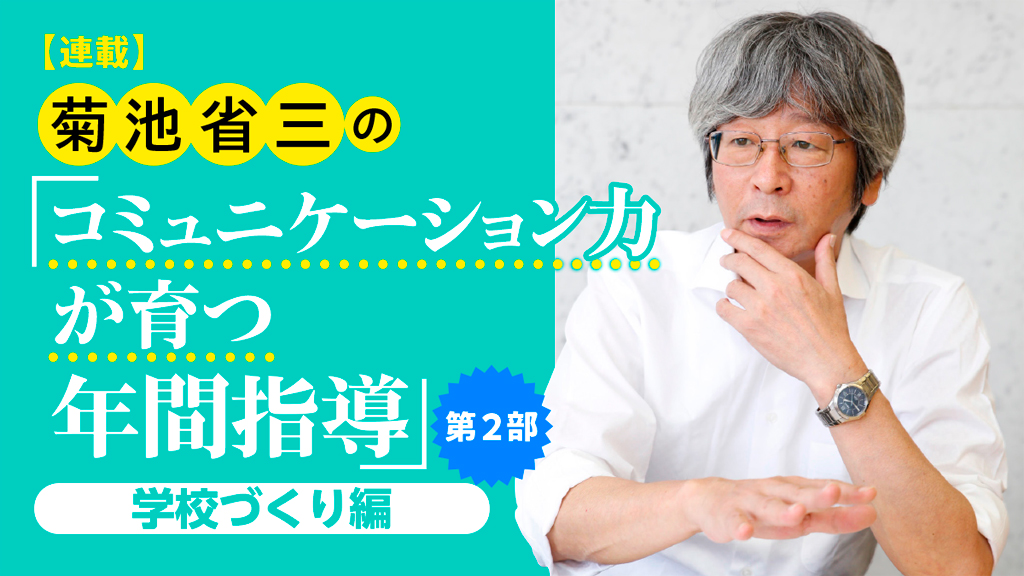
菊池実践を追試する学校の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載が、いよいよ第2部に突入。第2部では学級にとどまらず、学年、学校、地域を変えていくことを視野に入れた話し合いの授業を展開、レポートしていきます。第2部の実践者たちは以下の3名。第1回は、山形県の曽根原 隼先生の学級(6年生)における2025年6月の授業記録をお届けします。

目次
担任・曽根原 隼先生より、学級の現状報告
4年生から担任している子供たちですが、5年生進級時にクラス替えがあり、現学級は持ち上がりの2年目です。4年生で担任した当初は、大変元気のある子、授業中にほとんど発言できない子、教室から出てしまう子もいました。
そのため、聞く力、質問する力を育てたいと考え、4、5年生では対話・話し合いの授業を意識してきました。少しずつ友達同士のつながりが構築され、お互いに話を聞き合おうとする空気ができてきたことで、今では授業中に教室から出ていく子もいなくなり、全員が仲のよい学級になってきています。
そこで今年度は、次の3つのゴールイメージを持って取り組んでいます。
・子供たちが真剣に学ぶことができる、あたたかく、楽しく、厳しい学級
・子供たちが輪になり、認め合い、語り合い、高め合いなどの「あい」のあふれる学級
・互いにリーダーシップを発揮しながら成長させ合うことができる、「日本一」と誇れる学級
私自身、これまで学級経営の軸に価値語を置いてきましたが、今年度も、改めて価値語を大切に指導していこうと考えています。
昨年度より、もっと子供自身が成長を実感できるように、価値語と実体験を結びつけたいと思ったからです。
昨年度、価値語に取り組んだとき、その意味は理解できていたとしても、言葉と実体験の結びつきが弱かったのではないかと反省しました。そこで、今年度は価値語モデルをもう一度丁寧に実践していきながら子供たちの頑張りをほめ、実際の対話・話し合いの場面でも自信を持って取り組めるようにしていきたいと考えています。
菊池先生による授業レポート
3時間目、子供たちは「みんなが楽しめる『なかよし昼休み』にしよう」という論題で熟議を行った。まず、3つのチームに分かれて問題点を出し合った。
⚫︎1人で行動している人がいる
⚫︎ばらばらで活動している
⚫︎楽しめていない人がいる
の3つの問題点が出され、最も重要な1つを選ぶ熟議を行った。
まだ取り組み始めたばかりで熟議に慣れていないこともあり、チームでの話し合いがなかなかまとまらず、4時間目半ばまでかかった。
このように全員で取り組んだ熟議に続いて、菊池先生が授業を行った。
<熟議とは、○○○が○○○のことを話し合い、○○○がしあわせになれるように、何かを決めたり変えたりする>
菊池先生が黒板に書き、「○○○には同じ言葉が入ります。わかる人?」と尋ねると、1人の子が素早く手を挙げた。
菊池先生が、
「集中して見ているなあ」とつぶやきながら、板書されていた熟議の論題『みんなが楽しめる……』を指さすと、「あっ!」「わかった!」と次々と手が挙がった。
真っ先に挙手した子が、
「『みんな』です」と発表すると、大きな拍手が起こった。
「熟議は大人もやります。広いところで大人がやったとき、ある先生が入っていたグループがめちゃくちゃ盛り上がっていました。その先生が次のグループに行くと、今度はそのグループが盛り上がりました。なぜでしょう」
菊池先生の問いかけに、子供たちは首を傾げて考え込んだ。
「その先生は、ただ、一生懸命聞いていたそうです。後から、『本気になって聞いたら、人間は必ず話すんです』と言ったそうです」
納得した表情でうなずく子供たち。
菊池先生が板書を指さした。
<熟議のルール>
・最後まで聞く
・意見を肯定する
・黙らず発表
・決まったら実行
「聞く、話す、話し合って決める。周りのみんなが一生懸命聞いていたから、今日の熟議が盛り上がったんですね」
菊池先生が子供たちをほめ、みんなで大きな拍手をした。
![]()
熟議のルールとして、最初に「聞く」を示すことはとても重要です。
話し合いというと、「話す」ことが優先されがちですが、一番大切なのは「聞く」ことです。聞くことで、納得したり質問したり、子供たちのかけ合いが生まれてきます。
熟議の話し合いの中で、「なぜそう思ったの?」という質問には、反論の意味合いが含まれます。「なぜなら~~だから」という説明は、立証の意味合いをもちます。
「どうして?」→「なぜなら~」というかけ合いを繰り返すことで、熟議の話し合いは活発になっていくのです。
違う意見でも肯定する「傾聴」とは
「大人が熟議をする協会があります。その会では、盛り上がるポイントをアドバイスしているのですが、さっき、みんなの話し合いの中でもそれが見られました」と、菊池先生が、チームごとに書いて作った付箋を指さした。
「人間は、空白があると埋めたくなるのだそうです。矢印を書くと、その先を書きたくなるのだそうです。みんなの模造紙もそうだったね」
なんとなくわかった表情の子供たちに、
「さっき、みんなが決めたことに、さらに矢印を入れて、その先を書き込んでいきましょう。『例えば』と具体的な案を考えていこう。いいな、みんなで模造紙を埋めろ!」
キリッとした菊池先生の指示に、子供たちはさっと模造紙に向かった。
![]()
熟議のキモはかけ合いです。
ただ付箋を貼るのではなく、「あ、私も同じ意見」「それってどういうこと?」「なぜなら、こういうことだから」「それなら、こっちの意見とも重なるよね」「だったら、この意見はどう?」と話し合う。子供たちは付箋を貼りながら、意見をかけ合うことでお互いに触発されていきます。
そうしたかけ合いを通して、意見が広がり、新たな意見が生まれてきます。
教師は、こうしたかけ合いの意味を理解し、見取っていかなければなりません。
かけ合いができているチームを取り上げ、他のチームにもそのよさを広げていく橋渡しの役割も必要です。
菊池先生が発破をかけると、子供たちが一斉に席を立ち、意見を出し合った。カラーペンで書き込まれたアイデアで、模造紙がみるみるいっぱいになった。
矢印付けと書き込みの後、菊池先生が、
「このグループでは、『1年生はこうだったから』『去年もそうだったから』と、具体的な場面を出して話し合っていて、とてもよかったですね」とほめ、話を続けた。
「熟議では、自分と違う意見が出たときも、基本的には全て肯定します。『自分と違う意見でも肯定する』というのは、自分と考えた『意見』は違うけれど、相手がそう考えた『理由』は肯定しよう、ということなんです。
なぜ相手がそう考えたのかという理由に関するエピソードを聞く。Aさんは『1年生にはこうした方がいい。去年もそうだったから』という自分の経験をもとにエピソードを語っていました。エピソードを聞くことで、『だから、Aさんはそういう案を出したんだな』と思えるでしょう。
こうした聞き方を『傾聴』といいます。
一生懸命聞く『傾聴』は、エピソードを出し合って、自分と違う意見でも肯定的に捉える。そして、違う意見の中から一致する点を見つけていこうと考えることなんです。
『傾聴』ができるようになると、違う立場の人の背景・理由を聞いても、『いいね、いいね』と声をかけ合えるようになる。とても難しいけれど、きっとできるようになります。
友達の様子を見て、話を聞いて、友達の思いを想像する。大事な友達、仲間だから、みんなでいいものをつくっていく。みんなが幸せになる話し合いを大切にしていってほしいと思います」
子供たちは真剣な表情で、菊池先生の言葉を「傾聴」した。
菊池先生から曽根原先生へのメッセージ
話し合いのルールとして、
①書いたら発表
②相談したら発表
③聞いたら発表
これらをセットにして考えます。発表(相手に返す)があってこそ、話し「合い」なのです。
温かい人間関係を軸に話し合いをするのだから、相手の発言に対してリアクションをするのは当たり前のことです。教師もそこを意識して、言葉かけをしていく必要があります。
「最後まで聞く」
「意見を肯定する」
「黙らず発表」
「決まったら実行」
こうした熟議のグランドルールは、上記の①~③を促すものです。熟議に取り組み始めた頃は、グランドルールを何度も示しながら子供たちに徹底させていくことが重要です。
さらに大切なのが、熟議の話し合いそのものの振り返りです。
論題を出し、その解決方法を見つけて終わるのではなく、話し合いそのものの振り返りを行い、次につなげていく必要があります。
例えば、![]() のように、教師が子供たちのかけ合いの様子を見て、いいところを取り上げてほめる。似ている意見をまとめるとき、2つの意見の付箋を並べながら、相違点を出し合う。その結果を模造紙に書き込んでいく。ここが活発にならなければ、白熱した熟議にはなりません。自分の意見を丁寧に発表でき、その意見に対して的確に話し合えているかを教師が見ていき、子供たちに返していくことが重要です。話し合いの中身そのものを高めていくことで、子供たちの意欲はさらに高まり、白熱した話し合いへとつながっていくはずです。
のように、教師が子供たちのかけ合いの様子を見て、いいところを取り上げてほめる。似ている意見をまとめるとき、2つの意見の付箋を並べながら、相違点を出し合う。その結果を模造紙に書き込んでいく。ここが活発にならなければ、白熱した熟議にはなりません。自分の意見を丁寧に発表でき、その意見に対して的確に話し合えているかを教師が見ていき、子供たちに返していくことが重要です。話し合いの中身そのものを高めていくことで、子供たちの意欲はさらに高まり、白熱した話し合いへとつながっていくはずです。
熟議は、実生活に伴う内容を論題にします。子供は自分事として捉えることができるので、意見に自分らしさが出ますし、即興で意見を出すこともできます。一人ひとりの意見に意味があるのです。
熟議が終わった後の教師の講評では、子供たちへのねぎらいとよかったところ、改善点を示しましょう。単に「頑張ったね」で終わらせるのではなく、「こういうところがよかった。次はこんなところにも目を向けよう」と、子供たちのエピソードをもとに示していくと、子供たちもイメージしやすいでしょう。
特に重要なのが、「聞き合い」です。「よく聞く」とは、ただ黙って聞くことではありません。聞いているときのうなずきや表情、聞いた後のリアクションや感嘆の言葉、発表に対しての質問、ここまでを「聞くこと」のセットとして捉えましょう。能動的に聞くことこそが、「聞き合う」の第一歩です。
教師が、子供たちに優しく温かく関わっていくことはもちろん大切です。しかし、それだけでは子供たちはぬるま湯的な環境に浸ってしまいます。担任はメリハリをつけ、ときには「君たちはもっと上に行ける」と発破をかけ、厳しく子供たちに負荷を与えることも必要です。
負荷を与えるのは、子供たちの力を信じるからこそ。何より、教師自身が「絶対に成長させる」という責任を持つことです。その重み、覚悟を持ち続けてほしいと思います。
菊池省三先生による授業解説
「主体的・対話的で深い学びの実現」が提唱されているものの、こうした話し合いが行われている教室は多くはありません。“正解” に向けた “手段” の1つとして話し合いを行っているにすぎないのです。
対話・話し合いとは、考え続けること。みんなで意見を出し合い、最適な納得解を見つけていくことです。同じ論題で話し合ったとしても、学級によって結論が異なるのは当然のことです。
熟議やディベートは、こうした対話・話し合いの基礎になります。だからこそ、丁寧に指導していく必要があります。
熟議の論題は、自分たちの日常生活に即したものになります。
自分たちの学級をどう向上させるかに始まった熟議は、回数を重ねながら、学年、学校、さらには地域と論題の幅を広げ、ダイナミックな学びになっていきます。これが「熟議で学ぶ」ことであり、学びの社会化です。
対話・話し合いで学んだ力は、自分たちの学級を変えていくとともに、学年、学校、地域も変えていく可能性があります。熟議やディベートは、その第一歩になる学びだと考えると、ゴールイメージのその先も見えてくるのではないでしょうか。

菊池先生の最新刊、今までにない提案性を孕んで発売中!
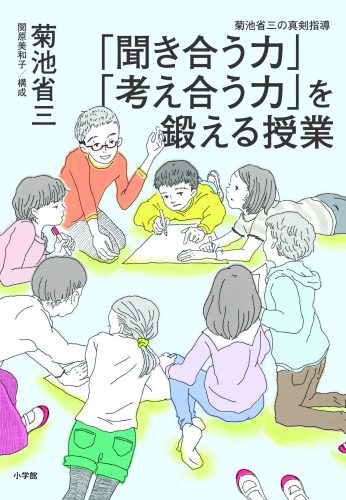
2025年3月22日のリアル対面セミナーの記録動画(有料)を公開中です!
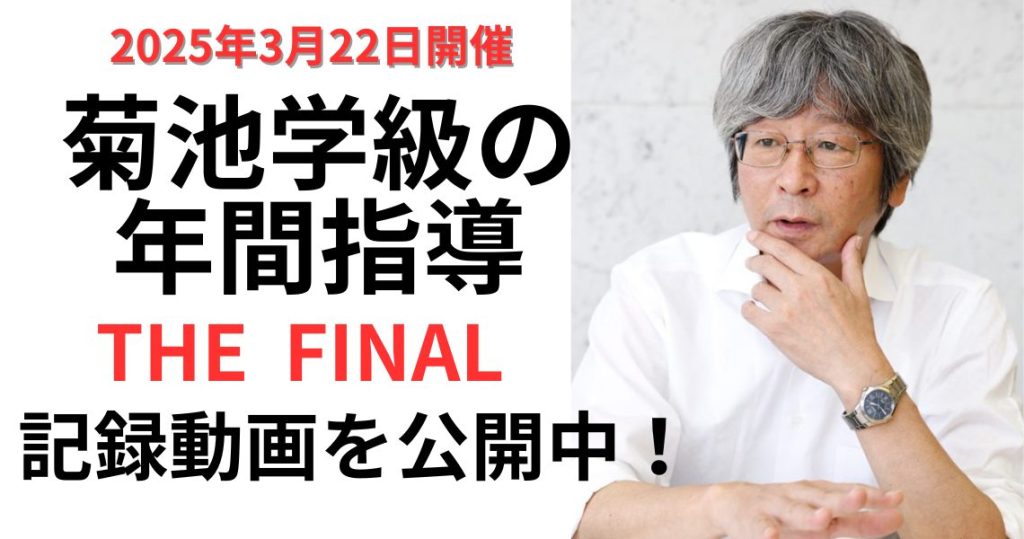
↓2025年3月発売の最新刊
「聞き合う力」「考え合う力」を鍛える授業
好評発売中です!
↓若手が菊池実践を学ぶために最適の単行本
「一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ」 発売中です!
取材・文/関原美和子

Profile
きくち・しょうぞう。1959年愛媛県生まれ。北九州市の小学校教諭として崩壊した学級を20数年で次々と立て直し、その実践が注目を集める。2012年にはNHK『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演、大反響を呼ぶ。教育実践サークル「菊池道場」主宰。『菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 生きる力がつく授業』(講談社)、『一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ コミュニケーション力を育てる指導ステップ』(小学館)他著書多数。