失敗しない!担任目線の「いじめの防止・対応」完全ガイド

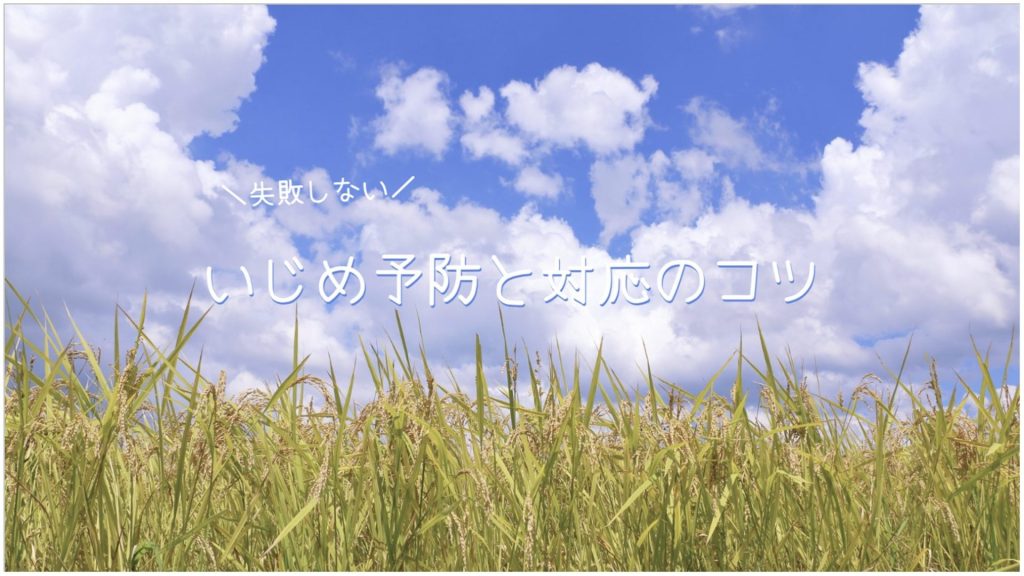
学級経営の中心的な課題となる「いじめ」。様々な行事が終わり、いったん落ち着く11月こそ、その対策に適したタイミングです。埼玉県公立小学校の紺野悟先生による完全ガイド、ここでは「いじめ」の定義を広く捉えることで小さな芽を摘み、いち早く対応していく方法を伝授します!
日常に見られる“対処すべき”事案の具体例、指導を考える上で重要な加害者の心理的背景別いじめのタイプ分析、いじめに発展させないための5つの効果的な予防法、担任が行う対応の7つのポイントと、今回も完全網羅でガイドします。加害者、被害者を問わず、子供たちを心の傷から守る基盤づくりを行いましょう!
執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟
目次
11月は「いじめ」を防ぐ学級づくりに適した時期です!
まもなく様々な行事がひと通り終わり、日常的な学校生活を送ることのできる時期になります。多くの学校で、9月から10月にかけて運動会、10月から11月にかけて音楽会があるのではないでしょうか。
これらが終わり、いったん落ち着く11月。12月の怒涛のように過ぎていく学期末までの合間の、ポッと時間が生まれる時期です。
そんな日常的な学校生活でこそ、メンテナンスと微調整に時間をかけましょう。
その一つが、今回のテーマである『いじめ』です。
いじめは放っておくと日常化します。
取り返しのつかない心の傷になります。
そうならないために、今、この落ち着いたタイミングこそ、中心的な課題を捉える必要があります。
どこからが「いじめ」なの?
どの先生も一度は聞いたことがあるでしょう。「いじめ」は明確に定義されています。
①いじめの定義
「いじめ防止対策推進法」には、「いじめ」は以下のように定義されています。
(定義)
文部科学省ホームページ 別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)より
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
つまり、次のように解釈されます。
- された側が「いじめ」と思ったらいじめです。
- どんなに小さなことでも、いじめです。
- いじめに大きいも小さいもありません。
- 学校内でも学校外でも、いじめです。
詳しくは、文部科学省のホームページをご覧ください。また、定義の変遷についての資料も掲載されています。
②これっていじめ?
では、次に挙げる例は、「いじめ」なのでしょうか。
- 長田君が瀬川君に「バカ!」って言った。瀬川君が泣いて訴えてきた。
- 「佐藤さんと野口さんににらまれた」と萩原さんが訴えているが、野口さんは否定している。
- 津田君に水をかけられて、カッとなった高山君は水をかけ返した。どちらも嫌だったが、教師には言わなかった。
- 毎回、“前へならえ”のときにツンツンされるのが嫌で、佐野君は中島さんに「やめろよ!」と怒鳴った。それを中島さんが「威嚇された」と訴えてきた。
- 本吉さんはノートを配るときに、投げるように置いてくる。私にだけじゃなくてみんなのを投げているけど、嫌だなって思って先生に相談した。
- 放課後、公園で田中さんに自転車を倒された。
ここで書いた一文では、全体像をつかむのに不十分ですが、どれも「いじめ」として扱う可能性がある事案です。
被害者が「いじめだ」「嫌だ」「悲しい」と感じたものは、すべて「いじめ」の行為と捉えるので、「お互い様でしょ」と思うこともあるのですが、スルーするわけにはいきません。
③いじめとトラブルとちょっかい
どの案件も教師は「いじめ」として捉えて対応する必要性はありますが、「いじめ」と言葉にする必要はありません。いじめなのか、トラブルなのか、ちょっかいなのかの境目はあいまいです。むしろどれとも捉えることができます。
ですので、「いじめか、いじめではないのか」ということにこだわらずに対処します。
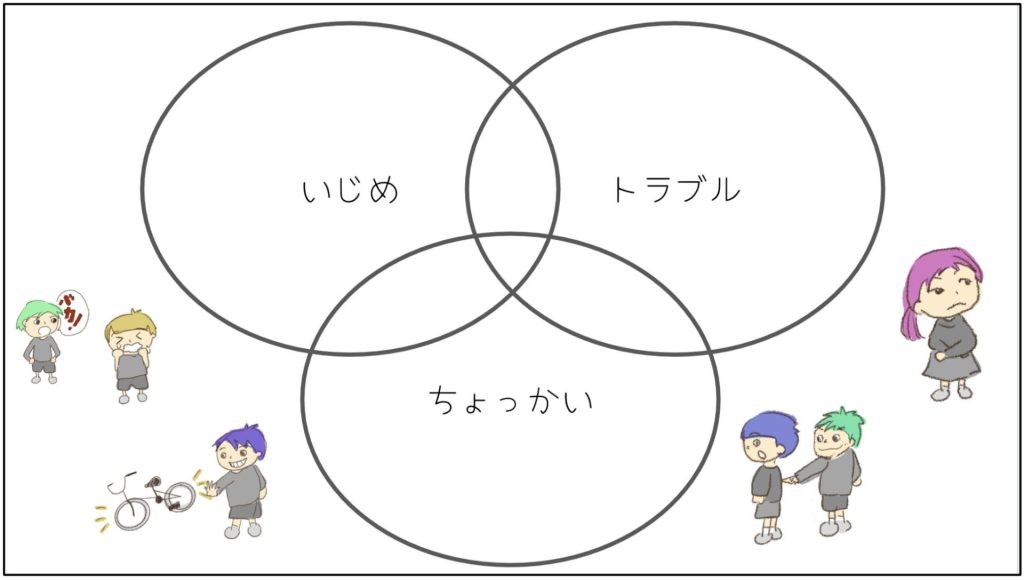
子供たちと出来事を話し合うときに大事なのは、いじめと認定するかどうかより、何がどのように起きて、どんな思いをしたかということです。
いじめ記録簿に掲載するかという業務上のいじめ認定はさておき、今目の前で起きている事案に対して話を聞くことを大切にします。
ここでは、すべて「いじめ」という言葉で話していきます。

