全国学力・学習状況調査【わかる!教育ニュース #77】
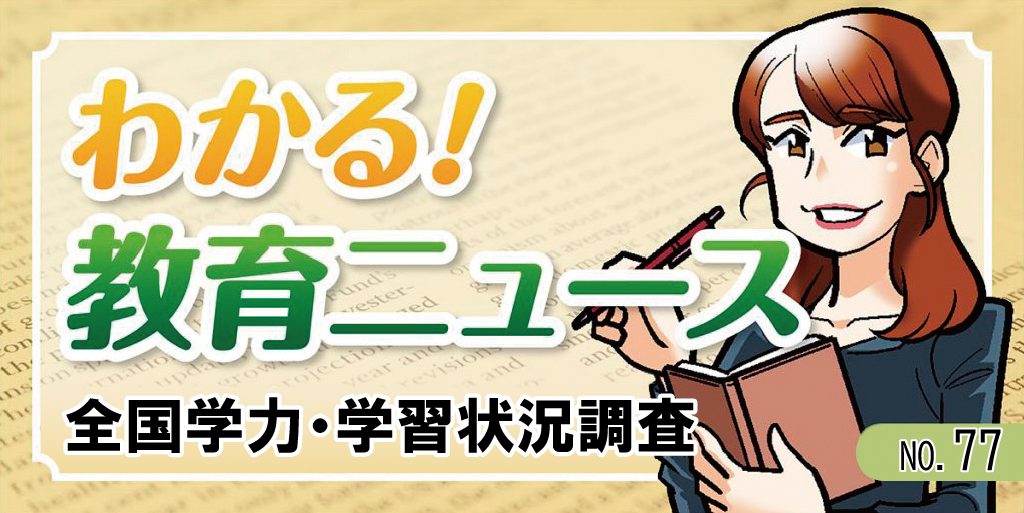
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第77回のテーマは「全国学力・学習状況調査」です。
目次
令和7年度全国学力・学習状況調査結果の都道府県別データを発表
子供の学力の変化を見る「経年変化分析調査」の結果で、家で本を読む環境が整っているかどうかが、生活習慣や学力の差につながっていることを以前取り上げました。でも、家庭環境の「格差」は乗り越えられないものなのでしょうか。
小6と中3を対象に4月に行った全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)は今回から全国平均正答率、全体の分析、都道府県別のデータの3回に分けて発表することになりました。このほど出た都道府県別のデータは、順位付けや過度な競争を避けるため、単に「成績」を比べるのではなく、地域ごとの特徴や課題に焦点を当てる形になっています(参照データ)。
まず、全国の平均正答率は、小6が国語67.0%、算数58.2%、3年ぶりに実施した理科が57.3%でした。中3は国語が54.6%ですが、数学は48.8%と5割を切りました。CBT方式を導入した理科は、国際的な学力調査で使う「IRT(項目反応理論)スコア」で算出。500点を基準に表しており、今回は505点でした。
都道府県ごとの正答率だけを見ると、上位層の顔ぶれは、秋田、富山、石川、福井など例年通り。ただ、今回の発表の形式を踏まえて注目するべきなのは、学力層の分布です。正答数で4つに分けた学力層ごとの割合を見ると、上位県は最も低い学力層の割合が少なく、学力の底上げが見られます。一方、下位県は低学力層の割合が多く、例えば、中3の数学では、最も低い学力層が全国平均を11.8ポイント上回った県もありました。

