「てびき」をキイワードに再発見する 伝説の教師 大村はまの国語授業づくり #2 「ぽっと始めてぷつんと終わる」作文を

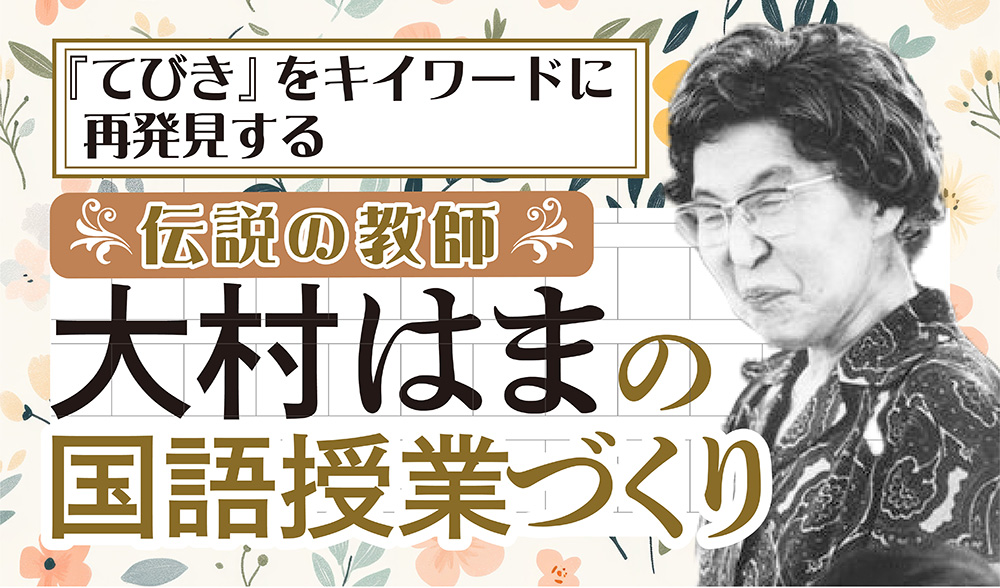
日本教育史上突出した実践を展開し、没後20年を経た今も伝説として語り継がれる国語教師、大村はま。現役時代の教え子であり、その逝去の二日前まで身近に寄り添った苅谷夏子さんが、今、改めて大村はまの国語授業づくりの「凄み」を語る連載です。
執筆/苅谷夏子(大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長)
目次
はじめに
大村はま国語教室の生徒として次から次へ懸命に単元学習に取り組んだ私が、一番素朴に思い出すあの教室の印象は、「困らされなかった」ということかもしれない。13歳の頃にそう思ったことをはっきり覚えている。
いつも頭をフル回転させて、驚くほどたくさんの資料を読んで、たくさん書き、グループの仲間と本気になって話し合った。そうやって取り組むプロジェクトはいつもとても新しかったので、簡単に予想できるそれらしい結論や、どこかのだれかがとっくに見出している答えなど探してもないことはわかっていた。目標も手法も中学生が容易に手の届くものではなかった。いつでも鉛筆を握る手に汗をかいていたような記憶がある。苦労も苦心もした。
けれども、そうした中でも、「いったい何をどうしたらいいんだろう」と呆然と困ることはなかったのだ。それは不思議なほどだった。結論や答えまで誘導されたというわけではない。いちいち細かく示されて、従順にただひたすら従って、付いていっただけだとしたら、きっとあんな達成感は得られなかった。大村教室では、自分の頭を懸命に使うその使い方の方向性や入り口のヒント、ステップの踏み方が、確かに、しかも魅力的に示されていたのだ。使ってみたいヒント、使えばいいことができそうな頼もしいステップがきっとあった。だから、苦労はしたが、困らなかった。苦労はしたが、自分の取り組みの成果を自分自身のものと思えて、うれしかった。
「自分の頭を懸命に使うその使い方」をちょうどよい加減に提示し、味わわせてくれたのが、大村はまの「てびき」だった。そのてびきの出し方のうまさを、当時の私たちは気づいていなかったが、生徒の状況や目標、取り組みの内容にふさわしい形で、実にうまく手を引いてくれていた。おせっかいを焼き過ぎず、私たちの思考の流れに寄り添いつつも、必ず一歩引き上げる力のあるてびき。これなくして単元学習は実らなかったのではないだろうか。
実は困っている子どもたち
この「困らされなかった」という印象が強かった理由の一つに、大村教室に出会うまで、特に国語という教科で私は「困らされていた」という事実がある。わりあい「できる子」であったけれども、実は結構困っていた。まずそもそも先生の求めることが本当にはよくわからないことがよくあった。ことばとしては理解できても、実際にどう考えればいいかはわからない。なんとかそれらしい答えにたどり着いても、これでいいのか、いけないのか、自分は本当にそう思っているのか、自信がなかった。多くの子どもは、教室で人知れず結構困っているのではないだろうか。
先日、たいへん熱心な先生の実践の話を伺う機会があった。読書生活を通じて子どもたちに自分自身の成長を振り返る機会を作りたいと願った実践だった。「てびき」は用意なさいましたか? と尋ねたところ、見せていただくことができた。それはたとえば「本を読んでいて疑問に思ったことを書きとめていこう」「疑問点を友だちと話し合ってみよう」というようなものだった。
本を読みながら、疑問に思ったことを拾いあげ、それについて友だちとも話し合ってみる、それは意味も価値もあるし、やった方がいいことに違いない。けれども、そう指示されても、はたと困る子どもがきっと多いのだ。子どもは、その種の指示をされたとき、なんとか従おうとがんばるだろうけれども、本当のところは、かなりあれこれ混乱している。「疑問って聞きたいことっていうこと? 誰かに答を聞くっていうこと?」「疑問って言われても、別に急には思いつかないのに」「読んでいて、そうか、そうなんだ、ってすんなりわかったから、疑問ていわれてもなあ」などと心の中でぼやく。「疑問なんていっぱいある。わからないことだらけだ。でも、いちいちそんなのを言っても始まらないでしょ」「自分の疑問は、別にわざわざ言うようなことでもない」などと当惑しているかもしれない。「疑問って、どういうことを言うのが一番いいの?」と「教室での良い答え」を探そうとしているかもしれない。
本当にはさほど疑問と思っていなくても、疑問文の形でどんどん「疑問」を作る子どもも少なくないのは、あちこちの教室を見て気づくことだ。結局のところ、「疑問」ということばの示す意味の広がりを前にして、目の焦点が合わないような感覚から抜け出せず、子どもは困るのではないだろうか。しっかりと考えようとする子どもほど、困るかもしれない。困った結果、もし「疑問」ということばを辞書で引いたとしても、その語義を目の前の材料に結びつけるのは容易ではない。
これは一例に過ぎないが、こんなふうに子どもは、さまざまなかたちで困っている。この例で言えば「疑問を持とう」という投げかけだけでは、子どもたちは十分に価値のある思考に移れるわけではない、ということだ。困らせないためには、その時々の頭の働かせる対象や方向に動き出すためのちょうどいいてびきが欲しい。
てびきは主体性や個性を損なうか
子どもの主体性や個性の発露をそっと見守ることをこれまで以上に重視する今の時代に、こうした「てびき」は批判を浴びる可能性が大きい。大村はま自身が、すでに現役時代に「子どもを型にはめる」という批判を受けていた。その際の大村の反論は、まず「子どもの個性というものは、てびきをしたくらいで萎んでしまったりゆがめられたりはしない。そんな脆弱なものではない」という「個性」への信頼と理解に裏打ちされたものだった。「主体性」は、放置することで確保されるとも思っていなかったし、さらに大村が重視したのは、「子どもは、いろいろな力を付ける途上にあり、自分に合った有用なてびきは、喜んで受け止める」という実感と認識だった。たとえばスポーツでも技術でも芸術でも、基本の動作や考え方、向き合い方をしっかりと自分のものにすることはどうしても必要で、それに異論はないだろう。習う側も文句はない。いい師匠を持つことは、たとえば釣りでも、たとえば絵でも野球でも、幸せなスタートを約束してくれるに違いない。なぜ、ことば(特に母語)を育てる教育に関わると、突然おとなは及び腰になるのか。「惜しみなく教えよう」と大村はまは言う。その教え方が子どもたちにふさわしく、無理のないもので、確かな成長につながるものであるならば、だれに遠慮のいるものか。そういう覚悟で、大村はすべての取り組みに「てびき」を添わせた。
大村自作の「てびき」に注目しながら、今回は前回の続きで、もう一度「話す」に注目したい。
第一回の後半に添えた「夏休みのスピーチ」の「話し出しのてびき」をヒントになさった方、使ってみた方はあっただろうか。子どもたちのスピーチに新鮮な風が送り込まれたという手ごたえはあっただろうか。
「いきいきと話す」
教室で交わされる話しことばがいきいきとしたものであってほしい、というのは誰もが願うことだろう。精彩のない、つまらなさそうな、力の入っていないことばが子どもの口から出るのを聞くのは辛いことだ。けれども、だからといって「いきいきと話しなさい」「もっと大きな声で、元気に、はきはきと」「楽しく話そう」と指示したからと言って、それが叶うわけではない。そんな指示をしたら、さらにことばは萎縮する。先生がどれだけ「いきいきと話させたい」と願っていたとしても、ダイレクトにそう指示すればすんなり叶うほど、人と言語の関係は単純なものではない。カラ元気や不自然な調子を生んで終わりではないだろうか。生き生きと話す「演技」を習うのが目的ではない。そういう見極めをぴしりとしていたのが、大村はまの偉いところだ。「つまらない話をいきいきと話すなどという芸当は、子どもにはできません」というようないい方をしている。
たとえば、自分の話が、みんなもとっくに知っている二番煎じでしかないとか、たいして面白くも珍しくもない、平凡きわまりない話でしかない、などと自分でもわかっているとき、あるいは心から思っていることでもわかっていることでなく、自信のない話をするしかないとき、大人であっても「いきいきと」話すことなどできないに違いない。そういうものだ。頑張って声を張ってもどこかぎこちないことは、自分が一番わかる。そんな経験はちっともプラスには働かず、聞き手にも印象を残さない。
そういうときにこそ「てびき」が力を発することになる。まずはなんとかうまく伝えたいと心から思えるような内容をしっかりともつ、その助けをすること。そうした自然なエネルギーを糧に構成や表現を工夫して引き立つ話にしようとすること。それが話し手の「いきいき」を生み出すし、いきいきとした話を人の前でする味わい・手ごたえを覚えることになる。

「はじめ、中、終わり」は助けになっているか
構成の工夫としてよく目にするのは、「はじめ、中、おわり」という指導だ。これは、大村はまの作文指導や話しことばの指導とはたいへん異なる。大村は中学校の教室で、「ぽっと始めてぷつんと終わる」というスタイルを勧めた。半世紀以上も作文指導に心を砕いた国語教師の勧めとしてこれは注目に値する。大村はある時点で、「作文がいいものになるかどうか、書き出しでわかるようになった」という。それ以降は、書き出しで失敗している子どもには、うまくそこでストップをかけて、改めて別の方向から書き出すように手を貸した。うまくいかないとわかっているものを黙ってやらせておいても誰のためにもならない、という考えだった。
ここで大村の言う「失敗する書き出し・話し出し」というのは、平凡な型にそってとりあえずのことばを並べ、自分を早々と枠にはめてしまっている姿だ。明確に「これ」という内容に行き当らないまま始めてしまった勢いのない切り出し、あるいは、緊張感のない予告を繰り出してしまったせいで張りや広がりが失われたスタート。そういう冒頭部が、本人も気づかぬうちに全体の流れに影響してしまい、盛り返すことはどんどん難しくなる。
小学生だけでなく、中学生であっても、短い作文やスピーチに前置きもまとめもいらない、一番伝えたいことをよく考えた入口からすぱっと切りこんでいく、伝えたいことを十分に伝えたら、まとめなどいらないからそこでぷつんと終わりにする、それが大村の指導だった。
私は二十年ほども、ハガキ作文コンクールの審査員というのを務めている。小中学生が応募するこのコンクールの作品を見ていても、学校で指導されている「はじめ、中、終わり」が子どもにしみ込んでいることが実感されるが、それが一枚のハガキで表現する作文をいいものにしていると感じられることは少ない。それでなくても小さなハガキという媒体なのだから、前置きやまとめをする余地などほとんどなくて、ずばっと最も書きたいことを書けばいい。書き終わったら、そこで終わりにすればいい。はがきという媒体にはそれが似合うはずだし、賞をもらうような作品はやはりそういうスタイルになっている。
もともと「はじめ、中、終わり」というのは構成意識を促すものであり、説明文やレポートなどのスタイルとしては一定の意味を持つ。けれども子どもの作文指導という範囲では、実態としては、「さほど必要でもなく、魅力もない前置き」と、「わざわざ平凡なことばでまとめてくれなくても十分にわかっているのに、付け加えられた蛇足的なまとめ」という悲しいことになっている場合が多い。これは残念なことではないだろうか。
これしかないと選ばれた内容でずばりと話の核心に切り込んでいく、その手ごたえを味わわせるために、大村はまが作ったてびきの実際を見てみよう。読んだ本をクラスメイトにすすめるスピーチのためのてびきだ。
<友だちに本をすすめる「話しだし」のてびき>
ア、私のご紹介する本は、――です。この本のなかに、私のたいへん好きな場面があるんですが、それは――。
イ、この本のなかに、わたしのたいへん好きな人物が出てきます。それは――
ウ、この本を読んで、私は、ひとつの疑問をもちました。
エ、この本を読んで、私は前から疑問に思っていたことが、一つ解決されたような気がしました。
オ、この本を読んでいると、ときどき、思わず笑いだしてしまいます。
カ、この本を読みながら、いくたびか、本から目をはなして考えさせられました。
キ、皆さん、――のことを知りたいと思いませんか。
ク、皆さん、――は、どうしたらいいと思いますか。
ケ、――は、小さいとき、どんな子どもだったと思いますか。
コ、――は、どんなところだと思っていますか。
サ、――のようすを読んでみたいと思いませんか。
シ、この本を読みながら、私は、しばらく楽しい空想にひたりました。
ス、なんとなく読みはじめたこの本から、私はじつに多くのものを得ました。
セ、正直者が損をするといいますが、損するどころか、たいそうしあわせになったというお話です。
ソ、この本のなかに、こういうところがあります。(一節を朗読する)
× どんな本を紹介しようかと迷いましたが・・・
大村教室では読書はたいへん大事にされ、一人ひとりが「読書生活の記録」を書きとめながら幅広い本の世界に向き合っていた。その冊子には、「読んだ本」だけでなく、「読みたい本」「読書日記」「本で出合った印象的なことば」「読書について考える」「書評」「読書についての情報」「新刊書の広告の切り抜き」などが蓄積されていった。「友だちに本をすすめる」というスピーチの取り組みをすることになったとき、そうした普段からの読書生活指導の積み重ねが重要な背景になっていたはずだ。そうした背景抜きに突然「読んだ本を友だちにすすめよう」と言っても、豊かな単元にはなりづらかっただろう。
生徒たちは、自分の記録をたどったりもしながら、あれこれと迷いつつ、それぞれ「よし、この一冊にしよう」と決めるプロセスがあったはずだ。クラスの仲間に向かって一冊の本をすすめるということは、自分の読書経験だけでなく個性や好み・趣味・センス、価値観を打ち出すことであるから、子どもにとっては重要な選択であるだろう。おそらく大村はゆるやかにその活動の豊かさや意味合いを示しながら、生徒たちがどういう腹案を持ち、どういう決定に至ったかを見取っていたに違いない。
その上で大村が書いたのが、上記の「話し出しのてびき」だ。生徒の人数分の本を念頭に置きながら、あの本ならこういう切り口で、あの子ならこういう目の付け所で、こういう方向で、たとえば思い切ってここを取り出して、とさまざまな案が示されている。生徒の選んだ本が多様であれば、案も多様になるのが当然ともいえる。その多様性は、そこにあるはずのものであっても、子どもたちに任せておけば自然にあふれ出てくるものではないだろう。多様性を発露し形にするすべ、それ自体を学ぼうとしているのが子どもだ。それをただ自由にと言われても、子どもは困る。
「てびき」を使う側の気持ち
私が生徒だった時の大村教室を思い出すと、てびきの“ソ”の「この本の中にこういうところがあります」といって、一節の朗読を始めるなどというのは、かっこいいし、きっと人気があって、誰かがやったに違いないと思う。その一節を一冊の中からどう選ぶか、そこが自分らしさの発露となるし、その本への愛着の結晶にもなる。かといって、クラスであの人もこの人もこれを選びそうだとなったら、ちょっと新鮮さも落ちてくることになる。それとなく情報交換をしながら、方向修正をしたり、このてびきにはない新たな切り出し方を探したりすることになるだろう。ここには15の話し出しの例が並んでいるが、それを順々に読んでいくうちに、どこかで、自分に響くものに出会えば、そこから派生する新たな、自分と自分の選んだ本だけにぴたりとはまる何かを思いついたりする。大村は、静かに教室を回りながらその様子を見取って、もし必要であれば一対一で生徒と対話し、個人的なてびきをすることもあったはずだ。この個人的に渡されるてびきは、さらに的を外さなかった。
こうしたてびきを見てもわかるように、本のあらすじを伝えるという最も「普通」なやり方は静かに封印されている。自分がその本に惹かれたことを伝えるのに、あらすじを言っても始まらない、というのは、本というものと本気で向き合ったときに出てくる自然な認識だろう。「何がどうなって、結局こうなった」というようなことを述べても、その本の魅力を伝えることには全くならない。読んでみよう! と思ってもらうには、自分自身にとってのその本の魅力のありかをしっかり見きわめ、形にすることなのだ。その誘いが、このてびきには示されている。
一人一人が本を読むということを大事にする教室のあり方が、感じられるのではないだろうか。こういうスピーチの会ができるなら、どれほど読書コミュニティが活性化されることだろう。読書量に皆が一目置いているAさんはどんなふうにどんな本を紹介するか、独自の趣味を持つBさんは何を語ってくれるか、いつも予想を超えるものを出してくるCさんは今回はどんなものを見せてくれるか、あの優しいDさんはどんな本を選んだのか……。本の世界を舞台に、クラスが豊かな結びつきを強めるのではないだろうか。そして、どれだけ苦心はしても困ることはなく、話されることばは自然な勢いを帯び、いきいきとするのではないだろうか。

<大村はま略歴>
おおむら・はま。1906(明治39)年横浜市生まれ。東京女子大学卒業後、長野県諏訪市の諏訪高等女学校に赴任。その後、東京府立第八高等女学校へと転任。すぐれた生徒たちを育てるが、戦中、慰問袋や千人針を指導、学校が工場になる事態まで経験する。
敗戦後、新制中学校への転任を決め、後に国語単元学習と呼ばれるようになった実践を展開。古新聞の記事を切り抜いて、その一枚一枚に生徒への課題や誘いのことばを書き込み、100枚ほども用意し、駆け回る生徒を羽交い締めにして捕まえては、一枚ずつ渡していったと言う。1979(昭和54)年に教職を去るまで、単元計画をたて、ふさわしい教材を用意し、こどもの目をはっと開かせる「てびき」を用意して、ひたすらに教えつづけた。退職後も、90歳を超えるまで、新しい単元を創りつづけ、教える人は、常に学ぶ人でなければならない、ということを自ら貫いた。著書多数。
2005年、98歳10ヶ月で他界。その前日まで推敲を進めていた詩に、「優劣のかなたに」がある。
<筆者略歴>
かりや・なつこ。1956年東京生まれ。大田区立石川台中学校で、単元学習で知られる国語教師・大村はまに学ぶ。大村の晩年には傍らでその仕事を手伝い、その没後も、大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長として、大村はまの仕事に学び、継承しようとする活動に携わっている。東京大学国文科卒。生きものと人の暮らしを描くノンフィクション作家でもある。
主な著書に『評伝大村はま』(小学館)『大村はま 優劣のかなたに』『ことばの教育を問い直す』(鳥飼玖美子、苅谷剛彦との共著)『フクロウが来た』(筑摩書房)『タカシ 大丈夫な猫』(岩波書房)等。
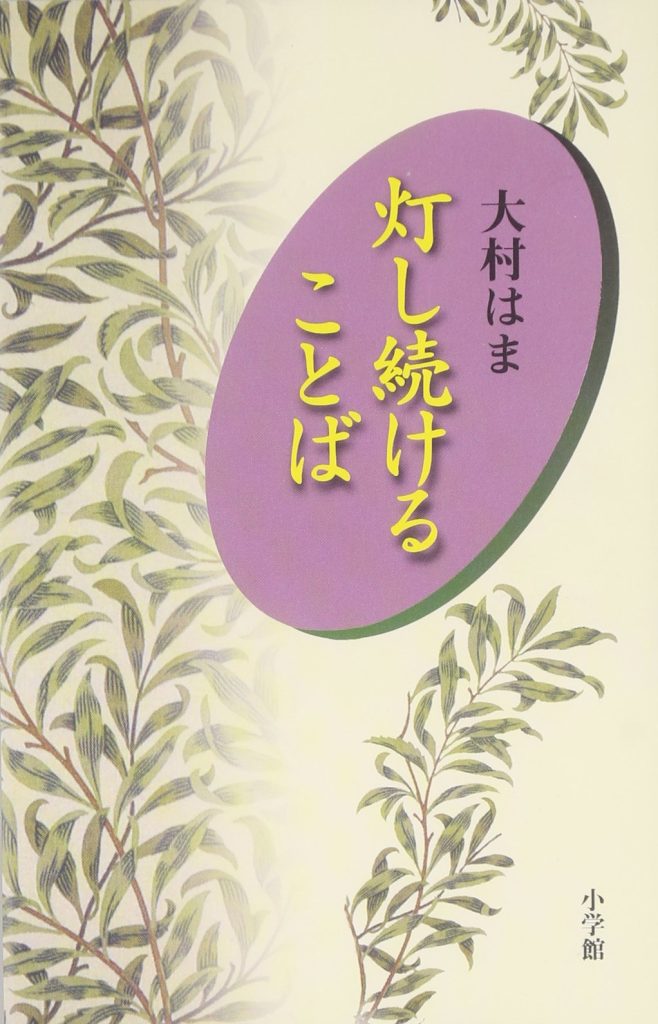
ロングセラー決定版!
灯し続けることば
著/大村はま
「国語教育の神様」とまで言われた国語教師・大村はまの著作・執筆から選びだした珠玉のことば52本と、その周辺。自らを律しつつ、人を育てることに人生を賭けてきた大村はまの神髄がここに凝縮されています。子どもにかかわるすべての大人、仕事に携わるすべての職業人に、折に触れてページを開いて読んでほしい一冊です。(新書版/164頁)
大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。

