学びを深め多様な考えを促す「発表の指導」のポイント【学ぶ意欲と力を育てる 学習指導の極意③】

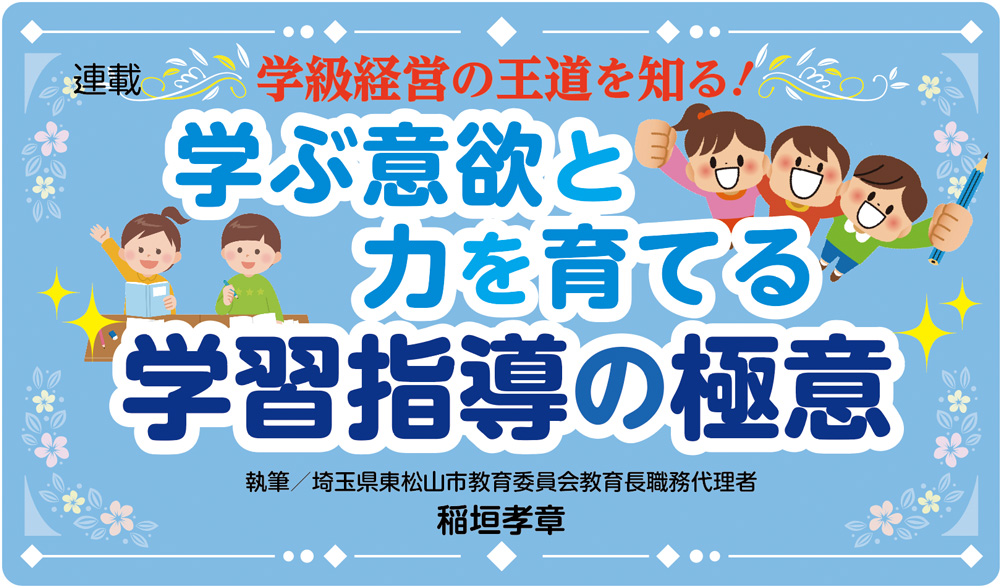
子供たちの学ぶ意欲と力を育てるためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて、学習指導の基礎基本を解説します。第3回は、発表の指導について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
「発表の指導」は、効果的な授業を展開していく上で大切な視点です。子供たちがどのような発表の仕方をしているかを見ると、教師の指導理念や指導方法が分かるものです。「発表の指導」は、まさに教師の授業展開上、そして学級経営上、とても重要な指導事項です。そこで、適切な発表の指導をするにあたって、次の3つのキーワード「主語を付けた発表」「根拠を明確にした発表」「他の意見と関連した発表」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 主語を付けた発表
教師の「答えが分かる人?」との発問に「25です」とだけ答える子供の発言では、授業の学びは深まりません。このように主語を付けないで答えだけを発表する授業を観ることがあります。
大切なのは、「私は、25だと思います。そのわけは~」という「主語を付け、根拠を明確にした発表」を目指すことです。主語を付けて発表することは、他の意見との関連発言を促すきっかけになります。まずは、1年生から主語を付けて発表できるように指導していきましょう。
関連発言のきっかけとなるよう指導します

「私は、~と思います」と主語を付けて発表する指導を行います。このことによって、前に同じような発表をした子供がいれば、「私もAさんと同じように~と思います」と発表することができます。このような発表をするためには、他の意見をよく聞いていないと「私もAさんと同じように」と発表することはできません。
「友達の話をよく聞きましょう。それが自分のためになります」「自分の考えを発表しましょう。それがみんなのためになります」などの言葉をつかって指導し、主語を付けて発表することの大切さを再確認していきましょう。
CHECK② 根拠を明確にした発表
前記の「25です」という答えでは、その子供はどのようにしてその答えを導いたのか分かりません。まずは、その子なりの言葉で、答えを導いた根拠となる理由を発表できるように指導します。このことにより、他の子供たちの学びを広げ、学びを深めることの端緒となります。低学年のうちから、可能な限り根拠となる理由を発表できるように指導していきましょう。
考えの根拠となる理由を発表できるように指導します
例えば、「それは~このような表を使うと10と15になり合わせて25になったからです」という発表の仕方です。導いた答えの根拠を知ることで、他の子供は自分の考え方との相違点を見いだすことができます。
仮に、発表した答えが誤っていても、考え方を理解することで、みんなでやり直して正解を見付けていくことが可能となり、学びが広がり、深まることに直結します。根拠となる理由を発表できるように、根気強く指導していきましょう。

