GW明けにも間に合う! 給食・掃除システムづくり完全ガイド

新学期が始まって1か月。学級生活も軌道に乗りはじめ、イベントシーズン到来前のゴールデンウィーク明けが見直しのチャンスと、埼玉県公立小学校の紺野悟先生が学級システムをより意義あるものに再構築する手順を伝授します。システム化することの効果を確認し、学級経営の安定につながる「より機能するシステム」へと微調整していきます。「面倒な当番」ではなく、子供たちがメリットを感じ、感謝や自己有用感につながる「学級全体で取り組むシステム」へと、このタイミングでブラッシュアップしていきましょう!
執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟

目次
「学級が回る」システムの条件
新学期が始まって、1か月がたちました。1日くらいなら担任が何も言わなくても、「学級が回る」のではないでしょうか。「学級が回る」とは、スムーズに教室が運営されているという意味です。
そこには必ず、いくつかのシステムが存在します。電車の改札を人がスムーズに通れたり、時間になったら走ってくる人を待たずに電車が出発したりするように、スムーズな運営のためには、システムが不可欠です。
「学級が回る」ようなシステムにするためには、次のような条件があると考えられます。
① 負担が偏っていない。
② 分担に平等性があり、自分の仕事に納得している。
③ 各自が自分の役割を理解して取り組んでいる。
④ 忘れていることに寛容で、支援ができる。
⑤ 初動が早い。
⑥ 場合によっては、楽しみよりも仕事を優先することもできる。
みなさんの担任する学級はいかがでしょうか。
さて、本記事では、『GW明けにも間に合う! 学級システムづくりの手順』をテーマに、4月からつくり上げてきた学級のシステムを見直す視点と、つくり上げるときに気を付けることをまとめました。ゴールデンウィーク明けに、それぞれの学級でより機能する学級システムとなるよう、微調整するきっかけとなれば幸いです。
適切な学級システムとは
まずは、システムとはどんなものなのか整理しましょう。システムとは、多くの物事の一連の働きを秩序立てた『全体的なまとまり』のことです。業務の効率化、従業員の勤怠管理、顧客情報の管理、 課題の解決のためにつくられます。
学級に置き換えてみると、学級が1日の授業、休み時間、給食、掃除などの活動が運営されていけるような仕組みのことであり、それらをつくることを学級システムづくりと言うことができます。
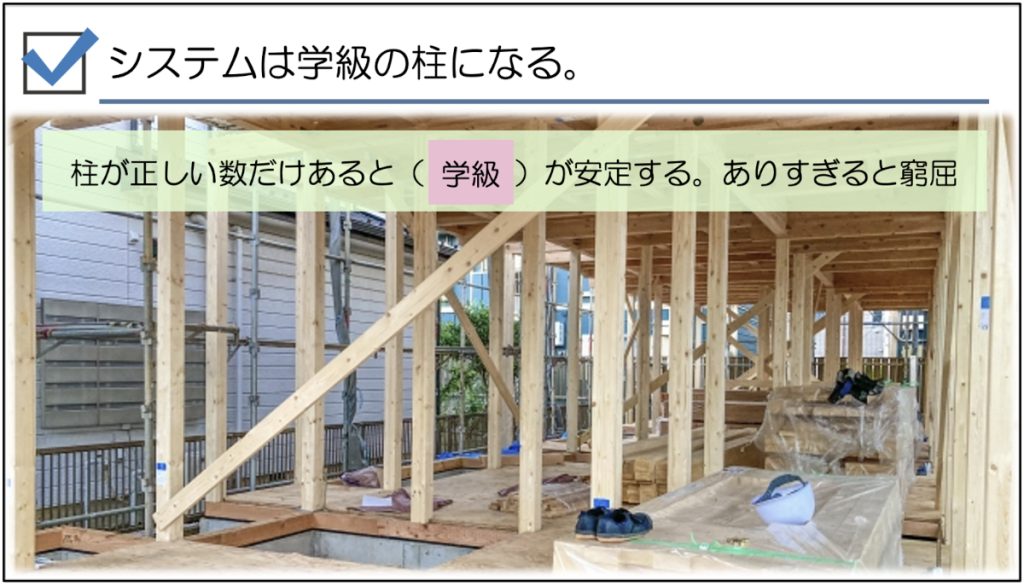
システムは、例えるならば、学級の柱のような存在です。学級を安定させるためには、役割が分担され、仕事内容が明確で、流れるように遂行されていくようなシステムであれば、より機能度が高く、運営上安定していると言えます。
例えば、日直当番は「名前順に1日交代」とシステムが設定されているとします。そうすると、毎日「今日は誰がやる?」というやり取りが不要になります。平等に役割が配分されていて、順に回ってくるというシステムができあがります。これに、欠席の場合はどうするか、仕事内容は何かを定めることで、より安定的に運営がなされていきます。
このようなシステムが教室の中には多数存在し、1日の生活がつくられていきます。しかし、上の図のように、家づくりの柱で例えると、柱がありすぎると窮屈な部屋ができあがるように、学級生活も(設定が細かすぎれば)システムで動かされているだけになってしまいます。工夫の余地も、支え合う温かさも不要で、ドライで永遠に同じペースで動き続けるエスカレーターのような単調な学級になってしまうことでしょう。そこで、適度に適切なシステムづくりが求められます。
学級システムは学級の安定のために必要ですが、システムだらけでは面白みのない淡泊な学級になってしまいます。

