雨の日でも盛り上がろう!絆を深める厳選アクテビティ「しりとり2選」|俵原流!子供を笑顔にする学級づくり #3


子供の笑顔を育てる「笑育」という実践のもと、安全で明るい学校、学級をつくってきた俵原正仁先生。これまで培ってきた学級づくりのアイデアやメソッドを、ユーモアを交えつつ、新任の先生にも分かりやすく解説します。月1回公開。第3回は、梅雨の時期に重宝するアクティビティ2選を紹介します。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
雨の日でも遊べるアクティビティで学級崩壊を予防しよう
6月は、1年の中でも学級崩壊が起こりやすい月と言われています。ただ、突然、学級が崩れるということはありません。その前に何かしらの兆候が必ず表れます。いわゆる「崩壊フラグ」です。
その1つに、「友達への配慮がなくなる」というものがあります。ただでさえ、6月は雨が多く外で遊ぶことができません。子供たちもストレスがたまり、友達への配慮もなくなりがちです。
そこで、今回は、雨の日でも楽しめて、さらに、「友達同士の関わり合いを増やす」こともできる「しりとり遊び」を2つ紹介します。ぜひ、お試しください。
アクティビティ1:隣の子との絆を深める「ゴリラをバナナに」
1つ目は、教室で一番近くにいる隣の子との絆を深める「しりとり遊び」です。
紅林くん!
はい。
いきなりの指名に戸惑いながらも、ノリのいい紅林くんは、元気な返事を返してくれました。声かけはさらに続きます。
ゴ・リ・ラ
人は、突然、「ゴ・リ・ラ」と話しかけられると、脊髄反射的に次の言葉を口にします。
ラッパ
素晴らしい。拍手!
教師の勢いにつられて、子供たちも拍手します。紅林くんもなんだか嬉しそうです。
「ゴリラ」とくれば、当然、次は「ラッパ」ですよね。このようにしりとりをして、今から「ゴリラ」を「バナナ」にしてもらいます。題して「ゴリラをバナナに」。拍手!
「いぇ~~~い!
拍手と共に、ほめられて気分のいい紅林くんを中心に声援もあがります。
ただし、1人で「ゴリラ」を「バナナ」にするのではありません。隣の人とペアを組んでください。二人でかわりばんこにノートに書いていきます。思い付かない場合は相談してもかまいません。クリアできたら、手を挙げて教えてください。では、用意スタート!
スタートのかけ声で、子供たちはいっせいに取り掛かります。
ゴリラ→ラッパ→パイナップル→ルンバ→バナナ
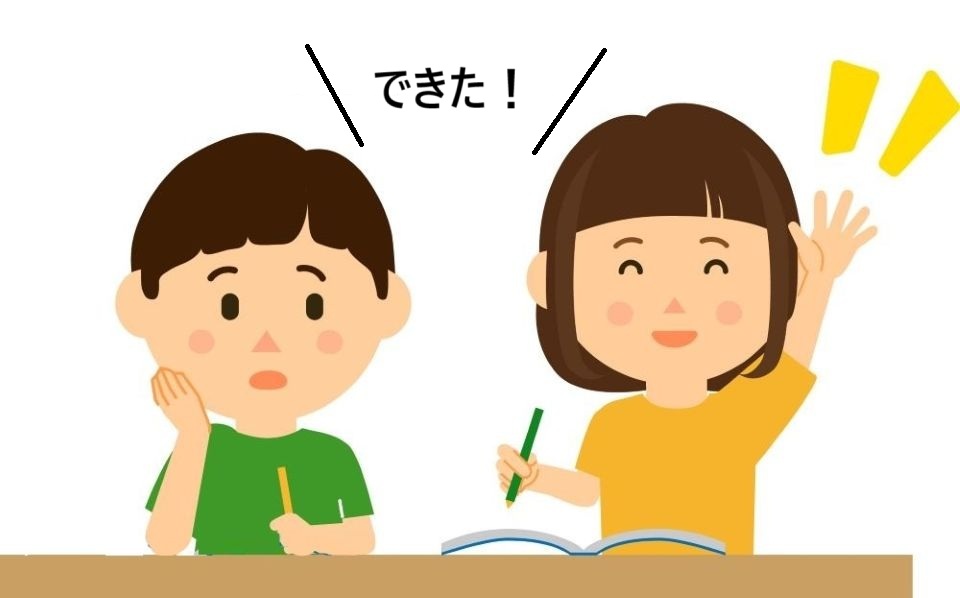
しばらくすると、「できた」という声があがりました。全体の動きにストップをかけます。早く終わったペアに空白の時間をつくらないために、次の指示を伝えます。
まだの人もいますが、一度やめてください。クリアできたペアは2回目のクリアに挑戦します。ただし、一度使った言葉は使えません。今から5分間で、何回クリアできるか頑張ってください。では、スタート!
一度使った言葉を使えなくすることで、クリアすればするほど難易度が上がっていきます。このようなちょっとした工夫が、子供たちの意欲を高めます。
ゴリラ→ラッパ→パイナップル→ルンバ→バナナ【1回目】
ゴリラ→ラッコ→コアラ→ラクダ→ダンス→すなば→バナナ【2回目】
5分の間、教師は机間巡視を行いながら、それぞれのペアに声をかけていきます。
少ない回数でクリアしたね。この言葉、よく思い付いたなあ。
すごいな。森さんと若月くんのペア、4回目にチャレンジ中。
これらの教師の言葉は、声をかけられた以外の子供たちも意外とよく聞いています。「自分たちもがんばろう」と集中力も増し、クラス全体のやる気がアップします。
この「しりとり遊び」のポイントは、「ペアですること」と「原則はかわりばんこで行うが、困ったときには相談してもかまわないこと」の2つです。
子供たちの目的は「ゴリラをバナナにすること」ですが、教師にとって、この「しりとり遊び」は、あくまでも手段であり、目的は「隣の子との関わり合いを増やし、二人で力を合わせること」になります。特に意識しているのが、
困ったときには相談してもいい
の部分です。楽しい遊びの中で体験させることで、授業や生活の場面でも、「困ったときには相談してもいい」ということを子供たちに意識させていくのです。
アクティビティ2:班のメンバーとの交流を深める「班対抗・しりとり合戦」
「しりとり遊び」の2つ目は、授業や生活の場面でよく活用される班のメンバーとの絆を深める「しりとり遊び」です、班対抗で行います。まずは、ルールの説明をします。
今から、班対抗しりとり合戦を始めます。1班から順番にしりとりをしていきます。制限時間内に答えればクリア、できなければ、アウトです。班の誰が答えてもかまいません。まずは、試しのゲームです。それでは、立ってください。
全員、笑顔で立ち上がります。
しりとりは3文字限定です。制限時間は5秒。では、1班から。バナナの「ナ」。5・4・3……
いきなりカウントダウンされて、慌ててしまい、誰からも答が出そうにない雰囲気の中、普段、自分から発表することが少ない宮城さんから声が聞こえました。
なすび
1班の他の3人から歓声が上がります。「やるな、宮城」という紅林くんの声も聞こえてきます。
オッケー。次は、2班。なすびの「び」。5・4・3……
ビ、ビスケット
5文字はダメです。2・1・アウト! 残念でした。2班は座ってください。次は3班。なすびの「び」

ワイワイと楽しそうな雰囲気の中、しりとり合戦が続いてきます。
この「しりとり遊び」のポイントは、
班の誰が答えてもいい
というところです。
これが、1周目は紅林くん、2周目は西川さん、3周目は宮城さん……というように回答する順番をあらかじめ決めて固定してしまうと、答えることができない時に、その子1人の責任になってしまいます。負けず嫌いな子からきつい言葉で責め立てられ、班の雰囲気が悪くなってしまうこともあります。班の絆を深めるために行ったしりとり合戦なのに、これでは本末転倒です。班の誰もが答えていいということは、負けた時は、答えることができなかった全員の責任ということになります。これはこれで絆が深まります。
班対抗の様々な応用アクティビティ
この「班の誰が答えてもいい」というポイントを「班の誰かが○○すれば……」に変えることで、他のアクティビティでも応用可能です。
例えば、「班対抗・紙飛行機大会」です。メンバー一人一人が飛ばせた合計距離を競い合わせると、優勝できなかった時に飛ばした距離が一番短かった子が責められることがあります(もちろん、このようなことで友達を責めない子を育てなければいけないのですが……)。そうするのではなく、一番遠くまで紙飛行機を飛ばせた子がいる班を優勝とするのです。こうすれば、たとえ自分の紙飛行機は50cmしか飛ばすことができなかった子も優勝の喜びを味わうことができます。その結果、遠くまで飛ばした子に対して、尊敬と感謝の気持ちをもつことになります。
他にも、「班対抗・大声合戦」(一番大きな声を出した子のいる班が優勝。声の大きさは、騒音計アプリなどで計測する)や「班対抗・10秒で止めろ!」(ストップウォッチの画面を見ないで10秒に一番近いタイムで止めることができた子がいる班が優勝)、「班対抗・目をつむって片足立ち大会」(目をつむって片足になり、一番長い時間立っていた子がいる班が優勝。早くアウトになった子が、まだがんばっている自分の班の友達を全力で応援する姿を見ることができる)などがあります。

ちなみに、今回紹介した「しりとり遊び」の最初の指導は、授業の隙間の時間などに行います。もちろん、それ1回で終わるようなことはしません。私は、朝の会や帰りの会などで、今回紹介したような友達と関わるアクティビティを日常的に行っていました。そのメニューの一つが、これらの「しりとり遊び」です。
普段から、いろいろな友達と楽しく関わり合わせることで、学級崩壊を防ぐだけでなく、授業の場面においても、思春期を迎えるような高学年でさえ自然な感じで友達と関わることができるようになるからです。
次回予告
6月下旬から7月上旬にかけて、多くの学校では学期末の個人面談(個人懇談)が行われます。子供たちと楽しく遊んだり勉強したりすることは大好きだけど、保護者との個人面談となると気が重いという若い先生方は多いと思います。昭和に若手教師だった私も同じ思いをもっていました。つまり、若い先生が、個人面談に対してプレッシャーを感じるのは、いつの時代も変わらないということです。
ただし、個人面談のポイントをつかみ、準備をしっかりと行えば、そのプレッシャーはかなり軽くなります。そこで、次回は、若い先生方のプレッシャーを少しでも軽くするために「保護者の信頼を得る個人面談7つのポイント」についてお話しします。お楽しみに。

俵原正仁(たわらはら・まさひと)●兵庫県公立小学校校長。座右の銘は、「ゴールはハッピーエンドに決まっている」。著書に『プロ教師のクラスがうまくいく「叱らない」指導術 』(学陽書房)、『なぜかクラスがうまくいく教師のちょっとした習慣』(学陽書房)、『スペシャリスト直伝! 全員をひきつける「話し方」の極意 』(明治図書出版)など多数。
俵原正仁先生執筆!校長におすすめの講話文例集↓
俵原正仁先生執筆!校長におすすめの学校経営術↓
【俵原正仁先生の著書】
プロ教師のクラスがうまくいく「叱らない」指導術(学陽書房)
スペシャリスト直伝! 全員をひきつける「話し方」の極意(明治図書出版)
若い教師のための1年生が絶対こっちを向く指導(学陽書房)
イラスト/イラストAC

