【校内研アップデート#05】もっと気軽に活発に! 時間と労力をかけずにできる「研究授業」のすすめ
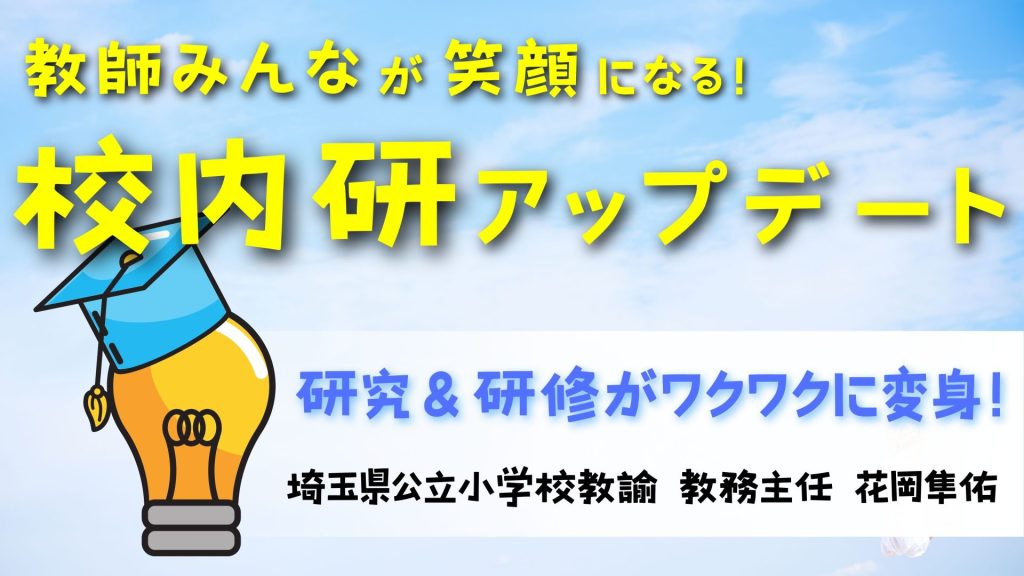
従来の固定観念を覆す新しい校内研究会「北フェス」で話題となった埼玉県公立小学校の花岡隼佑先生が、教師全員が笑顔になれる楽しい校内研のあり方を提案します。フラットな対話と自発的な参加を重視した実践的なアイデアを、若手からベテランまで全ての教師向けに分かりやすく解説します。
執筆/埼玉県公立小学校教諭・花岡隼佑
目次
負担は軽く、実りは多く。新しいかたちの研究授業
埼玉県の公立小学校に勤務している花岡隼佑(はなおか・しゅんすけ)です。連載5回目となった今回のテーマは、校内研究とセットで語られることが多い「研究授業」についてです。
【Before】年に1回の代表者による研究授業
私がこれまで勤務した学校では、年に1回、代表者を決めて研究授業を行うことが一般的でした。私自身も研究授業をした経験があり、指導案の検討や勉強会などを通じて成長してきました。そのため、研究授業の全てが悪いとは思っていませんし、「すぐになくなればいい」というような極端な考えもありません。
ただ、従来の研究授業に課題がなかったかと問われると……結構見つかっちゃいました。
課題①:“授業者、誰がやる?”問題
この問題に直面したことがある方は多いのではないでしょうか。もちろん、自ら「やります!」と立候補する方だってたくさんいますから、そのような積極的な姿勢を否定するつもりはありません。
ですが……。
「さーて、研究授業の授業者、誰やりますかっ?」
(シーン)
「……じゃあ、まだ年次が浅いですし……経験を積むために私がやり……」
「どうぞ、どうぞ!」
こんなきれいに某お笑いみたいな流れにはならないかもしれませんが、「研究授業は若手の仕事」なんていうレッテルを貼られ、押しつけるかのように授業者が決まっているのだとすれば、これは由々しき事態です。
成長したい!と自ら意欲的に引き受けるのと、受動的に引き受けざるを得ないのとでは、全く意味が異なります。
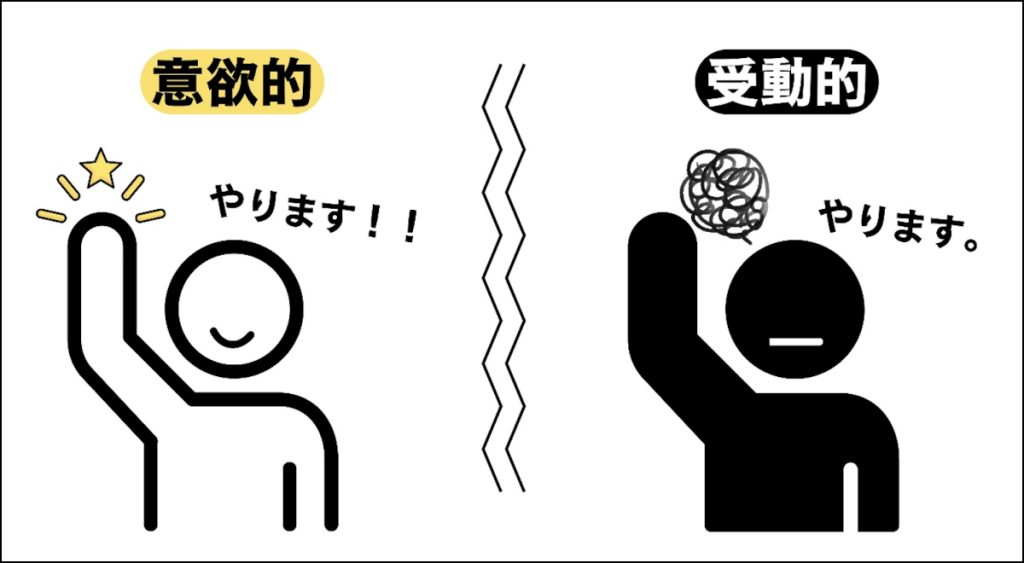
課題②:“年に1度の打ち上げ花火型研究”問題
多くの学校では、「研究授業は年に1度」というシステムが敷かれています。授業に至るまでの指導案検討や当日の準備等の労力を考えると、これが限界だというのはよく分かります。
では、この「年に1度」という頻度は本当に最適なのでしょうか。
研究授業の本来の目的は、ざっくり言うと「授業改善」です。研究授業をやること自体が目的ではなく、そこから得られた知見を今後の授業に落とし込んでいくこと=授業改善こそが最も大切な目的であるはずです。
「いやいや、あんなに大変なこと、年に何回もやれるかいっ!」
というお叱りの声が聞こえてきそうです。確かに、従来のような渾身の一撃的な授業を見せるスタイルでは無理でしょう。研究授業に向けて手持ちのエネルギーを全部費やし、終われば「やっと終わった!」と研究自体も終了してしまう「打ち上げ花火型」の校内研究では、授業改善のサイクルは十分に回りません。
課題③:“授業者に負担が偏りがち”問題
単元計画、指導案検討、掲示物作成、模擬授業……。授業者となった先生にいきなり降ってくる仕事量は膨大です。もちろん学年やブロックで仕事を手分けすることだってありますが、「もしも、当日の授業がうまくいかなかったら…」という不安から解き放たれることはありません。どんなに周りのサポートが手厚くても、その時間的・精神的負担をイーブン(平等)にすることは難しいです。
その反面、授業者がいちばん成長するというのも、紛れもない事実です。授業を構想し、参観してもらい、フィードバックをもらうことが、力をつける上で最も効果的なのは言うまでもありません。
ならば、年に1回、しかも校内の代表者数名という限定的なシステムではなく、いつでも、誰でも好きなタイミングで授業公開ができて、フィードバックまでもらえるシステムの方が、結果的に授業力が身に付き、学校のハッピーが増えると思いませんか!?

