昆虫の飼育は怖くない! 〜第3学年「チョウを育てよう」〜【理科の壺】

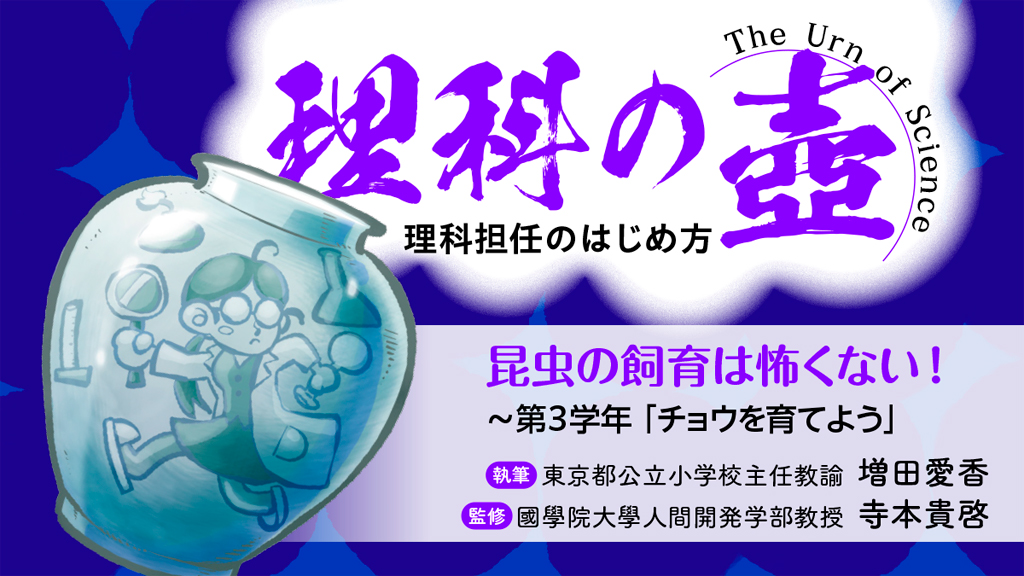
生き物の授業は、子どもたちが生き物とどれだけ関わっているかで、子どもたちの自然に対する親しみ度合いが変わります。子どもに野菜嫌いがあったとして、一緒に育てたら食べられるようになったということをよく聞きますが、生き物も同じです。最初は気持ち悪く見えるチョウの幼虫も、よくよく見るとかわいく感じられてくることが多いようです。
今回はチョウをうまく育てながら子どもたちにどのように関わらせるか、生き物嫌いを減らすにはどうするかがテーマです。先生があまり生き物に触れていないということも多いようです。一度子どもたちと一緒に育ててみませんか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/東京都公立小学校主任教諭・増田愛香
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.昆虫の飼育は好きですか?怖いですか?
第3学年「身の回りの生き物」の中では、「昆虫の成長と体のつくり」についての学習があります。多くの先生方にとって、生き物、特に昆虫を扱う単元は、「大好き!」よりも「面倒くさいな」「怖いな」と思われる方が多いのではないでしょうか。
昆虫飼育のハードルを下げ、ポイントをおさえて飼育することで、子どもたちが自然と触れ合う機会をつくってほしいと思います。そこに本物の観察でしか得られない感動や学びがあると思っています。

2.うまくいかないポイント
昆虫の飼育では、次のような「うまくいかないポイント」があります。
・花壇や校庭にエサになる植物がなく、昆虫がいない。
・昆虫だけを捕まえたので、エサがない、足りない。
・エサが不十分で幼虫が脱走し、いなくなる。
・ケースに十分なスペースがなく、チョウが羽化に失敗する。
・プラスチック製のケースの中でチョウが羽化し、羽ばたくと翅が傷ついてしまう。
・昆虫が怖くて、育てられない。
このような経験から、昆虫の飼育に抵抗がある先生は少なくありません。

