保護者とよりよい関係をつくる「学級通信」のつくり方【主体的に生きる力を育む学級経営の極意⑨】

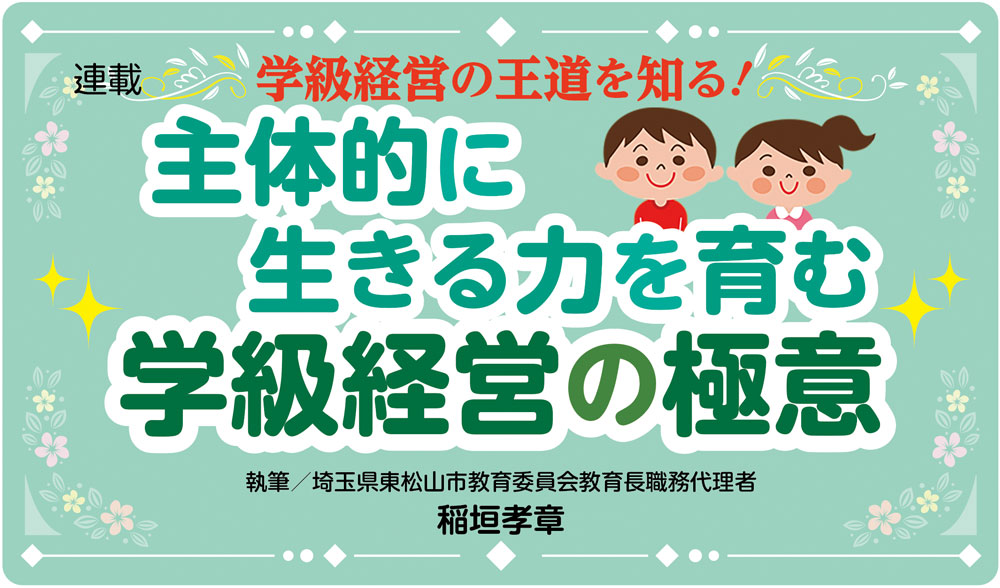
子供たちが多様な他者と関わりながら社会につながり、主体的に生きる力を育んでいくために、教師はどのような学級経営をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて基礎基本を解説します。第9回は「学級通信」のつくり方について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
「学級通信」は、学級担任と保護者をつなぐ「心の架け橋」とも言えます。保護者は、日常的な学級の子供たちの様子を知ることは困難です。「学級通信」の発行は、現在では働き方改革に逆行するように感じるかもしれません。しかし、保護者は、「学級通信」によって学級の子供たちの様子を知ることができ、学級担任との信頼関係を築くうえで貴重な資料にしています。「学級通信」の特質を踏まえ、「作成上の意義の再確認」「作成上のポイント」「表記上の配慮事項」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 作成上の意義の再確認
「学級通信」は、発行しなければならないものではありません。しかし、保護者とのよりよい関係を築くために、貴重な資料となるものです。教師からの一方通行のような単なるお知らせではなく、あくまでも相互交流としての「通信」であることが望まれます。
教師が「学級通信」に子供たちの学習や生活上のよさを取り上げ、保護者に発信します。その上で、保護者からも感想や要望、意見等も記載して返信してもらうような手立てを講じ、「通信」としての意義を踏まえて発行しましょう。
子供たちの「よさ」を共有できるようにします
「学級通信」は、子供たちの学級生活の様子を掲載していきます。その際、子供たちの学習や生活上の「よさ」を取り上げ、保護者と共有していくことが求められます。可能な限り、「よさ」を具体的な子供の姿として表現できるようにしていきましょう。

CHECK② 作成上のポイント
「学級通信」には、子供たちの学校生活での様子を保護者に知らせるため、子供の詩や作文を取り上げる等、個人名を掲載する場合があります。そのため、個人情報に関することに配慮するとともに、個々の子供の掲載回数などにも配慮することが求められます。
作成上の「7つのポイント」を踏まえます
①具体性(わかりやすく)……「算数ではこんな間違いが多いのね」
②適時性(時をとらえて)……「今、クラスで風邪がはやっているのね」
③計画性(発行回数を)………「隔週で発行されていてとても楽しみだわ」
④平等性(どの子も)…………「全員の子供の詩が載っているのね」
⑤通信性(保護者の考えも)…「他の保護者の考えもわかってありがたいわ」
⑥発信性(教育情報を)………「子供のお手伝いは大切なことなのね」
⑦信頼性(よさをとらえて)…「いつも子供たちのよいところを見てくださっているわ」

CHECK③ 表記上の配慮事項
「学級通信」は、学級担任が発行します。しかし、その責任は学校の責任者である校長にあります。学校としての発行文書なので、事前に管理職に閲覧してもらうことが大切です。わかりやすく、文意が通るようにするため、発行前に多くの人に目を通してもらうようにしましょう。
表記上の「4つのポイント」を踏まえます
①平易で簡潔な文章を…「評価規準って何かしら。先生の文章は難しくて~」
②断定的でない文章を…「先生は、『こうしなければならない』という文章が多くて~」
③誤字脱字のない文章を…「就学児ではなく、就学時ではないのかしら~」
④相手意識の明確な文章を…「計画的にやりましょう。これは子供向けの言葉?」
「学級通信」に取り上げる内容、文章表現は、教師の教育観や人間性さえも表現するものです。保護者との「心の架け橋」となり、信頼関係を深めていくような「学級通信」となるようにしていきましょう。
イラスト/イラストメーカーズ 池和子

