たくさんの人と交流する「ジグソー学習」を取り入れよう|対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #9

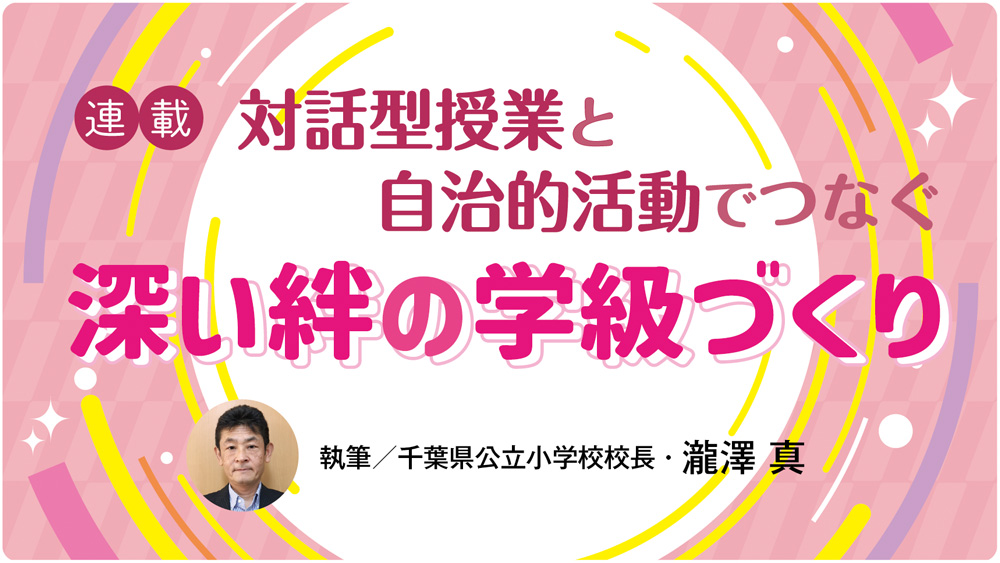
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第9回は、ジグソー学習について解説します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
ペア対話、3人組での話合いの次は、ジグソー学習
この連載では、対話型授業として、ペア対話、3人組での話合いについて解説してきました。
今回は、さらに多くの人と交流する、ジグソー学習を取り上げます。ジグソー学習自体の歴史は古いのですが、主体的・対話的な学びが脚光を浴びるようになり、再び注目されるようになりました。
なお、ジグソー学習(ジグソー法)について詳しく知りたい方は、「知識構成型ジグソー法」とは?【知っておきたい教育用語】のページも参照してみてください。
共同学習の手法は、ジグソー学習だけではありません。
しかし、ジグソー学習は、
・話し合う必要性がある
・一人一人が学び、協力しなければ成立しない
という点において、主体的・対話的で深い学びに有効な手法だと言えます。
ジグソー学習の基本手順
ジグソー学習にはいくつものバリエーションがあるので、今回は基本形を紹介します。
1.ホームチームをつくる
多くの学級では班をつくっていると思いますので、まずはその班をホームチームとします。ここでは仮に、4人の班が基本となっていることにします。
2.それぞれの課題を分担する

例えば、社会科で平安時代の貴族の暮らしについて考えるとします。そこで、「A:寝殿造り、B:食事、C:1日の生活、D:服装」の4つの課題を示し、ホームチームの4人がそれぞれ分担します。
班によって人数が異なる場合は、少ない班の人数に課題の数を合わせます。4人と5人の班が混在してるならば、課題は4つにします。そして、5人いる班は、どこかの課題に2人が参加するようにします。
3.専門家チームで集まり、学ぶ
ホームチームで「A:寝殿造り」担当になった子供同士で集まります。8班あれば、A担当が8人集まることになります。これを専門家チームと言います。上記の例で言えば、A~Dの4つの専門家チームができることになります。
そして、この専門家チームで、それぞれの分担について調べたり、話し合い考えを深めたりしていきます。例えば、寝殿造りの基本的な間取りなどを調べたり、そこでの暮らしを想像したりします。
ここでの活動をスムーズにするために、教師はあらかじめどの資料を見るとよいか、どんなことを話し合うとよいかなどをまとめた、学習の手引きなどを作っておくとよいでしょう。また、専門家チームで調べたり、話し合ったりしている際に、各グループをまわり、必要な支援や指導を行います。この時間に、いかに教師が各グループに有効な助言を与えられるかで、学習の質が変わってきます。
なお、専門家チームの人数が多い場合は、2つに分けるなどしてもよいでしょう。
4.ホームチームに戻り、学びを共有する

各自がホームチームに戻り、専門家チームで学んできたことを伝えます。他のメンバーは質問したり、意見を交わしたりします。それを順番に行っていき、それぞれの学びを共有します。ジグソーパズルのピースが集まり、絵が完成するようなイメージです。
まとめとして、この例では、班で「平安時代の暮らし新聞」を作ることにしました。

