低学年でも取り組める国語「お話づくり」のプログラミング学習
2020年度から全面実施の小学校プログラミング教育について、低学年向け授業状況を紹介します。今回は、 東京都町田市立小山中央小学校教諭&町田市小教研情報教育部・古屋一希先生による、プログラミングアプリでお話を作る国語の授業です。
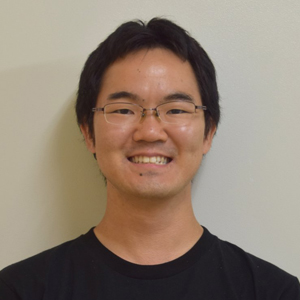
古屋一希●小山中央小学校において低学年から高学年までの担任を務めた経験を持ち、国語などの教科の中でプログラミングを活用した授業を行っている。同校の2020年度プログラミング教育のカリキュラムを担当。

目次
町田市内の全小学校に同環境を整備
今回は、東京都町田市立小山中央小学校を紹介します。町田市では市の教育振興基本計画「町田市教育プラン2019-2023」の一つとしてICT教育の取組を行っており、町田市立の全ての小学校にLTE版のノートパソコン『Chromebook』40台の導入を進めています。Chromebookは、Googleが開発した独自のOSを搭載したパソコンで、低価格で操作も簡単なことが特徴です。
町田市ではさらに、ICT活用の中核となる教員を「ICTマスター」として指名し、研究活動を行っています。
小山中央小学校では、2018年から児童用に40台、全教員に1台ずつChromebookが導入されました。これに加え、パソコンルームにはWindowsのノートパソコン40台が設置され、全学年の授業などに活用されています。
同校でプログラミング教育のカリキュラム作成を担当している古屋一希先生は、「低学年でのプログラミング教育を考えた際、国語と意外にマッチングすることに気付いたのです」と話します。「2017年度に三年生の国語で『段落を意識して、道案内の文章を書かせる』という授業を行った際、実際に組み立てられるプログラミングブロックを使ってみたところ、圧倒的な効果を得ることができました」
この経験をもとに、古屋先生は、二年生の国語でもChromebookでプログラミングアプリを使った授業に挑戦しました。国語の授業においては、「プログラミングをすることが目的ではなく、あくまで教科の指導内容を、子どもたちに理解させるためにプログラミングのブロックやアプリを取り入れています」と言います。
必修化される2020年度から、「教科の中に、いかにプログラミングを取り入れるか」と悩んでいる先生も多いでしょう。
今回ご紹介する国語の授業事例は、教科書の良さを生かしつつ、プログラミングをツールとして取り込むことで、子どもたちが自ら進んで学ぶ機会をつくる好例の一つと言えます。

『Chromebook』とは
Chromebookは、Googleが開発した独自のOS「Chrome OS」を搭載したノート型パソコンの総称で、様々なメーカーが製造しています。Windowsのパソコンのようにすべてのアプリをインストールして使うのではなく、高度な作業はネットワーク上のホストコンピュータに委ね、その入力と出力をWebブラウザで行うという設計思想のため、動作が軽快で起動時間も早いのが特長です。
町田市教育委員会によると、メリットとして「データがクラウド上に自動保存されるため、セキュリティ性と操作性に優れている。学校の共有機器としても使いやすく、低価格ながらタッチパネル機能を備え、キーボードも使用できる」といった点を挙げています。

