<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #2 徳島県石井町立石井小学校5年3組①<後編>

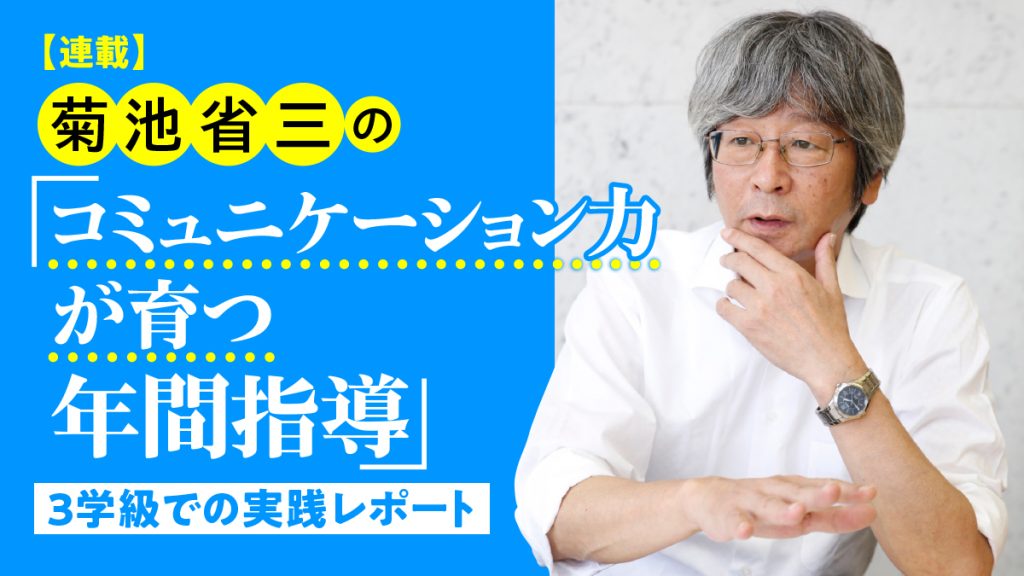
菊池実践を追試している3つの学級での授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートします。
3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、千葉の植本京介先生、高知の小笠原由衣先生。それぞれの学級をローテーションでレポートしていきますので、どうぞお楽しみに。原則的に、菊池先生の授業記録+担任のコメントという構成です。今回は、4月の堀井学級での菊池先生の授業レポート・後編です。

目次
体を動かす活動で、授業のスピードを上げる
菊池先生が新しい写真を見せながら、
「どこだかわかる?」
と尋ねると、
「見たことある」「CMだ!」
と子供たちが口々に答えた。
「これは京都です。『JRに乗って京都を観光しよう』という目的で、JR東海がポスターを作りました。このポスターは3つの言葉で書かれていて、ワードセンスがいいんです。その3つの言葉とは、まず京都を観光するCMだから、『京都』。次に、行ってもらいたいから、『行こう』。そして『そうだ』。この3つの言葉をどういう順番で並べたのでしょうか。
『自分ならこの順番でいこう』と思うことを考えましょう。付け足してもかまいません」
菊池先生がそう問いかけると、みんながノートに書き込んだ。
1分後、友達と意見交流。
「一人ぼっちを作らない。男女関係なく、いつも同じ人ばかりと話すよりも、まだ話したことがない友達と交流したいよね」
菊池先生が話すと、いろいろな子に声をかける姿が見られた。 2分後、そのままの位置で発表。
●そうだ京都に行ってみよう
●そうだ京都行こう
●そうだ行こう京都へ
「JR東海が考えたのは、『そうだ 京都、行こう。』でした」
菊池先生が答えを示し、みんなが席に戻った。
![]()
聞いて考え合う“癖”がついていない教室は、スピードが遅いものです。
教師が説明する際など、十分に理解させようとかみ砕いて話せば話すほど、子供たちにはさっと集中して考える習慣が身に付かず、さらに遅くなっていきます。
特に、低学年の担任、または担任経験が長い教師はゆっくり話す傾向が強く見られます。これでは、教室の空気はいつまでたっても停滞したままです。
話すことよりも聞くことのほうが処理速度が速いので、教師がゆっくり話す間、聞いている子供たちは集中力が欠けて余計なことを考えがちになります。授業にスピード感を持たせることが大きな鍵になります。
具体的には、子供たちを動かすことです。小刻みに問いかけて、考えさせたり答えさせたり隣の子と話し合わせたり。さらには、短い時間で書かせて意見交換をさせることがポイントです。
十分に学ぶ環境が整っていない教室は、考えるエネルギーがまだまだ弱いのです。じっくり時間をかけて考えさせてもできないのであれば、体を動かす学びの形態に持っていけばいいのです。
「ノートは作戦基地で、いっぱい書けば書くほど多くの意見を述べることができる」という話を聞きますが、現実的ではないと感じます。むしろ書いたものを読み合うだけの話し合いになってしまうというマイナス面もあるでしょう。ノートに書くことより、話し合いの場で他の人の意見を聞き、自分の意見をつくり、考え合えばいい。用意に時間をかけるより、即興力を身に付けることが、活発な話し合いを生み出します。
「菊池の授業は速い」とよく言われます。特にディベートでは時間を設定するので、子供たちは勝ちたいが故に、限られた時間内に多くの内容を話したり、質問したりするようになります。
そのスピード感が、一層迫力ある話し合いにつながっていきます。
自分の意見を考え、聞き合うことのハードル
「今日は、みなさんにワードセンスを磨いてもらいます。ぴったりの言葉を考えて、班で1つに絞って発表してもらおうと思います。さっき、3時間目の授業で出てきた人の名前を聞いていて覚えている人?」
菊池先生の問いかけに、大勢の手が挙がった。
「大谷翔平選手です」
と一人が答えると、
「みんなで学ぶ場所だから、みんなが楽しく思えるように、公の言葉を使う。今、彼は『大谷翔平選手です』と発表しました。これもワードセンスの1つだと思います。ここで拍手!」
みんなが大きな拍手を送った。
次に、大谷夫妻のツーショット写真を掲示しながら、菊池先生は、
「二人にぴったりの言葉を作ってください。もちろん、一人ひとり違っていいんだよね。まず、ノートに書きましょう」
と問いかけた。
ちょっと難しいお題だったか、鉛筆を持つ手が止まっている子も多い。
「じゃあ班になって、1つに決めましょう。決まったところから、黒板に書いてください」
さっと決めてすぐに黒板に書きに行く班もあれば、どれを選ぶかじっくり時間をかける班も。
黒板が少しずつ子供たちの言葉で埋まっていった。
![]()
自分の意見を書き、班で話し合って1つに決め、黒板に書く。単純な話し合いの流れに見えるかもしれませんが、じつはハードルが高い活動です。
まだ自己開示ができていない子供たちは、自分の意見を書くことができませんし、相互理解ができていない状態であれば、お互いの意見を聞き合うこともできません。乗り越えなければならないハードルが2つもあるのです
「4人グループなら、自分の意見も言いやすいし、いくつも意見が出てくるだろう」と思い込み、安易に取り組ませるのは、教師が子供たちに丸投げして責任を放棄しているのと同じです。

